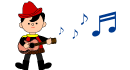COMEBACK MY DAUGHTERS

-
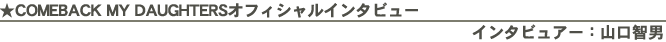
「カムバックってどういうバンド?」って聞かれたら、
やりたいことをやっているバンド――もうそう答えるだけでいいと思えるようになった
新ラインナップになったCOMEBACK MY DAUGHTERS(以下カムバック)が5作目のアルバム『Mira』を完成させた。
結成15年目にして、大きな転機を迎えた彼らが今一度、原点に立ち返って
見つけた一つの答えとも言える新作について話を聞いてみた。
――『Back In The Summer』から今回の『Mira』までの間に状況がいろいろ変わって、バンドは大きな転機を迎えましたね?
高本和英(Vo, Gt, Key) そうですね。(前ドラマーの中津川)吾郎ちゃんが抜けて、Pizza Of Deathを離れて、松原(圭甫/Dr, Key)が入って、(小坂)祐亮(Key)が逃げた(笑)。僕らは僕らで、なんで(バンドを)続けるんだろうって考えたんですけど、なんで続けたいのかわからなかった(笑)。ただ、やりたいなと思っただけでね。今回、コロムビアに移籍したのもPizza Of Deathに不満があったわけではないんですよ。本当に、ありがとうって思ってました。ただ、これでいいっていうのはなかったんですよね、ずっと。もう満足してるから、このまま続けていければいいという気持ちはなくて、もっともっとやれるはずだけど、今はこれが限界だっていうことを続けてきたと思うし、それが少しずつ進んでいる感じだったんですよ。他のバンドに比べたら、進む速度は遅いかもしれないけど、やりたいことを少しずつやりながら、少しずつ考え方も変わってきた。その進み方が遅いんで、その間にメンバーが離れていってしまったっていうのもあるかもしれないですけど、今回、Pizza Of Deathを離れて、コロムビアに行くっていうのもいわゆるインディからメジャーに行って、みたいなことも全然なくて。
――はい、それは。
高本 コロムビアの人と話した時に、「そんなおまえらの考え方もわかる。そのうえで一緒にやりたいんだ」と言われて、俺もやりたいって思ったっていうただそれだけの話で。こういう言い方はあれですけど、本当に、どこでもよかったんですよね(笑)。ただ、今回の話をもらったとき、「やりたいんだよね」ってけっこう暑苦しく言われて(笑)。
――暑苦しくですか?(笑)
高本 はい(笑)。その時、あぁ、俺もやりたいかもなって思って、それで、みんなに「どう?」って聞いたら、「いいよ」って。それが素直な反応だったんだと思います。
――そして、松原さんが新たに加わったわけですね。松原さんの加入はどんないきさつで?
戸川琢磨(Ba) 僕は前から松原に目をつけていて、僕が何か別のことをやるとき、ドラムか何か手伝ってもらおうと思ってたんですけど、吾郎ちゃんがやめてどうする?!ってなったとき、初めは試しにという感じでしたが、「やってみないか?」って誘ったんです。その流れですね。
高本 最初は、若いし、どんな奴かわからないしっていう心配はあったんですけど、何て言うのかな、すごくギラギラしてたんですよ。たぶん、それは彼が田舎者だからだと思うんですけど(笑)、音楽をやることに対して貪欲だった。普通に考えたら、そういう奴とバンドやるのが一番楽しいはずなんで、僕はテクニックよりも何よりもそこに惹かれました。こいつギラギラしてて最高だなって思ったんですよ。
――松原さんはカムバックについては?
松原 もう10年ぐらい聴いてたんですよ。だから、誘われた時はうれしかったですね。感情を表に出さないってよく言われるんですけど、内心ではメチャメチャうれしくて。
高本 いや、ギラついてるのバレてたって(笑)。
――サポートから正式にメンバーになるきっかけは、どんなことだったんですか?
高本 何だったんでしょうね? 助けてもらいたい、何とかしてもらいたいって、みんな突っ張ってるから、誰にもそういうことは言わないと思うんですけど、松原には何か、「しんどいから手伝ってくれ」って言えたのかな。松原にとって僕達は先輩で、バンド・キャリアも長いんですけど、割とどん臭いところも見せられたんですよ。ホント変な理由でメンバーが抜けるとか、その時の僕らの対応とか、カムバックの飾らない姿を短い期間で見せることができたのは大きかったのかな。
CHUN2(Gt) それと、バンドマンってそれぞれにバンド感みたいなものがあると思うんですけど、松原はバンドに対する気持ちが真っ直ぐだった。そういう面でもカムバックとはすごくフィットする感じだったんですよ。
――年齢の差は気になりませんか?
高本 ほとんど気にしたことないですね、彼に関しては(笑)。
CHUN2 この見た目ですから(笑)。
高本 僕らよりも老化が激しい。すぐ寝ちゃうんですよ。むしろ肉体的にはほとんど変わらないんじゃないかって(笑)。だから気にならない。走っても歩幅も狭いし(笑)。いい空気を作ってくれてますよ。(歳の差を)すっ飛ばしてくれてます。
――4作目の『OUTTA HERE』にひきつづき、今回もニューヨーク・レコーディングでしたね?
高本 前回のレコーディングに悔いがあったんでしょうね。
戸川 うん、そうだね。
高本 もちろん、それだけが理由じゃないですけど、一番はそれですね。『OUTTA HERE』の出来に悔いがあるわけではないんですけど、段取りも含め、自分達が馴染んでいないぶん、うまくできないところもあったんで、もし次行ったらっていうのはみんな考えてたと思うんですよ。そういう意味では今回、みんな悔いがないようにやったんじゃないかな。
戸川 バタバタでしたけどね。
高本 レコーディング直前に祐亮が抜けて、最悪の状況でしたけど、レコーディングの目的は、いい作品を妥協なく作るってことだけなんでね。バタバタではあったんですけど、逆に、いい作品を作ることしか考えられなかったんでレコーディングそのものはシンプルになってよかったです。
――とりあえずは、いい作品を作るだけだ、と?
高本 そうですね。せっかくニューヨークに来ているんだから みんなで楽しみながら、いい作品を作ろうってことしか考えてなかったですね。 説明するのは好きじゃないし、うまく喋れる自信もないから、 聴いた人が判断してくれればいい。
――今回の『Mira』は『OUTTA HERE』の延長上で、ある意味イレギュラーな作品だった『Back In The Summer』の経験が生かされている作品になりましたね。三十路をとうに過ぎた人達に使う言葉じゃないとは思うんですけど、すごくハートウォーミングな作品だと思いました(笑)。
高本 ハートウォーミング?!
CHUN2 はははは。
――とても心温まる作品なんだけど、でも、ちょっぴりせつない(笑)。
高本 はぁ、ハートウォーミングですか?(笑)
――あれ、ちょっと違いますか?
高本 いや、どうだろう。わからないです。俺達ハートウォーミングだよねって会話したことないから(笑)。
CHUN2 それちょっと気持ち悪いよね。
戸川 次、ハートウォーミングで行こうよって(笑)。
CHUN2 それ怖いよ。
高本 でも、いろいろなことがあって、状況は変わっているけど、とげとげしい気持ちはそんなに表に出てなくて。
――うんうん。
高本 強い決断をしたとしても、そういうのを掲げていく人間でもないんですよね、カムバックって。残された人間でやってやるぜ、みたいなところもない。ゆっくり時間をかけてやさしく受け入れていったあいつはやめたけど、しかたないかみたいな気持ちがレコーディング中にやってきてたのかな。そういうほわっとした気持ちが出たのかもしれないですね。
――『Mira』を聴いて、改めてこの人達はどんなにとんがったことをやっても、結果的に温もりある音になるんだなって感じたんですよね。
高本 ありがたいですね、それは。
――今回、こんな作品にしたいとか、こんな音にしたいとかっていう青写真はどんなふうに考えていたんですか?
高本 レコーディング前にバタバタしていたこともあって、はっきりとした青写真を持っていくことはできなかったんですよ。ただ、いろいろあったからこそ、一方的にこれだっていうものを押し付けるのではなく、聴いた人がいろいろな景色を思い浮かべることができるものにしたかった。説明するのは好きじゃないし、うまく喋れる自信もないから、聴いて判断してもらえればいい。「この人達、大丈夫なんだ」って思ってもらったり、「終わったな」って言われたり、それはそれでいいなって(笑)。
――米英のインディ・ロックに共鳴しつつ、オーケスタル・ポップとかアメリカーナなルーツ・ロックとかという言葉で表現できるサウンドとか曲とかが現在のカムバックの基本路線なのかな、改めて思いました。
高本 そうなんですかね?(笑) 最近、それがわからなくなってきてるんですよね。確かに洋楽は好きだから、そこそこ新譜も買ってるし、それがよかったらメンバーにも薦めますしね。たぶん、そういうのがメンバーそれぞれにあるんじゃないかな。ただ、そういうふうに言われるのはうれしいですけどね、リアルタイムのバンドとしては。でもまぁ、好きなものを好きなように各々が表現しているだけで、意識してそこで何かを打ち出そうとはしていないですね。
――そういう意味では、今回、アルバムの後半はメンバーの趣味という以外、特に一貫性を見出せない、いろいろなタイプの曲が並んでいるじゃないですか?
高本 はははは、そうですね。
――そのへんは『Back In The Summer』を作ったからこそかもしれないですけど、新境地として楽しめました。
高本 こういうふうに思われたいって気持ちが薄れてきたと言うか、聴き手に任せてると言うか、カムバックはこれなんだっていうのがないんですよ、今回は特に。もちろん、こういうところに気づいてくれたらうれしいなってことは各々やってると思うんですけど、でも、昔からあんまりなかったですけどね。何々系ですって掲げたこともない。それよりもおもしろいほうがいいだろうって考えてるんで。
――新境地と言える曲の一つ、7曲目の「Alone in the dark」はサイファイなサーフ・ロックですね?
CHUN2 おぉ〜。
高本 その曲は、うちらに暑苦しいオファーをくれたコロムビアのスタッフがUSインディ好きで、こんな俺らを誘ってくれてありがとうという気持ちもあって、あいつが喜ぶ曲を1曲作ろうじゃないかって作りはじめたんですけど、全然できなかった(笑)。かなり難航して、いろいろなパターンを試した結果、こういう形に落ち着きました。僕はザ・タイド(※ロサンゼルスのギター・ポップ・バンド)みたいなサウンドにプラス、90年代のエモっぽいメロディというイメージで作ったんですけど、みんなそれぞれに解釈が違ったんで、すごく変な感じの年代不明の曲になりましたね。
――CHUN2さんのギターはどんなイメージで弾いたんですか?
CHUN2 そのスタッフがちょっと前のエモが好きなんですよ。だから、そんな感じの曲になりつつあったんですけど、個人的にはそういうの今、興味ないなぁって(笑)。でも、基本的なラインはTK(高本)がもう組んでたんで決まってたんですけど、それを何かの拍子にアップテンポでやってみようかってなったとき、a-ha(※主に80年代に活躍したノルウェーの3人組ポップ・バンド)の「テイク・オン・ミー」のフレーズをふと思いついて、これ合うねって笑いながらやってたら……。
戸川 違うよ、キャップン・ジャズ(※89年〜95年まで活動していたエモの先駆的バンド)のほうだろ?
CHUN2 そうそう、それこれから言うから(笑)。そうなんですよ。「テイク・オン・ミー」はa-haじゃなくて、キャップン・ジャズがカヴァーしているほうのイメージだったんですよ。ちょっとパンキッシュで、イメージ的にはサーフ・ロックと言うか、僕はビーチ・フォッシルズ(※ブルックリンのインディ・ロック・バンド)みたいなアーバンなね、メロディは盛り上がりきらないんだけど、けっこうグッと来るところがあって、そういうところがすごく都会的だなってイメージ的にはそんなふうに考えてました。
――僕はデルタ・スピリット(※カリフォルニアのインディ・ロック・バンド)を思い出しました。
高本 ああ。好きですね。
CHUN2 デルタ・スピリットはいいですよね。
高本 デルタ・スピリットに関して言えば、オルタナ・カントリーからああいうことをやったじゃないですか。そういう意味では励みになったと言うか、自分の中では理由づけができたんですよね。彼らがこの間リリースしたアルバムは壮大な曲ばかりだったじゃないですか。これまではいろいろなタイプの曲にトライしたい気持ちと、アルバムを統一して世界観を固めるほうがいいという気持ちが割とせめぎあってたんですけど、今回は、そういうのがグチャングチャンでもおもしろいやって思えたんですよね。 『Mira』は自分達の本当に素に近いのかもしれない
――スウィンギンなダンス・ナンバーの「Steal her lips」からの「Alone in the dark」の流れはかなりびっくりでしたよ。
CHUN2 そうですね(笑)。
戸川 でも、この曲順、大好きだよ。
高本 ね。自分達の本当に素に近いのかもしれない。ああいうのもやりたいよねって言った後に、こうのもやりたいよねって。今までだったら、こういう曲を揃えていこうよっていうのが強かったかもしれないですけど、いいんじゃないって雰囲気になったと言うか、今のバンドの特権と言えば特権ですよね。昔のバンドも聴けるし、今のバンドも聴けるっていう。
――ラテンっぽい「Tornado」の歌詞は戸川さんが書いたそうですね?
戸川 高本から「1曲書いてみない?」って言われたんで、「じゃあ書いてみるよ」って途中まで書いたところで、「こんな感じでどう?」って見せたら、「じゃあ、英訳もお願い」って言うから、「ごめん日本語でもいい?」「いいよ」って今の形になりました。
高本 心境の変化があって。このメンバーだったらもう委ねてしまって、曲がおもしろくなるならいいだろうって。もちろん、1曲1曲に対するこだわりはあるんですよ。1曲1曲詰める作り方は変わってないんですけど、さっきも言ったように自分達がどう見られたいっていうのがなくなった。カムバックはカムバックで、どういうバンドって聞かれたら、やりたいことをやっているバンドだって(笑)。もうそう答えるだけでいいなって思えるようになった。今回、12曲中4曲、日本語で歌っているのもそういう考えからで、カムバックをよりオリジナルのものにするなら日本語の歌も試してみたらおもしろいだろうと思ってトライしてみたんですよ。
――その「Tornado」の次の「sciolism」は戸川さん作曲のインストで、こういうのは何て言うんですか? アバンギャルドって言うんですかね。これはどんなイメージで作ったんですか?
戸川 僕のイメージだと80年代のキング・クリムゾン(68年結成のイギリスのプログレッシヴ・ロック・バンド。11年に解散)。楽器があの人達、エレクトリックなんで、自分達が使ってるようなものに置き換えて、コミカルな乗りにもしたいなっていうのもあったんで、そのとき思い浮かんだのがブラジルのジャズ・ミュージシャンのヘルムート・パスコール。その人の音源を、ここ数年で何回か聴くことがあったんですけど、いいなって思ってたんで、その雰囲気をパッケージしてみました。こういうのが入ったら作品的にもとんがった部分が出るのかなって。
――ああ、なるほど。今回の曲順、僕もすごくいいなって思います。カムバックらしい世界観が後半、多少とっ散らかるけど、最終的にはらしいところに落ち着くというストーリーがあるじゃないですか?
戸川 『OUTTA HERE』の曲順もすごくよかったんですけど、普通のことをやっちゃうと、後半だれちゃうアルバムってけっこう多くて、今回、こういう曲順にすることでそういうのが避けられたかなって。
――そうですね。レコーディングはけっこうバタバタだったそうなんですけど、改めて振り返ってみてどうですか?
戸川 『OUTTA HERE』の時、初めてってことで気合が入りすぎてた部分があったんですね。そこを解放したらよりよくなるんじゃないかなってところまで解放できた気はしました。こうしなきゃいけないって部分の、こうしなきゃと、こういう方向もある、こういう方向もあるっていう選択肢も増えたと思いますし、メンバーが直前でいなくなっちゃって、4人で行くしかないって覚悟が割りと出た部分もあるような気もしますね。
――今回、ニューヨーク滞在中に前回のような事件は起きなかったんですか?
CHUN2 事件って言うか、「Alone in the dark」のビデオあるじゃないですか。あれの撮影の前、バラマツ(松原)がずっと不安そうな顔をしてたんですよ。「やばいやばい」って言ってるんで、「どうしたの?」って聞いたら、ビデオの撮影でスタジオからセントラル・パークまで走らされると思ってたっていう(笑)。実際に走ったらものすごい距離なんですよ、5キロぐらいあるんじゃないかな。
高本 ビデオに公園が映ってるじゃないですか。あの公園をどうやらセントラル・パークだと勘違いしたみたいで(笑)。 CHUN2 初日からずっとそれが不安だったらしいです。
戸川 それで早起きして、早朝、セントラル・パークまで歩いてみて、その遠さを知ったうえで不安がってた(笑)。
CHUN2 ここを走らされるんだって(笑)。
――あのー、撮影の前に確認しようとは思わなかったんですか?
松原 言ったらバカにされるんじゃないかって(苦笑)。
CHUN2 バカにするっておかしいだろ。それとこいつ、ニューヨークには20日間いたんですけど、その間ずっとイスで寝てたんですよ。
高本 宮本武蔵の生まれ変わりかと思いました。
――ちゃんとベッドはあったんですよね?
CHUN2 もちろん。でも、そこがよかったみたいです。
高本 だから、入るべくして入ったんですよ、カムバックに。それを見た時、また普通じゃない奴が入ってきたよって思いましたね(笑)。
2013/07/03 Release
 Mira
Mira
COCP-38033 / ¥2,625(税込)