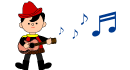寺神戸亮
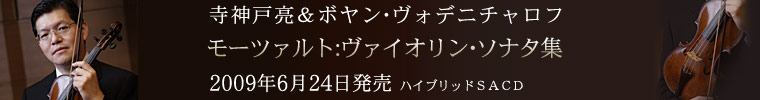
-
モーツァルトのヴァイオリン・ソナタが、実は・・・
モーツァルトのヴァイオリン・ソナタが、実はモーツァルト自身によって「ヴァイオリン伴奏付きピアノ・ソナタ」とされていたことは、ご存知のことも多いことでしょう。しかしながら従来、いわゆるモダン楽器での演奏において、その意味するところ、そしてその魅力について「なるほど」と思える演奏は、そう多くはなかったのではないでしょうか?「ピアノ・ソナタ」の側面を前面に出せば、ヴァイオリンの魅力が伝わりきらない・・・かといってヴァイオリンが思い切り演奏すれば「ピアノ・ソナタ」としての側面は後退する・・・隔靴掻痒の感は否めませんでした。 -

ALBUM 2009/06/24 Release COGQ-38 ¥3,150(税込)SACD 2ch、5.0ch CD-Audio
デンオン・アリアーレ・シリーズ20周年記念盤
モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ集
1. ヴァイオリン・ソナタ第25番 ト長調 K.301(293a)
2. ヴァイオリン・ソナタ第28番 ホ短調 K.304(300c)
3. ヴァイオリン・ソナタ第29番 イ長調 K.305(293d)
4. ヴァイオリン・ソナタ第30番 ニ長調 K.306(300l) -
アルバム『モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ集』の魅力
寺神戸によるオリジナル楽器での演奏は、そういった意味で、楽曲の真価を知らしめる待望の録音となりました。寺神戸が、楽曲の作風・様式の違いからバロック(K.301,K.304)とクラシカル(K.305,K306)の2種のヴァイオリンを使い分けている(音色の違いに耳を傾けるのも一興ではないでしょうか?)一方、フォルテピアノは、モーツァルトが、これらの曲を作曲した旅の途中で出会い、おおいに触発を受けたとされるシュタイン製の楽器の精巧なレプリカ。寺神戸と長く共演を続けている名手ボヤン・ヴォデニチャロフがこの楽器を弾けば、思い切り良く演奏しても決してヴァイオリンを覆い隠してしまうことはありません。互いを引き立てあう透明な響きによって、(モーツァルトが書いたままに特別な苦労をすることのない演奏によって)おのずと主役と脇役の交代が鮮明になるさまは、楽曲の魅力を再発見させてくれることでしょうか。加えて、この録音が、いわゆる《ワン・ポイント録音》によって収録されたことにも触れておきましょう。ミクシング操作による補正をせず、会場で響いたそのままの収録を可能にしたのは、オリジナル楽器だからこそ成し得た完璧なバランスがあったからこそ。サラウンド音声もミクシングをしていない、5チャンネル・ワンポイント録音です。濁りの全く無いクリアなサウンドは、リスナーの皆さんを、モーツァルトの時代にタイム・スリップさせてくれることでしょう。
流れるような曲想で始まるK.301、母を亡くしたモーツァルトの心情を反映したといわれるK.304の劇性、2つの楽器が華麗に協奏するK.306など、寺神戸と長年の盟友による、清冽にして親密な対話が魅力的なモーツァルトを、是非ご堪能いただきたいと思います。
最後に、寺神戸の信頼厚いプロデューサー、ゲルハルト・ベッツによるプロデューサーズ・ノートをどうぞ。これは、録音現場を知る人間による説得力のある内容で、CDのブックレットには掲載されていない、ここだけの読み物です。
-
モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ集 プロデューサーズ・ノート
この10年以上の間に寺神戸亮と一緒にやってきたいくつもの録音のことを振り返ると、最初の頃はモーツァルトばかりやっていたことに気がつく。ヴァイオリン協奏曲に弦楽五重奏曲。もちろん偶然にすぎないのだが、いずれにしても私は寺神戸のことを単なる一バロック・ヴァイオリン奏者と思ったことは一度もなかった。そんな私でも、この録音の直前に寺神戸亮とボヤンがリハーサルしているのを聴いた時には、彼ら二人がとても自然に、また自分たちのことをとてもよく理解した上でモーツァルトのソナタを演奏していることに驚かないわけにはいかなかった。それは別に彼らが作品の最初から最後まで一様に、平板に演奏していたという意味ではなく(彼らは例えば強弱やフレージングなど、楽譜に指定されていることはすべてきちんと実行する)、自分たちがやっていることを正確に理解していたということだ。というわけでプロデューサーとしての私の仕事は、あくまでも背景に留まり、彼らの演奏に表現や強弱の上で不釣り合いやアンバランスがないかどうか、注意深く聴き、見守っているだけでよかった。
フォルテピアノと初めて出会い、その音を聴く時はいつもわくわくドキドキする。フォルテピアノはモダン・ピアノと比べると、(聴き手の側から)音楽的に見ても(サウンド・エンジニアの立場から)技術的に見ても個々の楽器ごとの違いがはるかに大きい。今回私たちが使った、1788年製アンドレアス・シュタインのコピーはサウンドに温かみがあり、音色も豊かで変化に富んでいるが、大がかりなドラマチックな音楽にはあまり向いていない。実際、音量的にはヴァイオリンにもわずかながら劣っているほどで、少なくともステージ上で聴いている限りはそうなのだが、ホールの席から聴いてみると2つの楽器のバランスは驚くほど良かった(サラウンド・チャンネルを聴くとそれがよく分かる)。そこでメイン・マイクロフォンに入るバランスを調整するために、ヴァイオリンを普段より少しだけ遠くに、ピアニストのすぐ横に配置することにした。それによって二人の奏者の位置関係が視覚的にも音響的にも改善された。唯一の問題はピアニストが自分の出している音を十分にはっきりと聴き取れないことだったが、その解決策として彼の耳の方に向けて小さな反射板を置くことにした。
フォルテピアノの繊細なサウンドはこれらの音楽の気分、精神に申し分なく合っているように思える。今回録音されたソナタにはどれもかなり控えめでとりすました感じがあって、(協奏曲風に)2つの楽器を対比させるといった効果はほとんど使われていないし、2楽章しかないソナタでは調を対比させることもできず、ドラマチックな終楽章や急速な終楽章を置くこともできない。だがそのように技術的に制限された枠組の中にも、なんという豊かさがあることだろう。モーツァルトはこれらのソナタで真の音楽的ミクロコスモスを探求し、その印象をフォルテピアノの変化に富んだサウンドが強めている。フォルテピアノがピアニストの指の動きに即座に追随して、アタック、強弱、音色の微妙なニュアンスを作り出している──ボヤンがよく言うように、フォルテピアノは「ただ頭に思い描いただけで、実際に は弾いたか弾かないかぐらいの微妙なニュアンスまでをも現実のものにする」のだ──それによって、たぶん多くの皆さんがこれまでに聴いたことのない構造をはっきり と聴こえるようにすることができた。
リスナーの皆さんにもこの素晴らしい体験を一緒に楽しんでいただければ幸いである。
ゲルハルト・ベッツ
(訳:渡辺 正)