

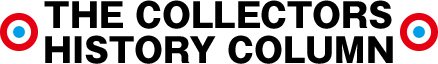
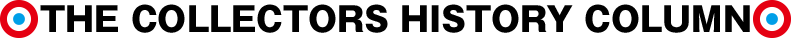

初めて吉田仁(SALON MUSIC)のプロデュースで臨んだ『UFO CLUV』は、チャート的に好成績だったわけではないが、関西圏を中心にスマッシュヒットとなったシングル“世界を止めて”に引っ張られ、じわじわとセールスを積み上げていった。当然、レーベル側やスタッフからは「“世界を止めて”に続くヒット・シングル」を要求されるようになるが、そもそも狙って“世界を止めて”を書いたわけではなかった加藤ひさしは、シングル候補曲作りに四苦八苦することになる。一時は、ドラマティックなメロディを持つ“真夜中の太陽”が、次のシングル候補と目されていた時期もあったそうだ。
クラシック・ロックへの強い愛情と、同時代のサウンドへの目配りが共存していた『UFO CLUV』と比べると、次のアルバム『CANDYMAN』は加藤ひさしの趣味性に傾いた曲が多い。前作の16ビート路線を継承した“恋をしようよ”がある一方で、この頃加藤が熱心に聴き直していたレイト60s〜アーリー70sバブルガム・ポップの強い影響下にある“MOON LOVE CHILD”や、シド・バレットやトゥモロウのサイケ・ポップ感を現代風に料理した“プリティ・ガール”など、曲は見事に粒揃い。かといってルーツ回帰にばかり没頭していたわけでもなく、コレクターズ流のパワー・ポップを極めた会心の1曲“キャンディマン”や、当時ポップ・マニアの間で局地的な盛り上がりを見せていたジェリーフィッシュからの刺激を感じさせる“愛ゆえに”“Rock'n Roll Star”も収録。ラストを飾る異色のブルース・ロック“ネイビーブルー”には同じ時期のポール・ウェラーを思わせるヘヴィネスがあるし、いかにも加藤ひさしらしい語り口のメッセージ・ソング“ザ・バラッド・オブ・ロンサム・ジョージ”もここで生まれている。こんな風に「ソングライター=加藤ひさし」の魅力がカラフルに開花した『CANDYMAN』は、ポップ・アルバムとしては間違いなく傑作の部類に入る1枚だろう。
楽曲のクォリティの高さを印象づけた反面、『CANDYMAN』には周囲が期待していた「“世界を止めて”に続くヒット・シングル」という役割を担えそうな曲が含まれていなかったし、前作で獲得したバンド・グルーヴをより発展させるような性質のアルバムにもなっていなかった。しかし『CANDYMAN』はアルバム・チャートで初めてトップ30入りを達成、テレビなどメディアにも積極的に露出するようになり、「次なるブレイク」へと期待を繋いでいる。

『CANDYMAN』発表後も、「“世界を止めて”に続くヒット・シングル」問題は加藤を悩ませ続けていた。「『Free』には“Dreamin'”や“スィート・シンディ”のような飛び切りのポップ・チューンが揃っているのに?」と不思議に思う人がいるかもしれないが、当時のコレクターズは「もっと突き抜けた、コマーシャルなシングル向きの曲」を常に求められ、ハードルをどんどん上げられていたのだ。前作・前々作に続いてプロデュースを引き受けた吉田仁は、バンド内の煮詰まり始めた空気を察知。ここで思い切って、ロンドンでのレコーディングを敢行することになる。
時代はブリットポップ全盛期の95年。レコーディングに使ったメゾン・ルージュ・スタジオでは、ブラーのデーモン・アルバーンが、やがて『ザ・グレイト・エスケープ』に収められる曲をタイプライターに向かって苦悩しながら書いていたという。まさに「オアシスVSブラー」戦争の真っ最中だったロンドンに、コレクターズはタイミング良く足を運んだわけだ。そういう時代の空気を想い返しながら、この『Free』というアルバムを聴き直してみて欲しい。
『Free』のエンジニアを担当したケニー・ジョーンズは、それまでザ・スミスやザ・ラーズも手掛けてきたベテランで、実はオアシスとも縁が深い。ケニーは加藤より1つ年上で、バンドが欲し続けていた伝統的な「ブリティッシュ・サウンド」も、90年代当時の「旬」なサウンドもよく理解していた。
ロンドンでは加藤ひさしが急病で倒れ、レコーディングは順風満帆とはいかなかったが、日本でうまくパッケージにできなかったバンドのダイナミズムやライヴでの躍動感が、本作には見事に封じ込められている。そこに着目すると、『Free』は前作『CANDYMAN』と対照的なアルバム、と言えるだろう。作家性の強かった『CANDYMAN』に対して、『Free』は「バンド=コレクターズ」の旨味を引き出すことに集中していた。
引き続きヒット曲を求められ続けた加藤は、“Good-bye”という名曲をものにした。イントロからコーラスに至るまで、これでヒットしなかったらどうするんだというほど徹底的にキャッチーに作られたこの曲も、シングルは大きな反響を得られずに終わったから不思議だ。この曲は後の2002年にトリビュート盤『BEAT OFFENDERS』で、くるりがカヴァーした。
アルバム全体を見ると、シニカルな歌詞のロックンロール“フライング・チャーチ”や、英国録音らしい憂いを湛えたアレンジの“ファニー・ストレンジ・タウン”、トラフィックを彷彿させる変拍子を交えた“フリーダム チルドレン”など、ヒット性云々というプレッシャーに逆らっているような印象がある。加藤ひさしが長髪に口ヒゲをたくわえていたのもちょうどこの時期で、後年「あの頃は反抗期だったのかも」と述懐していたのが印象的だった。「ロックなコレクターズ」を味わえる骨太なアルバムで、決して悪いセールスでもなかったが、『Free』も「本格的なブレイク」には今一歩届かずに終わった。
この95年は、9月に穏やかなフォーク・ロック調のCDシングル“素晴らしき人生”(隠れた名曲“ミッドナイト・レインボー”とのカップリング)、そして10月にリミックス・ヴァージョンを含むコロムビアでは初めてのベスト・アルバム『GOLD TOP』をリリースした、ある意味「節目」の年。3作続いた吉田仁とのタッグもここで一区切りし、次作では大胆な方向転換を余儀なくされる。
荒野政寿(CROSSBEAT)