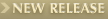“長富彩オフィシャル・インタビュー”
同じ空間を共有する人間を不思議な気分にさせてくれるピアニスト

まるで劇画から飛び出してきたかのような少女である。少女といっても、実年齢は23歳なのだが。ピアニストであると知らされていなければ、AKB(=秋葉原)な雰囲気を漂わす、か弱い少女にしか見えないだろう。
「私、もしピアニストになっていなかったら、スイスに行って、ハイジみたいにヤギのチーズを食べながら、ホルンを吹くような生活をしていたと思います」
しかし、ドレスに身を包み、ピアノの前に座れば、まるで別人のように情感を込めた演奏を披露する。
長富彩とは、同じ空間を共有する人間を不思議な気分にさせてくれるピアニストだ。
可愛らしい無垢な笑顔の裏には、どこか社会に、大人たちに、そしてもしかしたら世の音楽家たちに対しても、斜に構えるようなところがある。
その理由は彼女の人生を追うことによって、少しだけ理解できるだろう。
もし不合格だったら、今頃私はピアノを続けていなかったかもしれません

長富は、オペラ歌手の父と、ピアノ伴奏者だった母との間に1986年11月19日に埼玉で生まれた。
生後直後から音楽に親しみ、ひとりで立ち上がれるようになるとリビングに流れるマンボの曲にあわせてお尻を振って踊っていたという。幼児期はレーザーディスクで見たロシアの雪の並木道と、その映像に流れるチャイコフスキーの音楽がお気に入り。美空ひばりの「川の流れのように」も大好きで、そのCDを母におねだりしたのが初めてのわがままだった。
音楽に近しい環境にあり、自宅に母のグランドピアノがあれば、長富がピアノに興味を示すのは自然な流れだっただろう。しかし母は娘をピアノに触らせようとはせず、むしろピアノから遠ざけた。娘が「ピアノを弾きたい」と言い出したら、ピアニストである自分は、母であることを忘れて娘に厳しく指導してしまう——それが分かっていたから積極的にピアノに導こうとはしなかったのだ。
幼稚園に通い始めた長富は感受性の豊かな少女に育っていた。父が出演するオペラの舞台に行き、父が演じる役が死に直面する場面になると、ストーリーなど理解できるはずもないに、父親が死んでしまったと思い込んで観客席で号泣した。幼稚園では、言葉を話し始めるのは誰よりも早かったが、他の子たちが平仮名を覚える時期になっても彼女は平仮名を覚えようとはしなかった。
「他の子より、何かが欠落していたんだと思います。私は脳天気だった。そして幼稚園では問題児だった。いつも悪さをして『ゴキブリばあさんの部屋』と呼ばれた暗いお仕置き部屋に閉じ込められていたんですけど、私はその部屋でひとり騒いで遊んでいたんです」
頻繁に幼稚園の先生から「今日は悪さをしたので、叱りました」と母に報告があったのだが、娘に問い質すと本人はその叱られた事実すら忘れている。この頃から自分に都合のいいことだけを記憶にとどめ、都合の悪いことには関心を示さないようなところがあった。
 ある時、同い年の女の子が幼稚園でピアノを弾いて人気者になった。すると根っからの目立ちたがり屋である彼女はそれに嫉妬して、母に土下座をしながら「ピアノを教えて」とお願いする。
ある時、同い年の女の子が幼稚園でピアノを弾いて人気者になった。すると根っからの目立ちたがり屋である彼女はそれに嫉妬して、母に土下座をしながら「ピアノを教えて」とお願いする。
「人気者になるためだけにピアノを弾きたかったのに、ぜんぜん楽しくなくって、すぐに〝こんなはずじゃない〟と思いました。いざ練習が始まると、母がスパルタの〝先生〟になったんです。ピアノの練習はもう戦争。母が怖かったです」
しかし、ピアノを弾き始めてすぐに、彼女の才能が他の子と違うと周囲は自覚する。母は娘がピアノを弾き始めた日のことが忘れられない。
「初めてですからわけもわからない弾き方をするのに、ひとつの音楽にはなっていた。これは将来ピアニストになれるかもしれない……とその日に思いました」
ところが長富は小学校に通う頃になっても楽譜が読めなかった。鍵盤の位置もうる覚え。それでもブルグミュラーをわずか二ヶ月で終了し、ピアノ教室の指導者を驚かせた。
「楽譜も感覚で読んでいたんだと思います。CDを聴いて、楽譜に書いてある音符の位置で感覚的に弾いていた。なぜ自分が弾けたのか、その原理は分からなかったですね。私はハノンとか、基礎練習が大嫌いだったんです。曲を弾くことで基本的なテクニックは身につけていった。この時期に基礎を怠っていたことで、あとあと苦労することになるんですけどね(苦笑)」
小学4年生になり、父の友人であった東京音大講師の御邊典一(おんべのりかず)に師事する。「10年にひとりの感性かもしれない」が挨拶代わりの言葉だった。御邊は長富の個性がコンクールに向いていないことを見抜いていたが、チャレンジしてみることを決断する。そのコンクールで長富は〝事件〟を起こした。
課題曲はバッハだった。しかしレッスンとはまるで違う弾き方をしてしまい、あえなく予選で落選する。
「前日にダイアナ妃の葬儀があったんです。テレビのニュースを見ても、その話題一色。だから私、『祈ろう』と思って、まるでレクイエムのようにバッハを弾いたんです。ダイアナ妃が大好きだったわけでもないし、コンクールで目立とうとしたわけでもない。自然な感覚でそういう弾き方をしてしまいました」
これは自分の感性の赴くままピアノを演奏してきた彼女を端的に現すエピソードだろう。もともと彼女はピアニストならば誰もが通るコンクールの道を嫌っていた。
「『コンクール? 勘弁して、そういうの』って感じでした。私は目立ちたがり屋ではあったけど、昔から順位づけられるのが大嫌いだった」
以降、コンクールに積極的に参加することはなくなった。練習嫌いで、母に怒られることから逃げてばかりいたが、いつの間にかピアノが生活の一部となっていた。
 その後は御邊も「自由に弾かせる」ことに徹底して、彼女の感性を磨いていく。コンクールに出場させる代わりに、那須の自宅でリサイタルを企画した。この「彩ちゃんコンサート」は彼女が高校に進学するまで続いた。
その後は御邊も「自由に弾かせる」ことに徹底して、彼女の感性を磨いていく。コンクールに出場させる代わりに、那須の自宅でリサイタルを企画した。この「彩ちゃんコンサート」は彼女が高校に進学するまで続いた。
「うーん、でもこの頃はまだ、ピアノを〝やらされている〟感覚はあったかな。確かにピアノは私にとってご飯みたいなものになっていたけど、リサイタルが楽しい思い出だったかというと、リサイタルのためのきつい練習のことばかり思い出してしまう。もちろん、弾いて喜んでもらえるのは嬉しかったから、続いていたんだと思うけど……」
中学時代には、同年代の女の子たちと同じようにアイドルグループの音楽を聴き、つてを頼って実際にアイドルグループへの加入を真剣に考えたことがあった。
しかし、中学を卒業する頃には、将来はピアニストになることを漠然と考えるようになっていた。進学先は御邊のいる東京音大附属高校を希望する。
「私は勉強ができないから、ピアノが弾ける音楽学校しか選択肢がなかった。しかも、一般入試で出題される楽典や国語、数学、英語なんてまるでできないので、ピアノの実技の成績だけで合否が決まる東京音大附属高校ピアノ演奏家コースの推薦試験で受かるしか私に残された道はなかったんです」
ピアノ演奏家コースは最難関で、毎年合格者は数名だ。楽譜通りには弾かないし、作曲家のことも無知だった長富の推薦入試に関し、御邊からは受験した日の夜に「合格すれば奇跡」と告げられていた。長富は「その夜はお通夜のようでした」と振り返る。
翌日、合格者が発表される掲示板には彼女の受験番号だけが書かれていた。彼女の実力があまりに突出していたことによって、他に合格者はいなかったのだ。長富一家はみんなで抱き合い涙した。
「もし不合格だったら、今頃私はピアノを続けていなかったかもしれません」
柳川悠二(ノンフィクションライター)
以下、後編に続きます。近日中に公開予定