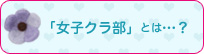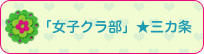ロマンチックなストーリーにときめいたり、物語の悲しい結末に涙したり、愉快なシーンに思わずほくそ笑んだり。そんな映画の名シーンには、さりげなくクラシックの音楽が使われているもの。


暑い夏は映画館に出かけてエネルギーを補給しよう!
ロマンチックなストーリーにときめいたり、物語の悲しい結末に涙したり、愉快なシーンに思わずほくそ笑んだり。そんな映画の名シーンには、さりげなくクラシックの音楽が使われているもの。普段クラシックにはなじみの無いあなたも、きっと心に引っかかるあのシーンのあの音楽。ぜひ音楽を聴いて、映画のすてきなワンシーンを思い返してみてください。きっとその時のわくわくドキドキ、ウルっとする気持ちがよみがえってくるはず。
無伴奏チェロ・ソナタ 第1楽章
(ポンヌフの恋人)
セーヌ川にかかる最古の橋「ポンヌフ」に住むホームレスの青年と、眼病をわずらって家出した少女の恋の物語。映画の冒頭に鳴り響くコダーイのチェロ・ソナタの空気を引き裂くような悲痛な音楽が、物語以上に強烈な印象を残します。劇中では、革命200年の花火を背景に二人の恋人がポンヌフの上で踊り興じるシーンも忘れがたく、ここでは<美しく青きドナウ>の華やかなワルツが奏でられています。
フルートとハープのための協奏曲 第2楽章
(アマデウス)
天才モーツァルト=得体のしれない奇人という図式を決定づけた、ミロシュ・フォアマンの異色伝記(?)映画。不幸にも『アマデウス』 のために、モーツァルトの毒殺者として人々に記憶されることになったサリエリですが、映画の中で、彼がモーツァルトの才能に絶望的に 打ちのめされるというのがこのシーン。モーツァルトの妻コンスタンツェが持ってきた楽譜を広げると、そこには<フルートとハープのた めの協奏曲>の天上的に美しい音楽が流れ出します。サリエリは本当にモーツァルトの才能に嫉妬したのかもしれない、と納得させるような、曇りもなく美しい音楽です。
オペラ《椿姫》 第1幕への前奏曲
(プリティ・ウーマン)
ジュリア・ロバーツの魅力あふれるラブ・コメディ『プリティ・ウーマン』。コールガールと実業家の恋を描くこの映画、劇中にはゴージャスなネックレスをつけドレスアップし、自家用ジェットでオペラ観劇に向かうという夢のようなシーンがありますが、その時の演目が《椿姫》でした。高級娼婦と青年貴族の恋の顛末を描いたオペラの結末は、映画とは違って、娼婦ヴィオレッタの死で終わる悲しいものです。
(マリー・アントワネット)
ポップな映像に音楽、スクリーンをうめ尽くす絢爛豪華なドレスにお菓子、今まで見たこともなかった現代風・時代劇映画 『マリー・アントワネット』には、ソフィア・コッポラ監督のガーリーな感性があふれまくっています。ポップ・ロックな音楽に まじってそこに登場するバロック音楽、ヴィヴァルディの「弦楽のための協奏曲」の踊り出すような明るい音楽は、ヴィヴィッドな映画の色彩観にもマッチしています。
弦楽のためのアダージョ
(アメリ)
女の子映画の金字塔『アメリ』。両親にかまってもらえず、空想癖のある引きこもり少女に成長してしまったアメリも、22歳になってようやく一人暮らしを始めることに。ひょんなことから“ひとを幸せにする喜び”に目覚め、最後には自分の幸せを見出します。映画の中では、寝室のテレビが重要な小道具として登場しますが、<弦楽のためのアダージョ>が重々しい響きで流れる場面でアメリが涙を流しながら見ているのは、ダイアナ妃の葬儀のニュース。次第にナレーションは、アメリ自身の架空の生涯を語り出し…という、この映画を象徴する不思議なシーンです。
《白鳥の湖》より第4幕 情景・終曲
(ブラック・スワン)
バレエ「白鳥の湖」を題材としながらも、バレエ映画というより、もはやサイコスリラーといった趣の『ブラック・スワン』。ナタリー・ポートマンが減量して自らバレリーナ姿に挑んだことでも話題に。全編に《白鳥の湖》の音楽が使用されているのは言うまでもないことですが、ここではバレエのラスト・シーンを飾る音楽をどうぞ。
ピアノ協奏曲 第2番 第2楽章
(逢びき)
1945年制作の名作古典映画『逢びき』。会社員の妻ローラと妻子のある医師アレックは、ある日、駅のホームで出会い、やがて毎週木曜日の逢びきを重ねるようになります。映画全編にわたって流れるラフマニノフのピアノ協奏曲第2番のロマンチックなメロディが、やるせない二人の気持ちに寄り添って流れる、シネマ=クラシック音楽の代表作と言えるでしょう。
(ヒューゴの不思議な発明)
マーティン・スコセッシ監督の映画愛がスクリーンいっぱいに詰め込まれた、ファンタジーと希望にあふれる3D映画。ヒューゴは、パリ・リヨン駅の時計台に隠れ住む孤児の少年。父が遺した機械人形のカラクリを探るうちに、おもちゃ屋の老人メリエスの隠された秘密が明らかになってゆきます。サティのこの美しい音楽は、メリエスの悲しい過去を振り返るシーンで、もの静かに鳴り響きます。
バラード 第1番 ト短調
(戦場のピアニスト)
ナチス・ドイツ軍がポーランドに侵攻する中、廃墟と化したワルシャワの街を生き抜いたユダヤ人ピアニスト、シュピルマン。長い逃亡生活の末、ある日ついに廃屋の中でドイツ人将校に見つかってしまいます。彼を問いただすうち、シュピルマンがピアニストであると知った将校は、彼をピアノの前に座らせ、何か弾くように促します。はじめは恐る恐る、次第に熱を帯びながらシュピルマンが演奏したのが、ショパンのバラード第1番。彼のピアノに心を動かされた将校は、この廃屋にシュピルマンを匿うようになるのです。
ホフマンの舟歌
(ライフ・イズ・ビューティフル)
ナチスの強制収容所を舞台にしながら、笑いと優しさと人生の喜びを明るく描いた稀有な作品。息子ジョズエを怖がらせないようにとグイドがついた嘘が、最後には奇跡をよび起こすこの映画には、「ライフ・イズ・ビューティフル!」と思わずにはいられない感動的なシーンがいくつもあります。ある日、収容所でドイツ人たちのパーティの給仕をすることになったグイドは、蓄音機のホーンを窓に向け、<舟歌>のレコードを流します。その美しい音楽は収容所の冷たい夜の空気をこえて、妻のいる女性監房にまで届いてゆきます。
(セブン・イヤーズ・イン・チベット)
ブラッド・ピット演じる傲慢なオーストリア人登山家ハラーと、少年ダライ・ラマ14世との心の交流を描いた『セブン・イヤーズ・イン・チベット』。ハラーがいよいよチベットを離れなければいけないという時、ダライ・ラマは大事にしていたオルゴールをハラーに託します。オルゴールから流れる<月の光>の清廉な音楽が、ハラーと不仲だった息子との心のしこりも溶かしてゆくラストシーンも印象的です。
オペラ《カヴァレリア・ルスティカーナ》
間奏曲
(ゴッドファーザー PART III)
言わずと知れたゴッド・ファーザー・シリーズの完結編、Part III のフィナーレは、オペラ《カヴァレリア・ルスティカーナ》が上演されるオペラハウスが舞台となります。オペラハウスで繰り広げられるコルレオーネ一族とファミリーをねらう刺客との攻防、その最後に訪れる悲劇…。そして映画の末尾で、再びこのオペラの間奏曲が、マイケル・コルリオーネの人生を包み込むかのように静かに流れます。
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調
(北京ヴァイオリン)
中国の田舎町に生まれた少年チュン。彼を男手ひとつで育てるチュンの父は、母の形見のヴァイオリンを巧みに弾きこなす息子を、一流のヴァイオリニストにすることに人生をかけ、ついに二人で北京へと上京します。大都会で翻弄される父と息子、そしてチュンの隠された秘密が明らかとなり…。チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲を演奏するラストシーンで、二人の愛情がさまざまな思いとともに昇華されてゆきます。
(交響曲 第5番より)
(ベニスに死す)
トマス・マンの小説を題材にしたヴィスコンティ監督の大傑作『ベニスに死す』と、もはや分かちがたく結びついた音楽マーラーのアダージェット。実際、映画の主人公は、原作の作家から作曲家に変更され、マーラーを思わせるような人物造形がされています。この官能的な音楽は、本来マーラーが、後に妻となるアルマにあてて作曲した音による恋文だったといわれています。
(愛と哀しみのボレロ)
指揮者カラヤン、ジャズ・ミュージシャンのグレン・ミラー、バレエ・ダンサーのヌレエフ、シャンソン歌手エディット・ピアフたち4人の音楽家をモデルに、大戦をはさんで2世代の物語を壮大に描く『愛と哀しみのボレロ』。この4つの家族の物語が一つに結び合わされ、パリのトロカデロ広場でボレロの大競演を繰り広げるクライマックスの迫力は圧倒的です。そこで踊るジョルジュ・ドン(ヌレエフ役)の姿が、この映画のすべてを語っているといっても過言ではないでしょう。
楽劇《トリスタンとイゾルデ》より愛の死
(ロミオ+ジュリエット)
レオナルド・ディカプリオとクレア・ディーンズによる、新感覚の『ロミオとジュリエット』。このシェイクスピアのよく知られた物語の源泉となったのが、媚薬の過ちで道ならぬ恋に落ちてしまった「トリスタンとイゾルデ」の悲恋です。映画のラストシーンでは、ワーグナーの《トリスタンとイゾルデ》の最後を飾る<愛の死>の、愛の崇高な思いだけを結晶したようなの美しい音楽が、さりげなく流れています。