

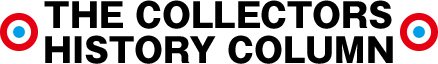
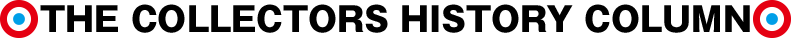
4枚目のアルバム『PICTURESQUE COLLECTORS' LAND』と、その後のツアーの反応を踏まえて、所属レーベルのテイチクと事務所の双方から、「リズム隊をメンバー・チェンジして強化するべき」という話が持ち上がったのが、1990年の秋~冬。協議の結果、チョーキーとしはる、リンゴ田巻がバンドを脱退することになった。
バンドはコロムビアに新設されたレーベル、SEVEN GODSへ移籍することに決定。新メンバーとして発表されたのは、元レッド・カーテン~オリジナル・ラヴのベーシストだった小里誠と、オーディションを経て選ばれた若手ドラマー、阿部耕作だった。

デビュー前から何かと縁があり、新レーベルの同僚でもあったピチカート・ファイヴから小西康陽をプロデューサーとして招き、新作をレコーディングすることに決定。加藤と小西は共に協力して映画『ナック』の再上映を実現するなど趣味の合うところもあったが、いざスタジオに入ってみるとロック感の相違があらわになって行ったという。
そして完成した『COLLECTOR NUMBER.5』は、1991年7月に世に出た。前作に続いてLP2枚組に匹敵するヴォリュームの大作で、まさに加藤と小西の個性がぶつかり合った感じの内容。サウンドの変化に戸惑ったファンも多かったが、今冷静に聴き直すと、大胆な構成の“おねがいホーキング博士”や、故・広川太一郎をフィーチャーした“ゴルフはいかが?”、ポエトリー・リーディング風の語りが新鮮な“二人”など、ここでしか聴けないタイプの奇抜な曲が耳に残る。これまではなかなか手が届かなかったスケールのバラード“あてのない船”や、ラストを飾る大曲“ジェットパイロットの夢”をものに出来ただけでも、バンドにとって大きな一歩となったアルバムと言えるのではないだろうか。
巨額の製作費を投じた『COLLECTOR NUMBER.5』だったが、シングル“SEE-SAW”が反響を呼んだものの、大々的なブレイクには至らなかった。
すでに次作用の曲作りが始まっていたが、ここですぐにアルバムには取り掛からず、新曲1曲+カヴァー曲+旧曲のセルフ・カヴァーという変則的な内容のミニ・アルバム『愛ある世界』を1992年5月に発表。ここに収められた「新曲」の“SUMMER OF LOVE”で、当時のUKロック・シーン、とりわけストーン・ローゼズを筆頭とするマンチェスター勢と足並みを揃えるようなサウンドに初めて取り組んでいる。
それまでのアルバムは「自分たちの好きな60sロック/モッズ&ネオ・モッズ/XTC的なひねくれたブリティッシュ・サウンド」などに根差しており、リアルタイムの音楽シーンとつながることを敢えて避けているようにすら見えた。しかし、ここで時代のグルーヴとリンクすることで、新しいリズム隊の向かうべき道がおのずと開けていくことになる。

サロン・ミュージックのレコードを聴いてギター・サウンドに感心した加藤ひさしは、次作のプロデュースを吉田仁に依頼。まったく背景が異なるように見える二者だが、吉田はニュー・ウェイヴ以前のクラシック・ロックにも造詣が深く、レコーディングのアイディアも豊富に引き出しを持っていた。「ロック・バンドの気持ちがわかる」タイプで、なおかつ最新のサウンドにも対応できた吉田の起用が、いよいよ本格的にバンドを覚醒させる。
加藤の狙い通り、このアルバムで聴ける古市コータローのギターは、ソリッドで芯のある、ヴィンテージ・ロック的説得力に満ちた響きをしている。そうしたサウンドこそ、長年このバンドに欲していたものだった。それと同時に、これまで以上に16ビートを意識して、“Monday”や“5・4・3・2ワンダフル”といったダンサブルな名曲が誕生。この2曲では“SUMMER OF LOVE”以上にリズム隊のうねりとグルーヴ感が威力を発揮していた。
SF的な序曲“月は無慈悲な夜の女王”から曲間無しで“愛ある世界”へつなぐ構成も鮮やか。今年豪華ゲスト・ヴォーカル陣によるオールスター編成で再録音された“愛ある世界”は、加藤が敬愛するザ・フーの匂いを濃厚に感じさせながらも、そのレプリカにはならない現代的な響きと、ひらめきに満ちた曲展開で最初から「名曲」の風格が備わっていた。
そして、何より大きかったのが、今に至るまで彼らの代表曲として語り継がれる名曲“世界を止めて”。早い段階からこれをライヴで披露し、演奏しながらアレンジを微調整してきたことで、レコーディングに臨む頃には完成度がかなり高くなっていたという。逆回転音のさりげない挿入、リズムの輪郭を際立たせるピアノ、眼前で鳴っているような生々しい響きのギター・ソロなど、曲の魅力を引き立てる技がどれも抜群の効果を発揮。「秘密に溢れていく恋」というテーマを普遍的なラヴ・ソングへと昇華した加藤の詞世界もハマり、「踊れるけど泣けるコレクターズ」という新しい扉を開けたのだった。
この時期のコレクターズは、ライヴでも観る度にぐんぐん成長し、グルーヴの逞しさを増しているのが毎回実感できた。当時巷を席巻していたいわゆる「渋谷系」のバンドとは異なるベクトルで、時代の音とクラシック・ロックの肉体美を絶妙なバランスで共存させていた当時のコレクターズは、やはり唯一無二の存在だったと今でも思う。
荒野政寿(CROSSBEAT)