

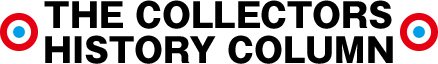
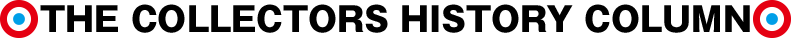
ザ・コレクターズのサード・アルバム『ぼくを苦悩させるさまざまな怪物たち』(1989年)の冒頭を飾る名曲「まぼろしのパレード」について、加藤ひさしは「瞬く間に終息してしまったネオGSムーヴメントに捧げた曲」、レクイエムであるという旨の発言をしていた。加藤はネオGSについて「個性的なバンドが多いシーンだったし、音楽性も高かった」「当時主流だったビート・バンドの一群よりもセンスの良いシーンだと自負していた」とも言っている。実際、紋切り型のロック・バンドに飽き飽きしたリスナーが、ネオGSに飛びついて面白がっている、という側面は確かにあった。
ここで少し、ネオGS出身組のその後の動きについておさらいしておく必要がありそうだ。レッド・カーテン~オリジナル・ラヴのフロントマンとして活動していた田島貴男は、ネオGSと近しい存在だったピチカート・ファイヴに要請されリード・シンガーとして加入、アルバム『Bellissima!』を1988年に発表した。レッド・カーテン時代のサイケ・ポップから早々と脱却してソウルやジャズへの傾倒を強めていた田島の個性がフィットし、このラインナップは1990年まで続く。その後仕切り直してメジャー・デビューしたオリジナル・ラヴと、新たに野宮真貴をシンガーに迎えたピチカート・ファイヴの活躍は、今さら説明するまでもないだろう。
同じくネオGSの人気バンドだったワウ・ワウ・ヒッピーズの3名に、ペイズリー・ブルー、ザ・ハワイズのメンバーが合流してロッテンハッツが生まれたのは1989年。サイケ色が強かったワウ・ワウ・ヒッピーズの音楽性とは対照的に、フォークやカントリーなどルーツ・ミュージック、ソウル、AORなどの影響も取り込んだ語彙豊富なアプローチで注目された彼らは、90年代に入ってからメジャー・デビューも果たした。このバンドは94年に解散、GREAT3とヒックスヴィルに分かれていく。
つまり「ポストネオGS」と言える1988~1989年の流れは、いわゆる「渋谷系」及びそれ以後に向けての準備段階。それぞれのバンドが音楽性を拡げ、装いも新たに、次なる表現へと向かい始めた時期だった。
では、そんな変革の時期に、コレクターズはどう動いていたか? それを如実に伝えるアルバムが、この3枚目だ。CGを用いたジャケットのアートワークに同時代性を意識した跡が窺えるが、他のネオGS出身組が目指したような「変化」のアルバムではなく、映画やSF小説にどっぷり浸かっていた当時の加藤ひさしイズムをより濃く抽出する方向に進んだ作品。まだレコーディングしていなかったストックも「CHEWING GUM」などいくつか入っており、初期の総まとめ的な印象を受ける。ここで遂にアナログ盤の時代が終了、初めてコンパクト・ディスクのみでのリリースになったが、彼らはわざわざLP盤サイズのジャケットを作ってファンにプレゼントするなど、60sマニアとしてのイメージを引き続き打ち出した。
バンドとしての進化を感じさせる部分も多いアルバムだ。最初の2枚を踏まえて“次はどこへ行こう?”と模索し出したことが窺える、幅広い音楽性の楽曲が並ぶ。後の彼らにつながる曲という意味では、レイト60s~アーリー70sのバブルガム・ポップ風味が出てきた「あの娘は電気磁石」(この曲がすかんちに与えた影響は小さくない)の存在が大きいし、ヘヴィなリフ・ロックに挑んだ「スーパー・ソニック・マン」、ライヴで定番曲になっていく「恋の3Dメガネ」など、ミドル・テンポのロック・チューンで試行錯誤をしている点が興味深い。レーベルからはヒット性の高い曲を要求され続けていたようだが、そうした声などどこ吹く風といった感じで、“やってみたかったこと”の具現化に注力しているアルバムとも言える。その最たる曲が、ザ・フーとSF映画をこよなく愛する加藤ひさしが書き上げたミニ・ロック・オペラ「ぼくを苦悩させるさまざまな怪物たちのオペラ」だ。憧れをバネにして取り組んだこの曲を加藤は「まだまだ習作の域」と謙遜していたが、こんなトライをしようと思い立つロック・バンドは彼ら以外に存在しなかった。

3枚目で曲調のヴァリエーションが増えたことも手伝って、4枚目『PICTURESQUE COLLECTORS’ LAND』は必然的に最も多彩なアルバムになった。CDの収録時間に合わせて曲数も増え、全15曲・約60分収録と、LP2枚組に相当するヴォリュームに。それまでになく凝った構成で驚かせる「マーブル・フラワー・ギャング団現わる!」や、前作での実験を踏まえて出来上がったコレクターズ流リフ・ロック の名曲「ぼくのプロペラ」では、歌詞に性的な暗喩が登場。シンフォニックな 「地球の小さなギア」や、洗練されたアレンジの「S・P・Y」を今改めて聴くと、音楽的にはコロムビア移籍後の作風にシフトし始めていたことに気付かされる。
前作の「太陽が昇るまえに」と同じく、悲劇的な内容が歌われる「チョークでしるされた手紙」は、この時期ならではの名曲。こうしたドラマティックな曲が続けて生まれた背景には、ルイ・マル監督の『鬼火』や、ジャン・リュック・ゴダール監督の諸作など、映画からの強い影響があった。アルバムのラストを飾るSFロック「ロケットマン」もそうだが、視覚を刺激する詩的な表現が歌詞に並び、ソングライターとしての成熟を強く印象づけるアルバムだ。
作品だけ聴いていると非常に充実した時期と思えるし、ライヴも精力的に行なっていたが、バンドの内情は穏やかではなかった。リード・トラック的にプッシュされた「ぼくのプロペラ」が話題になるも、セールスは引き続き苦戦。レコーディングではベースを加藤が自分で弾いてしまう場面もあり、音楽性が変化して曲構成が複雑になってきた分、バンドとしての成長は急務だった。
バンド・ブームの追い風が弱まり、もはや所属するシーンもなくなった80年代末~1990年のコレクターズは、文字通り“孤軍奮闘”している状況だった。どうやってバンドを存続させるのか、レーベル契約は続けられるのか、どうしたらブレイクできるのか――デビュー以来最大の壁に直面したこの頃、加藤ひさしの20代は終わった。
荒野政寿(CROSSBEAT)