

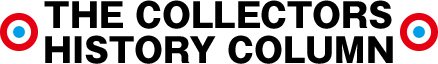
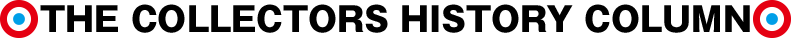
コロムビアへ移籍してから初めてのベスト・アルバム『GOLD TOP』を95年10月にリリースし、メンバー・チェンジ以降の活動に一区切りをつけたコレクターズ。“世界を止めて”のヒット以降、常にブレイク寸前と言われ続けながらセールス面で決定打を出せずにいたバンドは、96年に入るといよいよ抜本的な変化を迫られていた。それは率直に言えば〈一刻も早くヒット曲と売れるアルバムを!〉ということだ。

ここで新作のプロデューサーとして、伊藤銀次の名前が浮上する。時期的には、ちょうど伊藤が手掛けたウルフルズが“ガッツだぜ!!”(95年12月)で劇的ブレイクを果たした直後。早くからコレクターズに注目し、自身のアルバムで“僕は恐竜”をカバー、加藤ひさしや古市コータローと気心が知れていた伊藤は、まさに適任!と誰もが思ったはずだ。
しかし、伊藤銀次は自他共に認めるポップ・ソング・マニアであると同時に、ロック界から歌謡界へと足を踏み入れて切磋琢磨してきた〈ヒット請負人〉でもあった。今回の依頼は明らかに後者のマジックを期待してのもので、そうなるとコレクターズの個性やクセにメスを入れて、固定ファンの外側にいる〈大衆〉にアピールするような作品を生み出さねばならない。ゆえに、いちファンとしてコレクターズの楽曲を愛聴してきた伊藤にとっては、すんなり承諾しにくいオファーだった。
結果的にバンド側の熱意に押され、伊藤銀次の参加が決定。しかしいざ『MIGHTY BLOW』の制作に入ると、予想を遥かに越える大手術が待っていた。リズム・セクションのレコーディングは、それまで経験したことのない徹底したスパルタ式。また、加藤ひさしは歌詞に対するダメ出しの洗礼を受けている。当初は孤独でいることを肯定的に語る内容だった“クルーソー”や、『さらば青春の光』のジミーよろしく黄昏に〈背を向けて〉歩くイメージだった“GLORY DAYS”は、この内容で大衆の共感を得られるのか?という指摘を受け、現在の形へと書きかえられた。
しかし今思えば、この『MIGHTY BLOW』こそが、現在の〈開かれたコレクターズ〉の出発点なのだ。ここで〈大衆にアピールするというのはどういうことなのか?〉という問いを真正面から突きつけられ、発想の転換を余儀なくされた経験を踏まえて、次作で「TOUGH」が生まれ、さらに近年の「たよれる男」「Da!Da!!Da!!!」といった突き抜けた楽曲につながっていったのではないか……そう筆者は受け止めている。前作『Free』よりもシェイプアップしたバンド・サウンドで小気味よくまとめ、ビート・バンドとしての魅力を見つめ直した『MIGHTY BLOW』は、今こそ改めて聴き直されるべき一枚だ。

引き続き伊藤銀次のプロデュースで録音した、TVアニメ『こちら葛飾亀有公園前派出所』のエンディングテーマ“いいことあるさ”を96年11月にリリース。スマッシュヒットとなったこの曲の後、バンドはセルフ・プロデュース(ザ・イエローモンキーを育てた敏腕ディレクター、宗清裕之との共同プロデュース)で、次作に取り掛かり始めた。
“Giulietta”“TOUGH”“GIFT”と3枚の強力な先行シングルが出たことでもわかる通り、97年の『HERE TODAY』では加藤ひさしのソングライティングが乗りに乗っている。バンドのポテンシャルも、ずっと右肩上がりのまま。〈セールス面で結果を出さねば〉という追い込まれた状況が続いてはいたが、本作ではそうしたプレッシャーすら勢いへと転じて、『UFO CLUV』から続いた試行錯誤の集大成とも言うべきアルバムに仕上げている。
以前からあたためていた“嘆きのロミオ”は、ライヴでも見せ場になった一世一代の名曲。決してシングル向きとは言えないが、こうした背徳的なテーマを扱うにしても、安直なバラードではなくダイナミックなロック・チューンとして表現できてしまうのが〈90年代のコレクターズ〉だった。当時ヒット・チャートを占領していたJ-POP勢との大きな違いは、コレクターズがどんなに表現の幅を広げても、一貫して〈ロック・バンド〉でいることにこだわりを持ち続けたことにある。
時事ネタを扱った“TEENAGE FRANKENSTEIN”や“真実はかくせない”がある一方で、とことんハードにロックする古市コータローの魅力を浮き彫りにした“ELEPHANT RIDE”、甘いメロディがグルーヴする“JET HOLIDAY”など、多彩な楽曲を収録。“OVERTURE”で幕を開け、ミレニアム目前の不安感・空虚さを反映した美しい大曲“20世紀が終わっても”で締め括る構成も実に素晴らしい。〈コレクターズの最高傑作は、テイチク時代でも『UFO CLUV』でもなく『HERE TODAY』〉と力説するファンが少なからずいるのも頷ける、完成度の高いアルバムだ。

バンドとスタッフが一丸となり、総力戦で臨んだ『HERE TODAY』だったが、この傑作をもってしても〈本格的な大ブレイク〉という目標を達成することはできなかった。翌98年は、5月にシングル“FIND THE WAY HOME”と、ライヴ音源を選りすぐった編集盤『LIVING FOUR KICKS』を発売。続いて10月にシングル“CASH & MODEL GUN”をリリースしたものの、スタジオ・アルバムは出ないまま年が明けた。
99年4月発表の11thアルバム『BEAT SYMPHONIC』は、迷いの中でスタートした作品だ。〈何か話題作りが必要では?〉という観点から、一時は外部から著名アーティストをプロデューサーとして迎える案すら出たが、それが成就することもなく、結果的に『HERE TODAY』の路線を踏襲したセルフ・プロデュース作となった。
しかし、曲の粒は揃っていた。最大の収穫は、シングルとして先行カットされた“百億のキッスと千億の誓い”だろう。グランジ/オルタナ以降のラウドなギター・サウンドを取り入れ、コレクターズ流パワー・バラードの新しい形を提示したこの曲は、ライヴでも定番曲として長く愛されることになる。
いかにもロック・バンド然としていた『HERE TODAY』に比べると、“Brand☆New☆Heaven”、 “センチメンタル・スイート・ハートエイク”、 “Stay Cool! Stay Hip! Stay Young!”など、ポップ側に寄った曲が多く、前作とは兄弟のような関係のアルバム、とも言える。一方、それらとは対照的な激情のラヴ・ソング“Butterfly Kiss”、実質的に加藤ひさしのソロ曲と言っていい“Quiet Happy…”など、成熟を示す楽曲が収められているのも本作の魅力。30代後半に突入したメンバーのコクがある名演を収めた、聴き応えのあるアルバムだ。
今回ご紹介した3枚のアルバムは、J-POP全盛の90年代後半にコレクターズが〈メジャー・レーベルに所属するロック・バンド〉としてどう闘ってきたのかを示す、バンド史上でも重要な作品。ちょうど今週発売されたばかりの新しいボックス・セット『MUCH TOO ROMANTIC!』にも全て収められているので、この機会に〈30代のコレクターズ〉の凄味を改めて味わって欲しい。
荒野政寿(CROSSBEAT)