

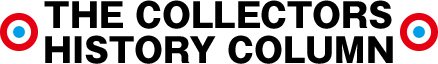
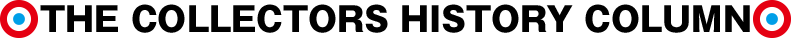

1999年、『BEAT SYMPHONIC』を最後に、一旦コロムビアとの契約が終了。バンドは「今後インディ・レーベルからリリースしていく可能性」も視野に入れて、早速スタジオに入る。これが変名プロジェクト、THE MAJESTIC FOURだ。オリジナル曲は全て英語詞で、バンドの原点であるサイケ・ポップに立ち戻って、やりたい放題やった時期。それまでメジャー・レーベル所属のロック・バンドとしてヒット曲を求められ続け、J-POP時代の真っ只中で孤軍奮闘してきたバンドにとって、これがいいガス抜きになった。
翌2000年1月に、THE MAJESTIC FOUR名義の6曲入りミニ・アルバム『MAGIC FUN FAIR』をリリース。正体を伏せすぎたせいか、レコード店では洋楽の棚に商品が置かれるという珍事も起きた。スーパー・ファーリー・アニマルズにインスパイアされた曲〈Dolly〉や、知る人ぞ知るオレンジの名曲〈Judy Over The Rainbow〉のカバーを含むこの作品は、「マニアックな洋楽ファンをも唸らせるコレクターズ」の、一つの頂点と言っていい作品。XTCの変名ユニット、デュークス・オブ・ストラトスフィアがそうであったように、別プロジェクトでの活動が、やがてバンド本隊のその後の作品にも影響を及ぼすことになる。

『MAGIC FUN FAIR』のセールスはそこそこの結果に終わったが、古巣のコロムビアからワンショット扱いでアルバムを出す話がまとまった。ここでコレクターズから『Free』以降距離を置いていた吉田仁が、プロデューサーとして久々に復帰、最新作に至るまでバンドを支え続けることになる。吉田がもう一度コレクターズを手掛けようと思った決め手は、バンドが自力で作った『MAGIC FUN FAIR』を聴いて、「まだこんなに良い曲が書けるのか!」と感心したから。それを踏まえて、レコーディングの予算を可能な限り節約しながら、楽曲の魅力を丁寧に引き出したアルバムが、次作『SUPERSONIC SUNRISE』(2001年2月発売)だった。
飛び切りポップな先行シングル〈恋のしわざ〉や、コレクターズ流16ビートを発展させた佳曲〈LUNA〉、そして窮地にありながらも前進しようという決意を表明した〈MILLION CROSSROADS ROCK〉などが並ぶアルバム前半に対し、後半は〈PUPPET MASTER〉〈遠距離通話サービス〉〈沈みゆく船〉といったブリティッシュ・ロックの薫り高い楽曲が揃い、アナログ盤のA面・B面を思わせる構成に。今では説明なしだと何の曲だかわからなそうな〈ジェリーに相談〉(当時日本でも放映されて話題を呼んだTV番組、ジェリー・スプリンガー・ショウをヒントにした曲)のように、遊び心や皮肉が歌詞に戻ってきた点も、本作の特徴。改めて「コレクターズの個性とは?」と自身に問い直したような、キャリアの折り返し地点となる重要なアルバムだ。

2001年の11月に先行シングル「PUNK OF HEARTS」をリリース後、アルバムの完成までしばらく間が空く。2002年に入ると、阿部耕作が忌野清志郎らと結成したLOVE JETSの活動を本格化。当時経営が悪化していた事務所もLOVE JETSでの活動をプッシュし、それと並行してコレクターズの次作のレコーディングを進めていくことに決まった。
ここでコレクターズ史上初めて、レコーディングにPro-Toolsが導入される。編集を飛躍的に容易にしたこのソフトがあってこその『GLITTER TUNE』(2002年11月発売)だった。ドラマー不在のまま、バンドはドラム・マシーンを使って一旦リズム・トラックを録音、後日阿部のドラムに差し替えていくという方法が取られている。吉田仁が編集に苦心した甲斐あって、リズムに違和感を感じさせない仕上がりになっている点はさすがだ。
幸い、曲の粒はまたしても揃っていた。古市コータローのシャープなギターが先導する〈ANY DREAM WILL DO〉。加藤ひさし流パワー・ポップを極めた名曲〈POWER OF LOVE〉。マージービート風のチャーミングな〈CRAZY LOVE FOR YOU〉がある一方で、やがてライヴ終盤の見せ場となるドラマティックなロック・バラード〈虚っぽの世界〉もここに収められている。
時代の変化もあって、打ち込みを用いたR&B/ポップ・ソングが全世界的な規模で主流になり始めたこの時期は、ロック・バンドがセールス的に厳しい状況に追い込まれていた。コレクターズも例外ではなかったが、そういう時期にあっても、たとえば〈WINTER ROSE〉でポーティスヘッドのサウンド作りを参考にするなど、それまでとは異なる音楽的な実験をスタジオ内で続けていた点に注目して欲しい。一見ひとつの「スタイル」を堅持してきたように見えるコレクターズだが、実際はトライ&エラーを何度も重ねながら、アルバムごとに変化し続けてきたバンドなのだ。単に外見ばかりでなく、そうやって変わり続けるという精神にこそ、彼らのモッズ観は顕れているように思う。
荒野政寿(CROSSBEAT)