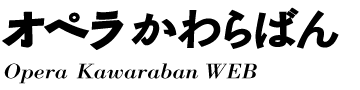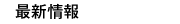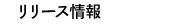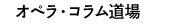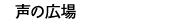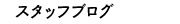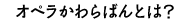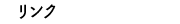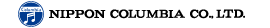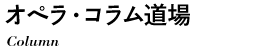連載内容
「レコード芸術」などで活躍する気鋭の評論家、広瀬大介さんが、オペラに登場する日の当たりにくい脇役になりきり、そのオペラの魅力と鑑賞のツボを押さえた作品解説、対象映像の演出について語る、世にも不思議ななりきり一人称ガイド。
これぞ自己言及のパラドックス!ねじれの向こうに真実がみえる!
プロフィール

広瀬大介
1973年生。一橋大学大学院言語社会研究科・博士後期課程修了。博士(学術)。著書に『リヒャルト・シュトラウス:自画像としてのオペラ』(アルテスパブリッシング、2009年)、『レコード芸術』誌寄稿のほか、NHKラジオ出演、CDライナーノーツ、オペラDVD対訳、演奏会曲目解説などへの寄稿多数。
Twitter ID: @dhirose
最近、無味乾燥な歴史書の代表格『徳川実記』に現代語訳が登場しはじめ、うれしさを噛みしめつつも、昔苦労して読んだのは何だったのか、と一抹の寂しさも感じているところ。好きな食べ物は相変わらず甘いチョコと甘い梅酒。

第5回 《ラ・ボエーム》
若者に向けてショナールが語る 「人生の成功には何が必要か」

《ラ・ボエーム》とは
1830年代、ナポレオンの「夢」が過ぎ去ったフランス・パリで、芸術によって身を立てようとする若き「卵」たちが暮らしていた。アンリ・ミュルジェールなる作家の手による『ボヘミアンの生活情景』(1851年)の中に描かれたひたむきな若者の姿に、作曲家ジャコモ・プッチーニも、自らの若き日の姿を重ね合わせたに違いない。同じ題材をもとにレオンカヴァッロも作品をものしたが、もっぱらプッチーニの作品ばかりが上演されているのは周知の通り。1896年(明治29年)にトリノで行われた初演ではあまり受けがよくなかったものの、その後イタリア各地での上演を重ねるごとに、爆発的に受け容れられていった。
1871年のパリ。フランスは前年の普仏戦争第二帝政・ナポレオン三世が支配するフランスと、鉄血宰相ビスマルク率いるプロイセン王国が、スペインの王位継承をきっかけとして始めた戦争。ヴェルサイユ宮殿でプロイセン王は新しいドイツ皇帝として即位し、以後フランスはドイツの後塵を拝することになり、賠償としてアルザス・ロレーヌ地方を割譲した。団塊ジュニア世代よりも上なら、この時の情景を描いたアルフォンス・ドーデの小説『最後の授業』が、教科書に載っていたのをご記憶のはず(現在は採用されていない)。なお、話の救いのなさという点では、同じドーデの『村の学校』(実話)のほうが、より生々しい。でドイツ・プロイセンに敗れ、社会的にも沈滞の時を迎えていた。若者は将来に希望を見出せず、先行き不安な中で鬱々とした日々を過ごしている。そんな若者たちを励ますべく、一人の男に声がかかった。その男、ショナール。いまやパリで知らぬものとてない、大作曲家の一人である。若き日の、オンボロに身を包んだ貧乏学生の姿はどこへやら。還暦を過ぎたショナール氏は、仕立ての良いフロックコートとシルクのシャポーに身を包み、パリ・ソルボンヌ大学の講堂に登壇した。会場は、著名な作曲家の勇姿を一目見ようと駆けつけた学生たちで立錐の余地もない。著名な文化人にして、社会のご意見番としても一目置かれるショナール氏、果たして、どんな毒舌で若者を鼓舞するのか。学生たちは固唾を呑んで第一声を待つ。
 貧乏学生時代のショナール先生を収めた大変貴重なショット
貧乏学生時代のショナール先生を収めた大変貴重なショット
ショナール:
おはよう、学生諸君! あー、ずいぶんいっぱい小僧どもがいるもんだと思ったが、どいつもこいつも浮かない顔ばかりだな。今のご時世、浮かれた顔した奴ほどお里がしれるってもんだ。
しかしお前らも、俺なんかの話をそんなに聞きたいかね。老人の繰り言に付き合ってるヒマがあるなら、帰ってすこし勉強しろって言いたいね。まあ、俺もそうやって毒づきながら、しっかり講演を引き受けてここに立っているんだから、人のことは言えた義理じゃない。もちろん謝礼もキッチリいただくしな。(会場笑い)
「つかみはOK」のショナール氏。やけに講演会慣れしているようだ。
で、今日のお題は……なんだったっけ?「人生の成功には何が必要か」。なんじゃこりゃ。おいおい主催者さん、こんなテーマ、本当に俺にしゃべらせていいのか? キャスティング間違ってないか?(会場笑い)
こんなテーマに、俺ほど不釣合いな人間もいないだろうに。政治家や実業家ならいざ知らず。俺はしがない、ただの作曲家だぞ。「成功」なんて言ってもたかが知れている。たまたま俺の作りだした旋律が多くの人間の耳に触れ、少しばかり気に入ってもらえたに過ぎない。まあ俺自身、持てる限りの才能と努力はつぎ込んだつもりだがな。 もっとも、多少なりとも世間に名の知られる存在になったのは、ひとえに俺を引き立ててくれた恩人のお陰であり、また若き日に出会った友達からもらった友情のおかげでもある。こう見えても人から受けた恩は、きちんと感じているんだぞ。 そうだな、今日はその辺のことを話そうか。ちょっと長くなるけどな。
おもむろに、演壇に置かれた水に口をつける。この絶妙な間で、観客は襟を正し、氏に改めて視線を集中させる。講演テクニックの妙ここにあり。ショナール氏、やはり講演会慣れしているようだ。
 ショナール先生のお仲間。食事代わりに酒を飲み、談論風発の日々
ショナール先生のお仲間。食事代わりに酒を飲み、談論風発の日々
お前らもそうだろうが、俺の青春時代はまさに「赤貧洗うがごとし」。花の都パリに住みたい一心で故郷を離れ、都会へ出てきたはいいものの、暮らしの当てがあるわけじゃない。一人で部屋を借りるなんて甲斐性があるわけもなく、同じ境遇の芸術家たちと4人で一部屋を借り、共同生活を始めたんだ。
芸術家同士の共同生活。お前らには想像つくか? 芸術家っていう生き物は「わがまま」と相場は決まっている。普通だったらアクの強い人間同士、衝突してすぐにオジャンになるものだろう。だけど、金がないというのは不思議なもので、そこに妙な連帯感が生まれるんだな。利害関係に惑わされない、純粋な心と心の結びつきが生まれるっつうことかもしれない。4人とも、微妙に職業が重なっていなかったのも、なんとか共同生活がうまくいった理由かもしれん。俺は音楽を生業としていて、あとの3人は、それぞれ詩人であり、画家であり、哲学家だった。
 コッリーネ。無口でモテないようだが、オペラでは意外に存在感あり
コッリーネ。無口でモテないようだが、オペラでは意外に存在感あり
 画家マルチェッロ。当時は強烈な彼女とお付き合いしていた
画家マルチェッロ。当時は強烈な彼女とお付き合いしていた
4人は仲がよいながらも、何となく二人ずつの組になって行動することが多かった。俺がいつもつるんでいたのは、哲学家のコッリーネ。大男で、無口で、常に眉間にしわを寄せているような奴だが、あいつがふとした時に漏らす一言は、実に人生の真理を突いていた。俺は、ごらんの通り、ふわふわと軽佻浮薄に生きていくタイプだけど、あいつとは妙に馬が合った。理由? そんなこと聞くなよ。今と違って、あの時は二人とも女に全然もてなかったんだ!(会場大爆笑)
そこへ行くと、画家と詩人の二人は、女にもててね。端で見ていてうらやましかった。画家のマルチェッロはとにかく美人好き。女をモデルに絵を描いては、そのモデルを口説いてしまうような奴だった。絵を描くのと口説くのと、どっちが目的なのか、ちっともわかりゃしない。さらに詩人のロドルフォは、いったん恋に墜ちてしまうと、周りが全く見えなくなってしまうタイプ。この二人は、女の母性本能を刺激する何かがあったんだろうな。「この人、わたしが助けなきゃ」って女に思わせるような危うさがね。
4人での生活は、実に楽しかった。楽しかったのだけど、そんな関係に変化が起きたきっかけが、ある日ロドルフォが連れてきた女だった。同じアパートに住んでいるお針子で、俺もすれ違って挨拶くらいはしたことはあったかな。正直それほど強い個性を持った女ではなかった。労咳病み結核のこと。この病気については、第3回《椿姫》でも散々取り上げ済み。ミュルジェールの原作には、実は戯曲版も存在したが、これはあまりに《椿姫》にストーリーが酷似していたため、オペラの台本としてそのまま流用することができなかった。で、いつも青白い顔をして、笑った顔は透き通るようだった。マルチェッロがいつも連れて歩いている女の派手さに比べれば、あまりに慎ましやか。ルチアという名前のその女に、ロドルフォはぞっこん入れあげてしまったんだ。
 彼女の名はミミ
彼女の名はミミ
彼女のことは、みんななぜかミミと呼んでいた。理由は知らん。ロドルフォは、どこに行くにもこのミミをつれて行かねば気が済まない。ミミがほかの男としゃべるだけで、嫉妬の炎を燃やす。本心では、コッリーネや俺としゃべるのでさえ、やめてほしいと思っていたかもしれないな。不器用で、一つのことに夢中になると周りが見えなくなるような男が、女に惚れ抜いてしまったんだ。そこに座ってる冴えないお前も、実はそういうタイプなんじゃないか?(会場どよめき)
ふふふ、どうやら図星だったか。まあ、それにしても、ロドルフォの猪突猛進っぷりは常軌を逸していた。惚れ抜くあまり、寒い冬、部屋の外で俺たち三人が気を遣って凍えながら待っているのに、なかなか中に入れてくれないこともあったな。ドア越しに聞こえてくるロドルフォの絶叫ハイCロドルフォのアリア「冷たき手を」で歌われる三点C(いわゆるハイC)は、本来の指定ではなく、「歌える人は歌っていいよ」という、ヴァリエーションの扱いに過ぎない。このハイCに不安を持つばっかりに、わざわざこのアリア全体を半音低くし、無理矢理歌う歌手も近年では多い。歌えないときは、本来の楽譜通り、より低い音で歌ってくれていいんですよ。、ありゃ、いまだに忘れられんよ。
もちろん忠告もした。おまえの本業は詩を書くことなんだ、ちゃんと仕事と恋の線引きはしろ、ってね。でも、女に愛を捧げてこそ霊感が生まれる、とか何とか言って、まともに働こうとしない。奴はひたすらミミとの愛に生きたんだ。その結果どうなったか。愛だけでは飯は食えない。愛だけでは寒い部屋で暖をとることはできない。当たり前だよな。でも、お前らも気をつけろよ、若き日の愛っていうのは、そんなことすら忘れさせる麻薬なんだ。そう、ロドルフォはミミの労咳を悪化させてしまったんだ。
俺はね、もう、黙ってみてられなかった。このまま放っておいたら、ミミは死んでしまうって思ったからな。それでロドルフォを説きに説いて、いったん別れさせこのへんは、ショナールの「創作」が加わっている。原作では、以前も付き合ったことのあった子爵の息子と「よりをもどす」形で、ミミが自主的に転がり込んだというのが、実際の顛末。、知り合いの金持ちの子爵に話をつけて、ミミをその息子に「預かって」もらうことにしたんだ。まあ、「預かる」とは言うものの、実際には「お妾さん」だな。でも、死んじまうよりはマシだと思ったんだ。
でもその甲斐なく、ミミの病勢はいよいよ募り、明日をも知れぬ命となってしまった。 あの日、ミミは自分の死期を悟っていたんだろう。彼女はなんと子爵の邸宅を抜け出し、俺たちのアパートへ戻ってきたんだ。
 ミミの最期。悲しくも美しい名場面である
ミミの最期。悲しくも美しい名場面である
やがて消え入るともしびのような、やつれ果てたミミが現れたとき、ロドルフォは、それはうろたえた。そんなに病気が進行しているだなんて、奴は思ってもいなかったからな。俺はといえば、子爵になんと言い訳をすればいいんだ、って、その場で考え込んでしまった。でも、コッリーネに連れ出されてね。最後のひとときくらい、二人きりにしてやれ、と。こういうときに、コッリーネはとてもよく気が回るんだ。奴が外套を売って金を作ろうという時に歌ってた嬰ハ短調幕切れにミミが事切れた後、観客の涙を誘う場面で演奏される音楽の一部は、第4幕でコッリーネが歌う短いアリア『さらば外套』の一節から採られている。そしてこの幕切れも、アリアと同じ嬰ハ短調。もちろん偶然の一致などではないことは、このコラムの読者の皆様ならもうお分かりのはず。『さらば外套』は、『さらばミミ』でもあるのだ。には、真実が宿っていた 。
ミミの最期、今でもはっきり覚えてるよ。まるで眠るようだった。皆が疲れ果て、意気消沈し、ミミからつかのま目を離していたんだ。その瞬間を見届けたのは、どういう巡り合わせか、俺だけだった。そばにいたマルチェッロには伝えたけど、ロドルフォに伝える勇気だけがどうしても出なくてな。あれは、今考えても悔やまれる。後々、ロドルフォには本気で責められた。どうしてすぐにミミの事切れた瞬間を教えてくれなかったんだ、って。ほんの短い時間の巡り合わせとはいえ、ミミを一人のままで逝かせてしまったんだから、奴が怒るのは無理もない。
もう、何度この場面を物語ってきたことだろう。なのに、いまでも話がこの場面にさしかかると、決まって胸をかきむしられるような思いに満たされる。熟練の講演者、老ショナール。つかのま黙し、目を閉じる。固唾を呑む学生たち。
失礼。話を続けよう。ミミの死をきっかけとして、我々の友情にも転機が訪れた。面と向かってはっきりとは言わないものの、ロドルフォが俺を見るまなざしは明らかに冷たくなった。俺が持ち帰るパンやワインには手もつけない。奴は、やがて抜け殻のようになって、パリを去り、故郷へと戻っていったんだ。まあ、冷たい言い方かもしれないが、あまりに繊細な彼にとって、詩人としてしたたかに暮らしていくことは、やはり荷が重かったんだろうな。自分のわがままから、愛する女性を死へと追いやったことも、俺たちの想像以上に、奴の心の重荷となったのかもしれない。
俺はね、すべてロドルフォのためによかれと思い、奴の足りないところ、苦手なところを補うように、協力してやったつもりだった。でも、あのとき俺は若かった。今思えばそれも、ロドルフォにとっては「小さな親切、大きなお世話」だったんだろう。若さゆえに思慮を欠く。お前らも良く覚えておけよ。場合によっては物事を進める原動力にもなるが、あまりに残酷な結果を招くこともあるんだ。今になって気づいても、それは後の祭りだけどな。
あれから40年が過ぎた。早いもんだ。その後、田舎に引っ込んだロドルフォからは手紙一通すら来ない。マルチェッロは老いてなお盛ん、女に不自由はしていないようで、居酒屋なんかの壁に絵を描く絵師として働いている。コッリーネはその後、大学に職を得て、学生に哲学のなんたるかを教えている。時々サシで飲んで、昔を懐かしむこともあるな。
お前らからみれば、俺は十分人生の「成功者」だろう。確かに俺は、世間をうまく泳いでいくという才能だけは、ロドルフォより持ち合わせていたかもしれない。でも、今にして思う。芸術家として見れば、それがどれだけのものか。俺の音楽は本当に人々の心を惹きつけているのだろうか。たとえ俺の音楽が、いまお前らの心を惹きつけたとしても、それが100年後、200年後も、人の心を掴んで離さない、永遠の真実を語る芸術となっているだろうか? ロドルフォが苦しみの中で流した一粒の涙のほうが、人の記憶に残ることもあるのではないか?
お前らには、若さというものは、それだけで人を傷つける可能性があるということを、是非知ってほしい。だが、人を傷つけ、傷つけられることでしか得られないものも、世の中にはあるのだということも知ってほしい。その上で、若さに任せて突っ走り、ぶつかりあい、若さならではの感情の高まりを経験してほしい。まあ、俺みたいな愉しい青春は、そうそう送れるものじゃないだろうけどな。
傷つけ合いか。そういえばいま、フランスはドイツにコテンパンに痛めつけられて、息も絶え絶えだな。ドイツ野郎はたしかにいけ好かないが、あいつらを恨むのは筋違いだと、俺は思う。立場が逆なら、フランスだって同じことをドイツにしたはずだ。そう、人を傷つけ、人に傷つけられながら、よりよい、住みやすい明日を作るのが、若いお前らの仕事じゃないのか。それこそが、『人生の成功に必要』なことなんじゃないか。まあ、俺がお前らに教えてやれるのはこのくらいだ。後は、自分たちの頭で一所懸命考えろ。自信を持て。そして、自分の力で解決しろ。きっといいアイディアも浮かんでくるさ。人生に迷ったら、いつでも俺の所に相談に来い。女ならなお大歓迎だ。ただし、一つ言っておく北方謙三『試みの地平線・伝説復活編』講談社文庫、2006年より。。俺にあまり惚れないでくれ。
会場は総立ち、拍手喝采。ダンディ&ピカレスク、ショナール先生の真骨頂である。
司会者:そろそろ時間となりました。ショナール先生、楽しく、ためになるお話をありがとうございました。ではこれから質疑応答に入りたいと思います。
第5回・了
このオペラが観たくなったら…

プッチーニ 《ラ・ボエーム》
マドリッド王立劇場 2006
名盤の多いプッチーニの代表作に新たな注目盤が登場。ミミ役には、今や飛ぶ鳥を落とす勢いの名リリック・ソプラノ、インヴァ・ムーラを起用。ドミンゴを驚倒させたと言われるその力強さとテクニックを駆使しながら、可憐なだけでない、新しいミミ像を打ち立てます。マドリッド王立劇場の音楽監督、ロペス=コボスの老練な指揮のもと、マチャードを始めとした実力派キャストも充実した歌唱を披露。また、かの名歌手マリオの子息、ジャンカルロ・デル・モナコ演出による「まるで映画の一場面のような」と評された、パリの日常生活を生き生きと活写した舞台は注目です。
■キャスト&スタッフ
ミミ:インヴァ・ムーラ
ムゼッタ:ラウラ・ジョルダーノ
ロドルフォ:アキレス・マチャード
マルチェッロ:ファビオ・マリア・カピタヌッチ
ショナール:ダビド・メネンデス
コッリーネ :フェリペ・ボウ
パルピニョール:ゴンサロ・フェルナンデス・デ・テラン
ベノア:フアン・トマス・マルティネス
アルチンドーロ:アルフレード・マリオッティ
演出:ジャンカルロ・デル・モナコ
指揮:ヘスス・ロペス・コボス
マドリッド王立劇場管弦楽団&合唱団(マドリッド交響楽団&合唱団)
■収録
2006年3月20、23、25日 マドリッド王立劇場(スペイン)
■SPEC
- [収録時間] 142分(本編117分・特典映像25分)
- [字幕] 日本語・イタリア語
- [映像] 16:9 カラー
- [音声] リニアPCMステレオ/Dolby Digital 5.0/DTS 5.0
- [ディスク仕様] 片面2層
- DVD●TDBA-5020 ¥6,090円(税込)