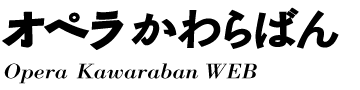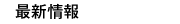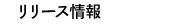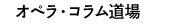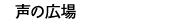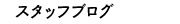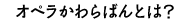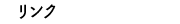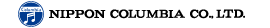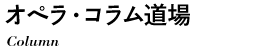連載内容
『絵はがきの時代』(青土社)の著者、細馬宏通さんのオペラ絵はがき連載。
細馬さんの所有するオペラ絵はがきコレクションをもとに、絵はがきの時代=図像交換の時代であり、さらにオペラ絵はがきがオペラをアイコンとして交換するメディアであったことを明らかにします。
初演当時の絵はがきから透かし見える時代精神!
プロフィール
 写真:渋谷博
写真:渋谷博
細馬宏通
1960年西宮市生まれ。滋賀県立大学人間文化学部教授。専門は会話とジェスチャーの分析、 19世紀以降の視聴覚メディア研究。著書に『絵はがきの時代』『浅草十二階』(いずれも青土社)など。バンド「かえる目」で作詞・作曲とボーカルを担当。
好きな音楽:中学生時代はブーレーズ指揮のドビュッシーとラベル、高校時代は荒井由実と矢野顕子、いまは物音から鼻歌まで。
好きな食べ物:ご飯と干物。

第3回 オペラは手紙を歌いうるか?(1)
- 宛先人の読む手紙 -

 白鳥と憩うヴェルディ。ヴェルディの譜面を出版し続けたリコルディ社がヴェルディの死後に発行したもの
白鳥と憩うヴェルディ。ヴェルディの譜面を出版し続けたリコルディ社がヴェルディの死後に発行したもの
オペラ初学者なりにいくつかのオペラを観ていて、むくむくとある疑問が頭をもたげてきた。それは「オペラでは、手紙を歌うことはできないのではないか?」という問いである。
馬鹿なことを言うな、《フィガロの結婚》の<手紙の二重奏>や《ホフマン物語》の冒頭をひくまでもなく、オペラに手紙の歌はつきものではないか、という声がきこえてきそうだ。確かに、手紙を歌うオペラはいくつもあるにはある。しかし、どうもその表現には一筋縄ではいかないひっかかりが感じられる。オペラに現れる手紙文には、他の部分にはない、奇妙な構造があるような気がしてならないのである。
この感触は、郵便好きのわたしの思い過ごしなのか、それともそこには確かな規則が実際にあるのか。以下、オペラの手紙場面と歌声の問題について、思うところを書いてみたい。
***
こんにち、わたしたちが手紙文を読む場面と言われて真っ先に思いうかべるのは、サスペンスドラマの手紙場面だろう。手紙をもらった主人公がまず自分の声で読み上げる。「花子さま、あなたがこの手紙を読む頃には、もうわたしはここにいないでしょう。わたしはあなたにあの日の秘密を打ち明けなければなりません…」そして、その声は、途中で手紙を書いた本人の声へと入れ替わるのがお約束だ。
もちろん、こんなことは日常生活では起こらない。差出人や宛先人自らが手紙を読み上げるというのは、とんでもなく恥ずかしい行為である。そもそも手紙というのは、声にできないこと、相手に直接声で伝えることのできないことを、声なき文字によって書くものである。そして、手紙を受け取る方にとっても、そこに何の秘密がこめられているか予想もつかない文面を、うかうかと人前で読むのははばかられる。
だからこそ、手紙には、秘密を守るための封がしているのだし、それは注意深く差出人から宛先人に渡される。人前で手紙の内容を声にするようなうかつな行為は、そもそも手紙にそぐわない。当の相手がそこにいる場合ですら、声で言うのははばかられる。そこがたとえオペラの舞台であっても。《椿姫》の第2幕を思い出してみよう。ヴィオレッタがアルフレードに別れの手紙をしたためて封をし終わったところに、当のアルフレードがやってくる。
アルフレード 「何をしてるの?」
ヴィオレッタ 「(手紙を隠しながら)何も。」
アルフレード 「手紙?」
ヴィオレッタ 「(狼狽して)ええ…いいえ…」
アルフレード 「ひどくうろたえてる!…誰に書いたの?」
ヴィオレッタ 「あなたに…」
アルフレード 「よこしなさい、その手紙を。」
ヴィオレッタ 「だめよ、今は…」
ここで、いまどきのやりとりのごとく「あ、さっきメールでも出したんだけど、読んでないんだったら今言うね」などと手紙を声にするのは愚の骨頂というものだ。たとえ宛先人が差出人の目の前に居ようとも、手紙はいま目の前で読まれてはならない。目の前で声にすることのできないことを書くのが手紙なのだから。ヴィオレッタは、アルフレードに面と向かって別れを告げることができないからこそ手紙を書いたのであり、当の相手に「よこしなさい」と言われても渡すわけにはいかない。
手紙をしたためる者は、手紙を声にすることはできない。では、手紙を受け取る側はどうか。もはや本人がいなくなったあと、宛先人の目の前に、開かれた手紙の文面がある。このときこそ、オペラの登場人物は、サスペンスドラマのごとく、観客への解説も兼ねて朗々とその内容を歌い上げればいいのではないか。いや、事はそう単純ではない。ヴィオレッタが去ったのち、別れの手紙をアルフレードが開封する場面を見てみよう。アルフレードはヴィオレッタからの手紙を読み始める。しかし、それは長くは続かない。
アルフレード 「アルフレード、この手紙があなたに届くときには…ああ!」
「ああ!」は、手紙文ではなく、手紙を読んだアルフレード自身の叫び声。手紙の肝心な部分は、アルフレードの絶叫によって中断されてしまっている。この点一つを見ても、手紙が、容易に声にされないものであることがききとれる。
さらによくきくと、この場面で、アルフレードが手紙文を読み上げる部分と「ああ!…」以降の部分には明確に区別が付けられている。手紙文の部分にはメロディらしいメロディがついていないのである。
イタリア語では、歌詞はこうなっている。
「Alfredo, al giungervi di questo foglio ... ah!」
「foglio(手紙)」ということばが最後にあるのだけれど、その直前までは、メロディのない、単一の音程で手紙の内容が歌われている。その背後で、弦楽器のトレモロが、メロディの現れる瞬間をいまかいまかと待ち構えるように緊張している。そして、末尾の「手紙 foglio」ということばだけが高い音程で歌われかと思うと、「ああ!」でアルフレードは一気に発声法を変えてフォルテッシモをうたう。そこまで弦だけだったオーケストラも、絶叫を合図に管を加えていっせいにクライマックスを奏でる。つまり、声にもオーケストレーションにも、手紙文と独白とでは明らかに違ったスコアがほどこされているのである。
手紙の読み上げ部分がいかにメロディに乏しかったかは、その後と比較すれば一聴瞭然だ。「ああ!」と振り向いてから、そこに父親がいることに気づいたアルフレードは、感極まって「お父さん Padre mio!」と声をあげる。この短い叫びの中には、それまでとは打って変わって豊かなメロディの高低が含まれている。そして、父ジェルモンは、アルフレードの叫びに答えるかのように、<プロヴァンスの海と陸>のアリアを朗々と歌い始める。
このアリアは、二人を引き離した父親が、息子を無事ヴィオレッタから引き離し、それまでの苦しみから解放されたことを神に感謝するという、現代の常識からすれば身勝手で狡猾にさえ聞こえる部分である。しかし、手紙の扱いに注目するならば、この場面は出色のドラマ性を持っているがわかる。手紙がけしてメロディにはできないこと、にもかかわらず、それは人の心を激しく動かすこと、その心の動きをあえて声にしようとすれば、それは、もはや手紙の文章から離れた叫びにしかならないことが、アルフレードの歌の中に素直に表現されている。しかも、手紙のもたらしたアルフレードの激しい感情の高まりは、続く父親のアリアへとぶつけられて、父親の包容力の大きさを感じさせる。音楽は、いわばメロディのない手紙文を跳ね板にして、聞き手の情動を一気に高め、<プロヴァンスの海と陸>の雄大なメロディへと誘うのである。(ゼッフィレッリ演出の《椿姫》でレナート・ブルソンのうたうアリアをきけば、この歌のドラマ性がはっきりわかるだろう)。
手紙は声をきらう。差出人は、直接声にして言えないことを手紙にしたため、宛先人はそれを人前では声にせずに秘して読む。この手紙の性質を反映するかのように、《椿姫》の第2幕では、手紙はオペラ的な声=メロディを奪われている。これは単なる偶然なのだろうか。《椿姫》のもうひとつの手紙場面、第 3幕第4景で考えてみよう。
ヴィオレッタは、アルフレードと引き離され、いまや病の床についている。彼女は胸から一通の手紙を取り出して読み上げる。それは二人を引き離したジェルモンからの詫び状である。「あなたは約束を守られた…(中略)あなたの犠牲をわたしはアルフレードに打ち明けました。わたしはあなたにお許しを求めに戻ります(後略)。」憂いを帯びたヴァイオリンのソロを背景に手紙の全文を読み上げたあと、ヴィオレッタはひとこと「遅いわ!」と絶叫する。途端にオーケストラが不穏な和音を鳴らす。
この長い手紙の内容に、メロディは全く伴っていない。直後に続く「待てども待てども attendo, attendo」という独白のもつ抑揚、それに続く<さようなら過ぎし日々の>のアリアと比べると、異様なほどである。この、メロディなき手紙文→絶叫→メロディの復活→アリア、という構造は、先のアルフレードの叫ぶ場面とそっくりであることに、賢明なる読者はお気づきだろう。メロディを付さないことによって手紙の手紙らしさを表すこれらの表現は、おそらくヴェルディによる意図的なものである。
ところで、このヴィオレッタの場面には、先のアルフレードの場面とは異なる点がある。アルフレードは叫びによって読み上げを中断してしまうのに対して、ヴィオレッタは手紙の全文を読み上げてから叫んでいる。この違いは、おそらく二人の読む手紙の質的な違いに由来している。
アルフレードの場合、手紙を読む声は中断される。そのことによって、その内容を初めて読む彼の衝撃が伝わってくる。いっぽうヴィオレッタの場合、手紙の全文は中断されることなく披露され続け、手紙にはメロディなき声が過剰に付されてゆく。観客はそれをききながら、この手紙の本来持っていたはずの秘密性が、もはや失われていることに気づく。この手紙は、どんなことが書いてあるのかと期待と不安におののきながら声をひそめて読むような手紙ではないらしい。どうやらそれは、すでに何度も飽きるほど読まれ、もはや声に出しても失う秘密がないほどにくたびれ果て、読み古された手紙だ。「遅いわ!」というヴィオレッタの絶叫には、この手紙が最初に持っていた希望を朽ち果てさせた、長い時間に対する失意がこもっている。観客はその失望の深さを、メロディなき声の長さによって知るのではないだろうか。
 《椿姫》より第2幕5景、父ジェルモンの登場場面。「私はアルフレードの父親です」。この後、父親の説得を受けたヴィオレッタは、アルフレードに別れの手紙を書く
《椿姫》より第2幕5景、父ジェルモンの登場場面。「私はアルフレードの父親です」。この後、父親の説得を受けたヴィオレッタは、アルフレードに別れの手紙を書く
第3回・了
このオペラが観たくなったら…

ヴェルディ 《椿姫》
フェニーチェ歌劇場2004
ゼッフィレッリ監督の名作、映画「椿姫」(ストラータス/ドミンゴ主演1982年)から20年-欧州のオペラ・シーンで人気沸騰の美しき歌姫ボンファデッリ、老練のブルゾン、ブッセートの「アイーダ」で彗星のように現われたスコット・パイパーを配し、ドミンゴ指揮という驚愕のキャスティングで実現した、ゼッフィレッリ演出の珠玉の「椿姫」。特典映像『メイキング・オブ・椿姫』など充実したドキュメンタリーも必見です。
■キャスト&スタッフ
ヴィオレッタ:ステファニア・ボンファデッリ
フローラ:アネリー・ペーボ
アンニーナ:パオラ・レヴェローニ
アルフレード:スコット・パイパー
ジョルジョ:レナート・ブルソン 他
演出:フランコ・ゼッフィレッリ
指揮:プラシド・ドミンゴ
アルトゥーロ・トスカニーニ財団管弦楽団
■収録
2002年2月24-27日 ジュゼッペ・ヴェルディ劇場(ブッセート)
■SPEC
- [収録時間] 本編139分 特典映像66分
- [字幕] 日本語・イタリア語
- [映像] 16:9 カラー
- [音声] リニアPCMステレオ/Dolby Digital 5.1/DTS 5.1
- [ディスク仕様] 片面2層(2枚組)
- DVD●TDBA-80210~1 ¥3,570円(税込)