上妻宏光インフォメーション
『NuTRAD』本日発売!インタビュー記事をUPしました。
『NuTRAD』発売記念オフィシャルインタビュー
上妻宏光 最新アルバム『NuTRAD』を語る
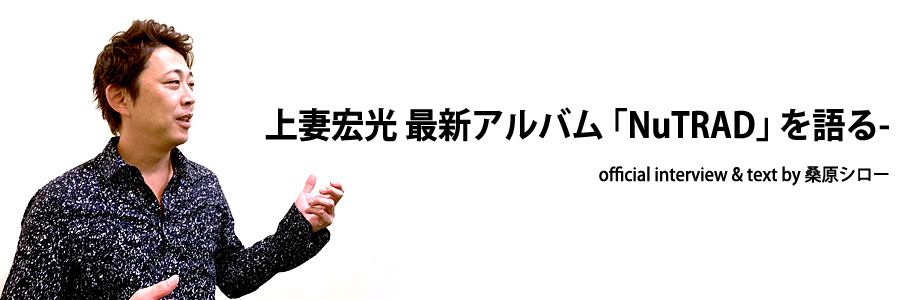
ジャンル横断的な音楽作りを展開してきた上妻宏光のことだからEDMに挑戦したという話を耳にしてもさほど驚きはなかったのだが、ここまでガツンとやられるとは。〈Nu〉という形容詞がこんなに大きく映える内容になっているとは思いもよらなかった。アルバムの出発点を追ってみると、2017年7月、カザフスタンのアスタナ国際博覧会の〈JAPAN DAY〉のステージに立ったことに遡る。それは〈日本の伝統は進化する〉をコンセプトに掲げ、三味線、雅楽、琴、尺八による日本文化の伝統表現、日本舞踊とダンスカンパニー、和楽器と洋楽器とのコラボが行われるなど、上妻のボーダレスな音楽活動を象徴するようなイヴェントだったようだ。そこで彼が得たものとはいったいなんだったのか。
「初の中央アジアでのライヴだったんです。シルクロードは三味線のルーツでもあり、その地に降り立ってみることで何が見えるか、という好奇心も働いていたんですが、何か懐かしいものがあったというか言葉では言い尽くせない感覚をおぼえたんです。そして、そこで得たものを形にすべきだと思いました。これまでにも日本やアジアを意識した作品はあったけど、よりその要素を発信しつつなおかつ楽しめるものを作りたいという思いが募って」
そこから「世界を踊らせたい」というキーワードが立ち上がってくる。そして出てきたのがEDMにアプローチするというアイディア。
「いまや世界の音楽シーンの中心を成しているけれど、僕にとって真逆にあるシーンですよね。知り合いのなかにもEDMを採り込んだ作品を出している人がいるんですが、日本の伝統音楽にEDMをかけ合わせただけのものが多く、結局のところワールド・ミュージック的な枠組みで取り扱われてしまうんじゃないかという不安もあって。そういう壁を超えてみたいというひとつの目的もありました」
あくまでも世界を喜ばせるダンス・ミュージックをクリエイトしたい。学究的なフィールドから抜け出して、人間の根源に潜む喜怒哀楽をつき動かす音楽を奏でたい。そんな欲求を抱えながら、自身の音楽の対極にあるものに思いっきりぶつかってみて、そこに起きる化学変化を確認してみようと彼は考えたようだ。とにかく大事なのはEDMリスナーにも訴求する音楽に仕上げなくてはならないという点。なおかつひとつのジャンルに取り込まれない多面性のある音楽として完成させねばならない。そこは百戦錬磨の上妻である、EDMやネオソウルなどを採り込みながらも、三味線のありようはまったく同じ。着るものが変わったことで見栄えが大きく変化しているが、これまでの彼となんら変わりはない。
「例えばマイルス・デイヴィスっていろんな人と組んでも彼自身のサウンドは不変。でも時を経るごと彼の周りの音楽が変わっていって、さまざまなアプローチをとるようになる。でも僕の目からみたら彼は何も変わらない。僕もまたそうありたいと思いますね」
今回参加した若手アーティストたちは、それぞれの分野で名の知れたクリエイター揃い。オシャレなコードによく調和する似合うフューチャーベース・スタイルの“AKATSUKI”などは、BABYMETALの“KARATE”を手がけたことでも知られるトラックメイカーDJ'TEKINA//SOMETHING a.k.a. Yuyoyuppeが参加。より未来感がアップした“BEAMS”の2018年ヴァージョンは、GRAN TURISMOのオリジナルサウンドトラックのプロデュースなどで知られる嘉生大樹がアレンジを担当している。
「三味線を知らないという人がいたら第一印象でどう感じるのか。僕の音をどう遊んでくれるのか、それって世代によって大きく変わってくるんじゃないかと。経験を積んできた相手なら、ある程度三味線の扱い方を知っているはず。ただEDMの世界に三味線ってほとんど入り込んでいない。三味線っていったいどういう音がするんだろう?ってまだそのレヴェル。そういった人たちがいったいどう加工するのか、オケに溶け込ませるのかが興味があった。僕も何枚も作品を作ってきていますから、三味線のここの部分は変えちゃダメですよ、といった何かしら防御線を張ることもあります。たえずフリーでありたいと思いながらもどこか制約を設けてしまっているところはある。そこに彼らがどんな働きかけをし、突き動かしてくれるのか楽しみだったし、新鮮な作業でした」
注文は最低限に、どうぞ好きにやってくれ、が基本姿勢。そういったプロセスによって生まれた楽曲は予想もしない刺激に溢れ、どれも新鮮な表情をしている。個人的におもしろさを覚えた“CROSS OVER”などバリバリにシーケンスで加工された世界が展開するが、どんなシチュエーションにも対応可能な一風変わったポップ・ミュージックとして成立している。
「でも、あまりEDMに寄りかかり過ぎず、自分自身のスタイルを崩さない、という意識は働いていました。だからラストに登場する“JONKARA”はオーセンティックなスタイルで仕上げている。過去と現在が交差するように心がけたんです」
ここ最近は、吸収する側から手渡していく側になった自覚があると上妻は言う。よりいっそう伝統を継承していく意識も強まっているんだと。
「ここ5年ぐらいでしょうか。それまでは目の前に見えかけているものをつかみ取りに行くという感覚が強かった。でも若い子たちに伝統を伝えていく作業を繰り返しているうちに、意識が変わっていったんです。ここ最近の作品の傾向も変化してますよね。それまでは僕の三味線はどの楽器とも対等であるという意識が強かった。でも、リードを受け持つこともあれば、ベーシックを担当してあえて引くこともあって、前に出たり後ろに回ったり、それぞれの役割を担うことを意識してやっているつもり。他の楽器と重なり合うとどうしても三味線の音が立ってしまうんですけど、今回はなるべくそうならないよう意識しています。そういう意味では、一般的な三味線アルバムとも一線を画しているかもしれない」
伝統と革新のバランスがここにきて彼のなかで変化しているということか。そんな上妻にとって〈新しさ〉を追いかけることの重要性とは?
「ただ本質的に新しいことってなかなか出せないと思うんですよね。だからどういった組み合わせで違った側面を見せることができるか。僕って基本大きく変わってないと思うんです。演奏自体もそうですし、志もそう。ただ、誰かがボタンを押してくれたことで刺激が生まれて、あまり弾いたことのないフレーズが飛び出したり、知らない場所に身を置くことで自分の見えなかった部分に光を当てることができたんじゃないかと。もちろん好きだからこそ世界を広げるようなスタンスを取り続けているんです。深さを追求していくのは良いんだけど、広げるとか継承していくことに比べれば右肩下がりというか、世界をどんどん狭くしていて、その音楽は結果わかる人にしかわからないものになっていく。でもベーシックな部分に枝葉をつけ、花を咲かせることによって、三味線の魅力を広く伝えていくことができる。フィールドが広がることによって新たな才能が生まれる土壌ができたりするのもまたひとつの伝承の形だと。僕がいろんなことにトライすることによって伝承につながっていくはずだと信じている。僕がやっていることって昔の人がやってきたこととさほど大差ないと思っていて。もっと楽器って改良できないか、楽曲っておもしろく出来ないかと彼らが試行錯誤を繰り返したものが継承されて、いま古典となっている。ひょっとしたらこうして僕がやっていることがも、100年後にはクラシックになっているかもしれない。これがあったから三味線音楽ってひとつ広がりを持ったんだよな、と言われるような活動をしたい。それこそ命をつなげていく作業だと思うので」
それはTHE BOOMの“いいあんべえ”カヴァーに参加している宮沢和史の音楽作りにも通じるもの。
「ふたりに共通するのは他県の人間だってこと。沖縄の伝統音楽を継承しているけれど彼は山梨の人間。僕もまた津軽じゃなく茨城の人間。逆に距離を持ちながら眺めることによって何か新しいものを発見できる可能性があるってことなじゃないかと。地元の人よりもより対象を好きになれる熱がある。地元の人間じゃないからいろんなトライも可能になるし」
“いいあんべえ”は“島唄”のあとのTHE BOOMオキナワン・アプローチの第2弾作であるが、ダンス・ミュージックを旗印に掲げた本作にはこちらの曲のほうがよくお似合いだ。聴きどころとしては、出自としてはアニキである三線と弟である津軽三味線が見事に融和していること。出会いのおもしろさが両者の掛け合いから浮かんでくるところなどもそう。『NuTRAD』は上妻がキャッチボールの楽しさを存分に味わった作品でもあるというが、高音が抜けるイイ声をお持ちの朝倉さやと共演した“MOGAMIGAWA(最上川舟唄)”や三味線が本来リズム楽器でもあることを証明するために大儀見元と丁々発止のセッションを繰り広げた“ONE TO ONE”などでも、上妻が奏でる音色から楽し気な感じが滲み出ている。
「三味線で世界を網羅したい。つねに考えていたし、三味線をメジャーにしたい。偏見を持たれることに対して抗ってきた。さまざまなリスナーに訴求する三味線を投げてみたい」という意識を働かせながら今日まで走ってきた彼。そんな彼が今回改めて『NuTRAD』と掲げた心境とはいかなるものだったのか。
「良い響きだと思いますね。そこにひとつの軸を置いてこれからも音楽を作っていきたいですし。ただ、これって新しい民謡なんですか?って言われたら、そういう楽曲ではないんですよね。根底にしっかりと民謡があるうえで新しいものを作りたいという志であったりトライする精神であったりをここで示したかった。これらの楽曲は、いまの自分たちの生活から生まれてきたサウンドになったと言ってもいいかなって思っています」
作品が完成して、どんなアルバムになったと感じているか。
「全編自分のカラーを出しているアルバムだと感じますね。エッジの効いたリズム感が全編に渡って出ている特徴や、アコースティックの楽器の響かせ方にも自分らしさが出ているし、ベーシックもしっかりと提示できた。楽曲のヴァリエーションや演奏のスタイルの方向性、新しいことに向かう姿勢も含めて、ある種集大成な1枚じゃないかと。出せるもの全部出したと思います」
いい意味でカオス渦巻く作品である。不思議な木や花が生い茂っていて未知なる密林に迷い込んだかのようなスリルも味わえる。そんなアルバムから見えてくるのは、攻めの姿勢を維持しながらも、たえずニュートラルな状態で任務を遂行する船長・上妻宏光の姿だ。
「僕は水みたいに生きたいと思っている。型に入れればちゃんと四角にもなれるし、いろんな形を変えながら、つねに冷静にいきたいんです」
最後に言いたいこと。40代の脂がのりまくった彼の演奏にじっくりと耳を傾けてほしい。ガツンとやられること必至なので。
official interview & text by 桑原シロー
(2018/11/7掲載)




