

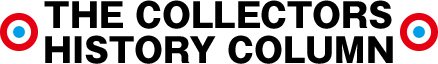
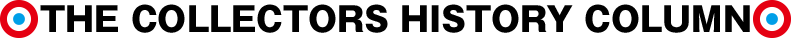
活動30周年の節目に、充実の新作『Roll Up The Collectors』を発表したザ・コレクターズ。ここまでの快進撃を振り返る上で決して忘れてはならない、2000年代に発表したアルバムの中で最も重要な作品が、2007年の『東京虫BUGS』だ。紆余曲折を経てバンドが「開眼」したと言えるこの野心作、つい最近のアルバムのように思っていたが、来年12月でリリースから10年! 時の流れは本当に早い。

2007年は関連リリースの多い年で、まず1月に、2枚目のコレクターズ・トリビュート・アルバムとなる『NO COLLECTORS, NO LIFE.』が発売された。メンバーと縁が深いフラワーカンパニーズや浅田信一&奥野真哉、加藤ひさしが日本デビューさせた台湾の旺福(ワンフー)らが参加する一方で、フーバーオーバー、ANATAKIKOUなど当時の「若手」ロック勢、ラッパーのダースレイダーなど幅広い顔ぶれが集結。やがてコータロー&ザ・ビザールメンの一員になるキタシンイチが在籍していたバンド、ファンキーパンキーも本作に参加していた。
また、加藤ひさしはこの年、現在ザ・コレクターズでドラムを担当している古沢'cozi'岳之が在籍していたFURSのアルバム『BEAT IT FURS!』にプロデューサーとして関わり、次作も手掛けている。それまで直接的な形ではほとんどなかった若手ミュージシャンたちとの交流が、その後のコレクターズの歴史に影響していくことになるわけだ。
2007年は「今」との接点を持ちながら、改めて原点を見つめ直した年でもあった。『NO COLLECTORS, NO LIFE.』初回盤のスペシャル・トラックとして、前身バンドTHE BIKEの「最新スタジオ録音」が突如世に出たのだ。元メンバーの加藤ひさし、リンゴ田巻に加え、ギターは古市コータローが担当。この3人で緊急レコーディングした“僕はひどいパラノイア”は、かつてTHE BIKEのライヴで頻繁に演奏された曲で、沢田研二のアルバム『単純な永遠』(1990年)に加藤が提供した“PLANET”の原曲にあたる。ジュリー・ヴァージョンは歌詞・アレンジ共にまったく異なるので、マニアは是非聴き比べてみて欲しい。
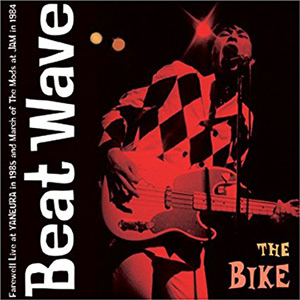
このサプライズ復活を号令に、THE BIKE~BIKES(末期の4人編成時代)の音源をコンパイルしたアルバムが2枚続けて登場。80年代前半の未発表ライヴ音源が『Beat Wave』に、高額で取引されていた自主制作ソノシートの収録曲とデモ音源が『Alive Heritages』にまとめられた。いずれも貴重なライヴ映像入りDVDをセットした2枚組。その後コレクターズで再録音される楽曲を多数収録、パンク/ニュー・ウェイヴ色が濃い演奏だが、すでに強烈なオリジナリティを発揮していることに驚かされる。もうひとつ興味深いのは、これら発掘盤のマスタリングを、共にモッズ・シーンで切磋琢磨した元ザ・シャムロックの山森“JEFF”正之が担当したことだ。

若き加藤ひさしにとってTHE BIKEは彼のすべてを賭けた宝物であり、このバンドで成功するという悲願が叶わなかった悔しさが、新たにコレクターズというバンドを生み出した。長い間封印してきたTHE BIKEの遺産と、ようやく正面から向き合えるようになった時期。特にコレクターズ脱退以来久々に実現したリンゴ田巻との共演は、気持ちに一区切りをつけるいい機会になったはずだ。

前作『ロック教室〜THE ROCK'N ROLL CULTURE SCHOOL〜』で他者が書いた詞・曲を取り上げ、「コレクターズ節」とは異なる表現に触れた経験。2000年代の若手バンドから得た刺激。前身バンドの音源を整理するなかで、再度向き合った若き日のパッション。それらすべてを糧として、『夜明けと未来と未来のカタチ』以来久しぶりに取り組んだ全曲オリジナルのスタジオ・アルバムが『東京虫BUGS』だった。
中でも最も驚かされたのが、アルバム冒頭を飾った“たよれる男”。歌詞のストーリー性や詞世界を重視してきた加藤ひさしが、この曲では言葉の響きと語呂の良さに焦点を絞ってきた。ラップよろしく韻を踏みながら、イメージが予想外の飛躍を見せていく。今でこそライヴの定番曲として定着した“たよれる男”だが、ここまで思い切った変化が歌詞に顕われたのは、コレクターズ史上初めてのこと。古くからのファンを戸惑わせるのは承知の上で、変わろうとする姿勢を示した勇気ある一歩だった。そしてここでの変化は、この後続く3部作『青春ミラー(キミを想う長い午後)』『地球の歩き方』『99匹目のサル』へと受け継がれていくことになる。
曲調や演奏にも変化が顕われ始めた。前作の“Thank U”で解禁されたレッド・ツェッペリンを思わせるダイナミックなハード・ロック的グルーヴ/リフ・ロックの快感が、コレクターズの新たな柱になったのは本作からだ。90年代に16ビート導入などの冒険を経てはいたが、その頃とは異なる角度から、「日本語のロックンロール・バンドとしてのグルーヴ」を再度模索。歌詞の変化と音の変化は不可分で、密接に結びついていた。その好例が、“東京虫バグズ”だろう。古市コータローのドライヴするリフが先導する形で突き進んでいくこの曲は、「3部作」で様々に試されるリズム追究の始点とも思える。
また、本作ではそれまでブリティッシュ・ロック派だった加藤ひさしの視野がグッと広がり、この年ヒットしたザ・ハイヤーのようなアメリカ産のダンサブルなパワー・ポップも横目で見ている。旧来のロックのリズム感が更新され、パンク系のバンドですらヒップホップ的なビートを用いるのが当たり前になってきた時代。そうした手法を従来のサイケ・ポップ感とうまく融合させたのが、“ザ モールズ オン ザ ヒルズ”だった。
1997年に『HERE TODAY』を完成させて以降、向かうべき次なる道を探し続けているように見えたコレクターズ。彼らが「コレクターズらしさ」というフォーマットを一旦『東京虫BUGS』で思い切ってリセットしていなければ、バンドの創造性は袋小路に入り、現在まで続かずに座礁していたかもしれない。お馴染みのレパートリーを繰り返し演奏するだけのベテランではなく、時代と共に変化しながら行き続ける生涯現役のロックンロール・バンド…それこそがコレクターズの進むべき道であり、彼らが定義するところの「Mods」であることを明示したのが、この『東京虫BUGS』というアルバムだった。
荒野政寿(CROSSBEAT)