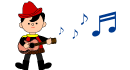[この一枚 No.50] 〜ヘルマン・プライ/モーツァルト:オペラ・アリア集〜
| 「いつもどうもありがとう ○○様 八九・四・七 吉田秀和」。私の手元に
先月亡くなられた吉田秀和氏のサイン入りの著書が1冊ある。二十数年前に鎌倉のご自宅に伺ってオーディオ装置を点検し、その後、色々お話を伺った折にプレゼントされたものだ。 当時、クラシックCDのセールスに大きな影響力を持つものは、「レコード芸術」誌の特選、朝日新聞の「試聴室」、そして吉田氏の2つの連載、「レコード芸術」誌の「今月の1枚」と朝日新聞での「音楽展望」であった。時に朝日の「母と子の試聴室」や「ブーニン人気」を起こしたNHK TV放送などもあったが、本流ではなかった。 こんな、影響力の大きい吉田氏だが、レコード会社宣伝担当からの直接の連絡は許されず、レコード芸術誌の編集長が氏ご指名の新譜を集め、鎌倉に届けるという不文律があった。稀に、氏が原稿を書くうえで不明な点の問い合わせの電話があったり、関連する旧譜を送ったりするのがわずかな接点だった。なので、何かの都合で直接吉田邸に新譜を届けるように編集長から言われたときは「チャンス到来」とばかりに緊張した。鎌倉駅で下車し、若宮大路を八幡宮まで歩き、路地をたどって行くと、なにげない普通の民家が吉田邸だったのにはいささか拍子抜けした記憶がある。 そんな吉田邸への再訪の話が突然湧いてきたのは89年春だった。吉田氏のオーディオ装置の調子が悪くなり、困った氏は周囲の人々に相談を持ちかけた。当時、日本コロムビアはレコードとオーディオ機器の両部門を持っていたので、私はオーディオ機器宣伝担当に「良い音」のクラシックCD新譜をプロモーション用に渡し、オーディオ評論家とのコミュニケーションを図ってもらうなど、関連部署との交流を行っていた。そんな関係を周囲の誰かが知っていたのか、「アイツに点検をさせましょう」となり、白羽の矢が立った次第である。 吉田氏には事前に電話で不具合を尋ね、オーディオ部門から交換機種を手配して、久し振りに鎌倉に伺った。通された部屋のオーディオ・ビデオ装置の接続を確認し、問題機種の交換と全ての動作確認を終えたのは数時間後だっただろうか。その後、和風の居間に敷かれた絨毯の上の応接椅子に向かい合って座り、談笑させていただいたが、氏は年下の者にも偉ぶる事無く、同じ目線で応対してくれた。話し方はNHK-FMの「名曲のたのしみ」のナレーションそのままだったこと を強く覚えている。 吉田邸を後にするときに、氏が表紙裏にサインし、渡してしてくれた本が「二度目のニューヨーク」だった。 当時でも社内にレコードとオーディオ部門を抱える会社は多くなかった。日本では当社のみ、(ビクターのレコード部門は子会社であった)世界的にもオランダ・フィリップスが思いつく程度だろうか。いずれも今は無くなったが、この両部門対等の関係が社内でのPCM録音機の開発や、海外でのオーディオ機器の販売やデジタル編集機の売込などの連携に繋がっていった。 日本コロムビア海外事業部ではオーディオ機器の海外販売を目的に1980年デノン・アメリカを、続いて1983年には西ドイツ、デュッセルドルフ近郊にデノン・ジャーマニー(エレクトロニック)を設立したが、ソニーやヤマハ、ビクター、パイオニアなどの同業他社に遅れをとったドイツ進出で、ブランド・イメージの確立が急務だった。また、レコード事業部にとってもドイツ販社の設立はヨーロッパ録音用の機材を録音毎に日本に持帰ることなく、恒常的にドイツ販社の倉庫に保管できるようになり、コストや安全面で大きな利点となった。 設立当初、「デノンのオーディオ機器は高音質なデノン録音の技術が生かされています」とドイツ人に訴えかける予定だったが、CDカタログのアーティストはドイツ人にとって馴染みのないフランス人、チェコ人、日本人、さらに当時政治的に緊張関係にあった東ドイツ人などで、西ドイツのアーティストは殆ど見当たらなかった。「無ければ、大物ドイツ人を起用してCDを作ろう」、その線でデノン・ジャーマニー副社長の西村は東京の洋楽部に「ヘルマン・プライでシューベルトの歌曲集の録音を行えませんか?」と依頼した。 鮫島有美子が登場する前の日本コロムビアには「歌曲」、「オペラ」の自主音源は殆ど無かった。1982年ウィーン・フォルクスオパーの日本公演から「こうもり」、「メリー・ウィドウ」、「ウィーン気質」のライヴ盤が目立つだけで、セールス的に厳しいドイツ歌曲は「欲しいが、他社音源を用いる」という状況であった。そこに「ヘルマン・プライ」という大物が浮上した。 1929年生まれのプライは日本では同世代のディートリヒ・フィッシャー=ディスカウ(1976年プラハの「芸術家の家」のモニタールームで見た指揮者としての彼は大変落ち着いた目をしていた)と比較され、「軽い」とやや下に見られていたが、欧米ではオペラからミュージカル、また歌曲からコール・ポーターまで歌い、多くのTVに出演するなど、その歌手活動の幅広さでトーマス・ハンプソンをはじめとする多くの後輩歌手や音楽家たちから尊敬され、高い知名度を誇っていた。 1984年4月、西村の熱意もあり、このプロジェクトのゴーサインが出て、ハンブルクでヴォルフ・エリクソン(コロムビアのブックレットではエーリヒソン、またはエリヒソンと記載されているが、テレフンケン、セオン、そしてソニーのヴィヴァルテのプロデューサーとして、この呼称が一般的)をディレクターに迎え、フランス人ピアニスト、フィリップ・ビアンコーニのピアノ(ベーゼンドルファー)でシューベルトの「冬の旅」続いて「白鳥の歌」の半分が録音された。 翌85年5月にはシューマンの「詩人の恋」、8月にはシューベルト「美しき水車小屋の娘」と「白鳥の歌」の残り、11月には「愛の歌」、86年5月にはシューマン「リーダークライス」、そして10月にはマーラー交響曲第8番《千人の交響曲》のソリストの一人、そのままザルツブルクに移動してモーツァルト/オペラ・アリア集、と3年間でバリトン歌手の主要レパートリー7枚のアルバムをいずれもエリクソンのディレクションで録音している。 余談だが、このオペラ・アリアの指揮者ブルーノ・ヴァイルは当時、ウィーンのオペラハウスなどで指揮を行っていたが、この録音がきっかけでエリクソンに認められ、彼が主宰するヴィヴァルテ・レーベルで古楽器オーケストラ、ターフェルムジークの指揮者に抜擢された。 当時の西ドイツではヘルマン・プライの威力は絶大で、デノンのオーディオ機器の発表会に彼がゲストで登場すると、マスコミは騒然とし、「プライが録音した日本の会社デノン」の認知度は急上昇し、たとえ録音制作費は回収できなかったとしても、莫大な宣伝効果があった。 いま、「この7枚の録音の中からオススメは?」と問われるならば、「プライの美声と明るさが感じられる、聴いて楽しいモーツァルトのオペラ・アリア集」を挙げるが、吉田氏ならばどうだろうか? 頭をかきながら、「それは当たり前すぎるよ。ドイツ語の詩とメロディが一体化しての美しさや深さを表現したシューベルトやシューマンを聴いてごらん。そこには歳や経験を積んでも『永遠の青年』のプライが感じられるから」と話してくれるだろうか。 (久) |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
[この一枚] インデックスへ |
|||