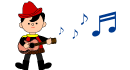[この一枚 No.51] 〜渡邉暁雄/シベリウス:交響曲全集〜
| 1981年末、日本コロムビアはレコードアカデミー賞を3つの部門で獲得した。交響曲部門でスウィトナー指揮ベルリン・シュターツカペレのベートーヴェン:交響曲第6番「田園」、室内楽曲部門でスメタナ四重奏団+スークのモーツァルト:弦楽五重奏曲第2番、第6番、そして日本人演奏部門で渡邉暁雄指揮日フィルのシベリウス:交響曲全集である。 渡邉暁雄指揮日本フィルは1962年、世界初ステレオ録音によるシベリウス交響曲全集が当時日本コロムビアとライセンス契約を結んでいた米国CBSのエピック・レーベルから全世界に発売されたことで、クラシック・レコードの歴史に大きくその名を刻んだ。 この録音も含め、当時の日フィルの録音は日本コロムビア録音陣の手によるものでなく、日フィルの親会社である文化放送のスタッフ、ディレクター草刈津三、ミクサー若林駿介によるものだった。 日本コロムビアの録音スタッフによるオーケストラ録音が行われ始めるのは1968年前後。日本コロムビアと米国CBSとのライセンス契約が終了し、クラシック音源を自主録音に求め始めた頃である。岩城宏之指揮NHK交響楽団のベートーヴェン交響曲全集の録音は、前述のフリー・エンジニア若林氏が6曲、日本コロムビアの林氏が3曲を担当している。 1972年にPCM(デジタル)録音が開始されてからは林正夫、岡田則男、後藤博、塩澤利安と、日本コロムビア録音部生え抜きのスタッフが国内外のオーケストラ録音を担当し、数々の名録音を残して今日に至っている。 話を戻そう。渡邉暁雄が日本コロムビアのデジタル録音に登場するのは1977年6月、チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲をカントロフの独奏、東京都交響楽団の伴奏で指揮したのが最初だった。その時のモニタールームでの印象は「物静かな、穏やかな指揮者」というものであった。 そして、1972年の日本フィルの分裂騒動も落ち着いた81年6月、1956年のオーケストラ結成から25周年を記念して、再び渡邉暁雄指揮日フィルのシベリウス交響曲全集のデジタルによる世界初録音が開始された。今回のディレクターは結城亨、録音エンジニアは林正夫という日本コロムビアの生え抜きが担当した。 62年盤の録音会場では客席が取り払われた東京文化会館小ホールなど数会場が用いられていたが、81年盤もオープンしたばかりの習志野文化ホールや昭和女子大学人見記念講堂で行われた。人見記念講堂は収容人員2000人強の大ホールで、残響時間は2秒以上あるのだが、ステージが広いためにオーケストラの音が纏まって音の厚みとならずに分散してしまう印象があり、反射板の位置や角度などに苦労した記憶がある。また、人見記念講堂裏の楽屋はモニタールームとして適当ではなかったため、急遽ロビーがモニタールームとなった。 この録音でも渡邉氏の印象は前回のチャイコフスキーと同じく、「紳士的」という言葉がふさわしかった。練習で楽員に声を荒げることなく、プレイバックを聴くときも、録音スタッフに対する演奏や音の注文は少なかった。そんな性格も影響があるのだろうか、第1番や第2番など、熱い演奏を期待すると、いささか物足りなさを感じるが、シベリウスの音楽のスタイルが大きく変わる第3番以降は端正さと程よい情熱がうまくブレンドされており、結果、81年のレコードアカデミー賞に選ばれたのだ、と納得させられる。 また、62年の旧盤と81年の新盤では録音スタッフの音処理の違いも面白い。顕著にその特徴が判るのはハープやグロッケンシュピールの扱いで、若林氏の録音が音楽的に作りこみ、説明的なものとするならば、林氏の録音ではコンサートホールで聴く様な自然な響きが捉えられている。 2008年9月、若林氏の追悼の会で参列者に想い出のCDを配布する、という企画が挙がった。氏の多くの録音の中から62年、世界初のシベリウス交響曲全集の中の1枚を選び、渡邉氏のご遺族に伺ったところ、「父は第4番が大好きで、またこの演奏は高く評価されていますので、この曲を是非」とのお言葉があった。 改めて旧、新盤を聞き比べると、おそらく、渡邉氏以外に同一レーベルに2回もシベリウスの交響曲全集を録音する指揮者は今後も現れないだろう、と感じられる、共に「紳士的な」素晴しい演奏だった。 (久) |
|||
|
|||
[この一枚] インデックスへ |
|||