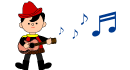[この一枚 No.57] 〜ティーレマン/ワーグナー:《ニーベルングの指環》バイロイト音楽祭2008年〜
| 大阪で万国博覧会が開かれた頃、九州に新設されたばかりの大学の音響設計学科で日本のクラシック録音の第一人者、若林駿介氏の集中講義が開始された。講義内容はステレオ理論からマイクロフォンやテープレコーダなどの録音機材の操作方法、また録音実習や自身が録音したマスターテープを用いた様々な音源の研究など収音(放送、録音、拡声)に関して多岐に渡る内容であった。 そして、この講義の中で一冊の本『ニーベルングの指環―プロデューサーの手記』が紹介された。 「この本の著者、ジョン・カルショーは1958年から65年までの8年を費やしてショルティ指揮ウィーン・フィルでワーグナーの楽劇《ニーベルングの指環》全曲を録音した英国デッカのプロデューサーです。当初、この本はキング・レコードから《指環》全集がLP19枚組(他にライトモチーフ3枚)として発売されたときの特典として付けられたのですが、その後、本単独でも販売されています。 カルショーはこの中で大作《指環》録音に関する様々な興味深いエピソード、まず企画から実現へ、音楽家との人間関係、スケジュール調整の苦労、オペラの録音テクニック、そして販売手法などを紹介しています。とても内容のある本なので、将来この分野を志す諸君は是非一度読んでおくことを薦めます」 当時、大卒の初任給が三万円前後の頃に、この《指環》全集は四万円という価格であった。現在の物価に換算すると三十万円前後であろうか、到底、学生の小遣いで買えるものでなく、音楽之友社から出版されたこの本(それでも確か四千円ぐらいだったと記憶する)を購入し、そこに記載された数々の録音テクニックや地下の鉱山に降りてゆく場面での無数の金床の音、ニーベルハイム族の悲鳴、神々のワルハラ城への入場前に鳴り響く雷などの「音のドラマ」は想像するしかなかった。 ただ、年末のNHK-FM放送、バイロイト音楽祭ライヴが《指環》の音楽に触れる機会だった。 次の《指環》体験は1983年、日本コロムビアから世界初のデジタル録音として発売されたヤノフスキ指揮ドレスデン・シュターツカペレの演奏だった。 以前、このコーナーでも取上げたが、このプロダクションは旧東ドイツのドイツ・シャルプラッテンが国家威信をかけて西ドイツのオイロディスクと共同制作したもので、ヨーロッパでは豪華なカートン・ケース入りのLPレコードだったが、日本ではワーグナー没後100周年記念としてCD18枚組、¥63,000として発売された。 ドイツから送られてきたマスターテープはレコードの面ごとに音が切れた状態で送られてきたので、担当の山崎ディレクターはまず楽譜上で面の切れ目を確認し、CDの収録時間(当時は70分を越えて収録できるヴィデオ・テープが入手困難で、しかも長時間CDは製造技術が確立されておらず、収録時間は64分前後と制限されていた)を加味して、CDの面割を決めることだった。そして、私はデジタル編集室で楽譜と照らし合わせながらLP面の切れ目を繋ぎ、CD用のマスターテープを作る編集作業を担当、連日ドレスデンのオーケストラと名歌手達が繰り広げる《指環》の華麗なサウンドに没っていた。 このヤノフスキ盤から30年弱が経過した2010年、日本コロムビアは待望のワーグナーの聖地バイロイト音楽祭でのライヴ録音、クリスティアン・ティーレマン指揮バイロイト祝祭管弦楽団&合唱団による《指環》2008年をCD14枚組、\18,900という超お買い得価格で発売した。 この盤は一聴すると直ぐに「他ではない、まさしくバイロイト祝祭劇場で収録されたもの」と判る。 例えば第一夜「ワルキューレ」の冒頭、これからの波乱の物語を暗示する前奏で吹き荒ぶ風雨を現す第一ヴァイオリンが右側から聴こえてくる。「右側から?」、これは決して再生装置の接続の誤りではなく、バイロイト祝祭劇場では第一ヴァイオリンは指揮者の右側に位置しているからだ。 ワーグナーが「観客が指揮者やオーケストラを観ることなく、舞台上のドラマに集中する」という理想を実現するために、自ら設計したこの劇場のオーケストラ・ピットはステージ手前からステージ奥に向かって掘り下げられた空間で、しかも、客席から見えないように紗幕で覆われている。 その中にオーケストラは、いわばひな壇を逆にした形で並んでいると考えれば理解して貰えるだろうか。一番上に指揮者、そして一段下がって右側に第一ヴァイオリンが位置する。またウィキペディアによるとチェロ、コントラバス、ハープはグループごとに左右に分けられ、他の楽器は順々に奥に向かって下がり、金管、打楽器ははるか下に位置するらしい。 第一ヴァイオリンは上手に位置しているので、構えた楽器の直接音は客席に向かうのではなく、まず、ステージに向かい、はね返って聴衆に届く。その他の楽器の音も地下のオーケストラ・ピットの中でブレンドされて紗幕を通じて聴衆に届く。 このため、通常の劇場ではオーケストラ楽員は歌手を見て、その歌や動作に併せて演奏することが可能だが、ステージが全く見えないバイロイトでは只、指揮棒だけが頼りである。歌を聴いて演奏すると観衆には歌とオーケストラがずれて聞こえてしまう。世界的指揮者でもこの劇場独特の空間に慣れないと演奏が難しいと言われる由縁である。 この劇場で聴くサウンドは、(実際1992年8月末に「タイホイザー」を聴く機会があり、デュッセルドルフから500kmの距離を車を飛ばしてバイロイトに辿り着き、終演後、また同じ道を帰ったのは懐かしい思い出だが)、真っ暗な劇場の底から聴こえてくるオーケストラ音はあまりに柔らかく、悪く言えば輝かしさや迫力の無さに唖然とした。その代わり、歌手の声はオーケストラの強奏時でも埋もれることなく、明瞭であった。これがワーグナーの理想だったのだろうか? このCDの録音もウィーンやドレスデンでのスタジオ録音では決して作れない、バイロイトのオケ・ピットでブレンドされた厚い弦楽器を中心としたオーケストラ・サウンドや、一昔前のワーグナー歌手と呼ばれる強い声ではないが、無理の無い歌声が作り出すステージ、そしてなにより指揮者ティーレマンが創り出す音楽の熱気という、この公演の特徴を良く捉えている。 バイエルン放送局との共同制作として、CDにクレジットされている録音スタッフはレコード会社やサウンドスタジオのメンバーではなく、ベルリンのヴィデオ制作会社のスタッフのようだ。公演当初から映像を前提とした音創りを目指し、まず2008年公演のCD化、そして2010年公演から「ワルキューレ」の映像化という順序だったのだろうか。 ワーグナー生誕200年の今年、各方面で《指環》が話題に上るとき、ティーレマンのこの演奏は「現代のワーグナー演奏の1つのスタンダード」として広く取上げられるだろう。 なお、冒頭に紹介したカルショーの本は長い間絶版であったが、2007年山崎浩太郎氏の訳で「ニーベルングの指環、リング・リザウンディング」として復刊されている。 カルショーはこの本の最後を「Zuruck vom Ring!」(指環に近づくな)という「神々のたそがれ」の最後のセリフで閉じている。逆を言えば、《指環》はそれほどまでに人を惹きつける作品なのである。 (久) |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
[この一枚] インデックスへ |
|||