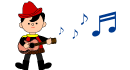[この一枚 No.67] 〜高橋悠治:J.S.バッハ《インヴェンションとシンフォニア》(装飾稿による)〜
|
昔のことだが、音楽評論家の佐々木節夫さんに誘われてベルギー、アントワープ(Antwerp)の古楽フェスティヴァルAntwerpiano(アントワーピアノ)の一晩のコンサートを聴いたことがあった。このフェスティヴァルは名前の最後にピアノ(piano)が組み込まれていることからもお解りのように、アントワープ出身の古楽指揮者、鍵盤楽器奏者ジョス・ファン・インマゼールが彼の地元で様々な歴史的鍵盤楽器の展示とそれらを用いたコンサートを行うために1989年から催されたもので、日本からは故小島芳子さんなどが出演していた。 佐々木さんと聴いたコンサートは鍵盤楽器の歴史を一晩で巡るプログラムで、ステージ上には様々な楽器が並べられていた。数百人の聴衆の前に現れたインマゼールは、まず小さなクラヴィコード(チェンバロより小型の鍵盤楽器)でバロック時代の音楽を演奏し始めたが、その音量はあまりにか細く、いくら客席で耳を済ましても音楽として捉えることができなかった。2曲目はチェンバロで、以降、モーツァルト時代のフォルテピアノ、ベートーヴェン時代のフォルテピアノと続き、後半のショパン、ドビュッシーではピアノが大きくなり、それに連れて音量、音色も豊かになっていった。 冒頭のクラヴィコードはバッハの時代、家庭で音楽を楽しむため、もしくは鍵盤楽器の練習用として普及したもので、インマゼールの意図は理解できるが、大きなホールでのコンサートに用いるには無理がある、と感じた一夜だった。 1970年大阪万博の鉄鋼館ではクセナキス、武満徹の作品と共に作曲家・高橋悠治の「エゲン」が1000個以上のスピーカを用いたサラウンド空間で再生上演されたことで、日本では「若き鬼才」として現代音楽ファン以外にも彼の名が知れ始めた。 翌71年、日本コロムビアはピアニスト・高橋悠治と契約し、イイノホールで「ベートーヴェン、メシアン、ストラヴィンスキー」のアルバムを録音する。以降、担当ディレクターは結城から川口に替わるが、79年頃まで多くのピアノ作品などを個性豊かに録音していく。 1720年、バッハが当時10才の長男、ヴィルヘルム・フリーデマン・バッハの鍵盤楽器練習用として作曲した作品が基本となっている《インヴェンションとシンフォニア》。 高橋が演奏するこのCDを現代のピアノ教師とフリーデマンと同じ年代である小学校高学年か、中学・高校生の生徒に聴いてもらうといったい、どんな反応を示すだろうか? おそらくピアノ教師はまず「なにこれ?この演奏と音!」と思われるだろう。 無理もない、第1曲目、ハ長調のインヴェンション冒頭から三連符の異稿を用い、様々な箇所が楽譜に無い装飾音で飾られている。そしてインヴェンションに続いては1番のシンフォニアが演奏され、さらにフラット記号3つが付けられた難しい第2番、ハ短調のインヴェンションではなく、フラット記号1つの第4番、ニ短調のインヴェンションに飛ぶなど、曲順を大幅に変えている。 おまけに高橋の演奏には独特の癖があり、加えてペダルを使っていないことや、残響があまり付けられていないこともあり、まるで家庭のアップライトピアノで弾いているように聴こえる。 ピアノ教師は「何故この演奏なのか?」を考える前に「生徒には練習用手本としては聴かせられないCD」と受け止められるかもしれない。 一方、ティーンエイジャーの生徒達は「COOL!」と受け止め、踊り出し、「このカッコイイ装飾はどうするんだろう?」とピアノに向かう子供もいるだろう。 ここで演奏家やコロムビア制作陣(川口・林)が意図したのはなにだったのだろう? 1970年代初頭、新バッハ全集の《インヴェンションとシンフォニア》の楽譜がドイツの楽譜出版社ベーレンライターより発売されたが、このアルバムは出版されたばかりの新バッハ全集をベースとしながらも、そこに様々なひねり技が加えられている。 まず、バッハの長男はおそらく、家庭のクラヴィコードで練習していただろうと想像することから、ピアノの音もそれに似せて、響きの豊かなコンサートホールで聴く感じではなく、あたかもクラヴィコードの隣で聴いているような近接的で、響きの少ない音に仕上げている。 曲順は当初バッハが息子の練習用に与えた難易度の低い順に並べ替えている。 1723年、バッハはこの曲を発表する時、最終稿の長調から短調に続ける調性の順序か、臨時記号が1つずつ増えてゆく難易度の順にするか迷い、結果、同時期の《平均律クラヴィーア曲集》と同じ調性の順序としたが、高橋は作曲された当初の教育目的に沿って難易度の順に戻している。 2声のインヴェンションに続いて3声のシンフォニアを演奏する理由は、この曲集の冒頭に書かれているバッハの言葉を引用しよう。「2声部をきれいに演奏するだけでなく、さらに上達したならば3声部を正しくそして上手に処理し、それと同時にすぐれた楽想(Inventiones)を身につけて、しかもそれを巧みに展開すること。・・・(音楽之友社 ウィーン原典版より引用) このインヴェンションとシンフォニアを続けて演奏するアイデアは高橋が最初では無く、グレン・グールドが1964年に録音した同曲のアルバムでも行われている。 そしてグールドもまた曲順を変えているが、高橋のようにバッハの教育目的の順ではなく、なぜこの順序なのかはライナーに記載が無く、ネット上で探しても答えは見つかっていない。 20世紀前半の巨匠達の時代には楽譜に無い音を加えたり、テンポを変えたりする恣意的な、ドラマチックな演奏が繰り広げられていた。その反省から今日まで「楽譜に忠実に演奏する」という教育がなされている。その観点から高橋の演奏を聴くと、至る所に楽譜に無い、様々な装飾音が付けられている。代表例として第5番のシンフォニアを取り上げよう。 この低音部の上昇音型に支えられて上の2声が和音でゆっくり動いていく音楽は楽譜のまま演奏すると単純で、退屈な音楽に聴こえかねない。しかし、音楽之友社版では次ページに記載されている別稿では全曲が装飾で飾られ、あたかもさなぎが蝶に変身したかのように大きく変容している。高橋はこの装飾稿を丁寧に、歌うように演奏し、まるでベートーヴェンのピアノ・ソナタの緩徐楽章を弾いてるかのように聴かせる。バッハの時代、まだ音域も狭く、強弱も小さかった鍵盤楽器で音楽のメリハリを装飾でつけることは自然なことであったし、上手に装飾を付けることが創意として演奏家に求められていた。楽譜に記されていない装飾をつけることはバッハにとっても、また高橋にとっても当然の行為で、「楽譜に書いてない音が多すぎる。ケシカラン」と叱る次元ではない。 マスターテープの編集では曲順が楽譜の順序と異なることや、いくつかの装飾稿は楽譜の途中や最後に記されていることから、あちこち楽譜を捲らなくてはならなかった。しかし最後にゆったりと第2番ハ短調のシンフォニアが聴こえてきたとき、まるで《平均律クラヴィーア曲集》の第24番のプレリュードに接したときのような、この曲集が単に教育目的だけでなく、バッハの偉大さを感じさせる小宇宙であることが感じられた。 このアルバムはまるで骸骨のような音と演奏で、一見奇妙に聴こえるが、骨格標本からは骨と骨の構造と機能が良くわかるように、そこに良く考えられたバッハの音楽の構造と凄さが透けて見える。 和田誠のジャケット・デザインも素敵で、ジョン・ケージのプリペアード・ピアノのアルバムと共に楽譜片手の試聴を勧める高橋の1枚である。 (久) |
|||
|
|||
[この一枚] インデックスへ |
|||