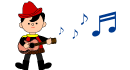[この一枚 No.76]〜ハンス・フォンク/R・シュトラウス:楽劇「ばらの騎士」〜
| 第1回PCMヨーロッパ録音の日程がほぼ固まりかけ、完成したばかりのPCM録音機2号機の調整と海外に持ち出す機材のリストアップや準備に追われた1974年秋、東京文化会館ではバイエルン州立歌劇場の来日公演が行われていた。 中でも、前年にオペラ「魔弾の射手」全曲盤で鮮烈なレコード・デビューを果たしたカルロス・クライバーが指揮する「ばらの騎士」には注目が集まっていた。 クライバーは期待を裏切らなかった。むしろそれ以上だった。スポットライトを浴びて指揮棒を振り下ろした瞬間から黒人の子供がハンカチを拾って舞台を去る最後まで、私はクライバーの、またR・シュトラウスの音楽の渦の中に取り込まれて、3時間の公演が一瞬に感じられるほどだった。 直後にクライバーがこの曲を録音していないこともあり、Boosey&Hawkes社から出版されているR・シュトラウス・オペラ全集の一冊、「ばらの騎士」の楽譜、豪華装丁A4版500ページ以上の大型本を買い求めた。暫くは楽譜を眺めて、R・シュトラウスの甘美で複雑な作曲・オーケストレーションに感心するばかりだった。 10年後、旧東ドイツ、ドイツ・シャルプラッテンとの共同制作で、ドレスデン・ゼンパーオペラハウスの復興こけら落とし公演のライヴ録音共同制作の話が纏りかけていた。そんな時期に、巨匠カラヤンによる2回目の「ばらの騎士」デジタル録音盤発売のニュースが流れてきた。 ゼンパー・オペラの演目が「魔弾の射手」と「ばらの騎士」と決まっていたこともあり、演奏・録音の比較対象として購入したが、聴き進むうちに、「人生の黄昏時を迎えた巨匠が残した遺産」と呼べるかのように、演奏・録音ともに細部に渡るまで丁寧に磨き上げられたカラヤンの演奏は別格であることを感じさせられた。 翌1985年1月、まだ正月という頃に日本コロムビアの録音スタッフの穴澤、高橋両名と共に、私の楽譜とCDがドレスデンに旅立った。出発直前まで幾つかの楽譜店に「ばらの騎士」の購入を手配していたのだが、いずれも在庫切れや入荷見込みなしと断られたため、急遽私物の楽譜とCDを共に差し出すことになってしまったのだ。 クラシック録音では、録音済テープ、編集箇所とテイク番号が記された楽譜、そして双方を繋げるテープノート(記録)、この3点が三種の神器で、どれが欠けても編集ができず、マスターテープが作れないのだ。これで何故楽譜がそんなに重要なのかが理解して頂けただろうか。 1945年2月13日から15日に渡る英米空軍のドレスデン大空襲でゼンパー・オペラハウスは焼け落ち、長い間廃墟としてエルベ河の畔に曝されていたが、40年後の1985年2月、遂にその美しい姿を再び現した。 この国家プロジェクトとも言える復興公演はヨーロッパ各国にテレビ中継され、CD、映像制作が決まっていた、完成したばかりの劇場での手探りの録音でもミスは許されなかった。 初出の解説書のクレジットにはB&K社とSCHOEPS社の両マイクロフォン・メーカーへの感謝が、さらに中には「録音について」として、技術陣による録音手法の説明が記されている。 それによると、ドイツ・シャルプラッテンの名録音エンジニア、クラウス・シュトリューベンと穴澤、高橋は、マイクロフォンの選択について検討を行った結果、メインマイクロフォンとしてSCHOEPSのMK3、無指向性マイク2本を天井から吊り下げ、オーケストラ・ピット内のオーケストラ収音用にB&K4006無指向性5本+補助マイク、舞台床前面中央にSCHOEPS MK4単一指向性マイク2本をORTF方式で置き、舞台前面左右と舞台天井に計9本のMK4マイクを仕込んだ。SCHOEPSは小型で、また照明がマイクに当たっても反射しにくい艶消し塗装がされており、その存在を気づかれにくい製品である。 コンサートのライヴ録音ならば良い音のする空中に吊り下げられたマイクロフォンが見えても問題視されないが、舞台上で繰り広げられる歌や演技を楽しみにオペラハウスを訪れた観客の視線の先にマイクロフォンが見えることは許されないのだ。 1月半ばから「魔弾の射手」と「ばらの騎士」のリハーサルとテスト公演(例えば傷痍軍人のための公演とか)が度々交互に行われ、少しずつ手直しが入り、2月13日と14日の復興記念公演本番を迎えた。 ワーグナーの盟友でもあったゼンパーが設計したオペラハウスの美しい響きが再び甦った!この公演はテレビ中継され、またニュースとして全世界に発信された。 公演の成功の余韻に浸る間もなく、 録音スタッフは編集個所と使用テイク番号が記載された楽譜と録音済テープ、ノートを直ちに日本に送り返したが、そこには「2月末にドレスデンで編集済テープの試聴会が行われるので、間に合うように編集を頼む」とのメモが添えてあった。 テープの往復の空輸、通関の時間を考えると2つのオペラの編集期間はわずか1週間しかなく、テープが編集スタジオに届いた日から突貫作業が始まった。 「魔弾の射手」はセリフが多く、オーケストラ編成も大きくないので編集は問題なく進んだが、「ばらの騎士」は前から楽譜を眺めていたので予想はしていたが、はるかに難問だった。 全編に渡ってオーケストラが切れ目なく続き、歌手達の二重唱、三重唱が多く、時には舞台上で動物が鳴き、大勢が動き回る。数回の公演テープの中から編集に使用する箇所を探すだけでも大変だった。でも、美しい音楽・サウンドに浸れることで辛さは吹き飛んだ。 日本コロムビアのPCM録音機は1972年当初から4チャンネルの入出力を備えていたため(正確には3号機までは8チャンネルを備えていたが、クラシック録音では4チャンネルで使っていた)今回はオーケストラの音を1,2チャンネルに、舞台の音を3,4チャンネルに別々に録音していた。 編集完了後、録音スタッフより「実際のオペラ公演では手前のピットにオーケストラがいて、奥に舞台がある。しかし、これまでの録音ではオーケストラのマイクと舞台のマイクが捉えた音に時間差が無いために舞台の音が実際の距離・時間よりも僅かだが早く到達し、あたかもオーケストラと同列にいるかのように聞こえてしまう。でも、今回は舞台の(3,4チャンネル)の音をデジタル技術を用いてオーケストラ・ピットの奥行(数メートル)分遅らせることで、マイクの相互干渉による歪を減らし、より澄んだ、奥行き感のある再生ができる」との提案があった。 では、実際にオーケストラのマイクと舞台のマイクの時間差はどれくらいなのか?答えは「魔弾の射手」が簡単に出してくれた。舞台上で鉄砲を撃つ場面が度々あるので、その銃撃音の時間差を調べればよかった。実際、デジタル遅延装置で時間差をつけた「魔弾の射手」は手前にオーケストラ、奥に舞台が拡がり、これまでにない透明感・臨場感が感じられたことから、2チャンネル・マスターテープはこの方式で作られた。 しかし、「ばらの騎士」ではこの方程式は通用しなかった。「魔弾」と同じマイク配置のはずだが、同じ時間差をつけると何か不自然に聴こえてしまうのだ。当時その原因は不明だったが、おそらく「魔弾」と比べるとはるかに使用楽器数や演奏者が多く、ピット内は人と楽器で溢れ、様々な場所から音が鳴っているのでマイク相互の到達時間差も複雑だったことが考えられる。 2月末に現地で行われたマスターテープの試聴会で両方の編集が承認されると、国内、海外盤共に超特急で各パーツ(レコード、CD、解説書、収納ケース)の製造が行われ、「魔弾の射手」は録音後2か月半未満の4月21日、「ばらの騎士」は翌5月21日に国内盤が発売されている。 「魔弾」を指揮したハウシルト、「ばら」を指揮したフォンク、共に歌劇場の指揮者としてうまく統率していたが、名盤と比較されるレコードの世界では無名の彼等の演奏に厳しい批評が多かった。なかでも「ばらの騎士」は前年に名歌手を揃え、ウィーン・フィルを用いたセッション録音の究極ともいえるカラヤン盤が登場した後だけに国内のセールスは伸びなかった。 演奏はともかく、一ヶ月以上に渡るマイク位置探しの努力とデジタル遅延補正を用いることで現れる透明感・奥行き感は、同時期に開始されたフランクフルト・アルテオーパーでのインバル/マーラー:交響曲全集の録音で結実する。高橋は交響曲第4番の録音でメインマイクの最適位置を探し出し、ワンポイント録音の神話を作り出す。また遅延補正技術は交響曲第6番以降のマスターテープ作成に導入されてゆく。 今日ではマルチトラック録音機能を備えたパソコンに各マイク出力を接続し、トラック毎に波形を見ながら簡単に時間差をつけられ、歪が減らせる。あの当時できなかったことがクラシック録音技術のひとつとして当然のように行われる時代になった。 個人的にはクライバーによるR・シュトラウスの名演を聴いた後に抱いた「いつかこのオペラを」という夢が、編集という形で叶ったことは望外の喜びだった。 差し出したあの楽譜は録音と編集で多くの書き込みがなされ、ボロボロになった。カラヤンのCDは現地で何回も試聴されたのだろうか、盤面は傷つき、ケースは無くなって戻ってきた。楽譜はその後新品と交換されたが、CDはいまも音飛びして満足に聴けないままである。 (久) |
|||
|
|||
[この一枚] インデックスへ |
|||