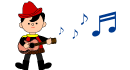[この一枚 No.81]〜バッティストーニ:イタリア・オペラ管弦楽・合唱名曲集〜
| 「オペラ大好き」、「フォルツァ・イタリア!」など、イタリアにちなんだクラシックの名曲を集めたアルバム(コンピレーション・アルバムと呼ばれるが)を企画するとき、いつも困っていたのが日本コロムビアの自主音源や海外の契約レーベル音源の中に、このアルバムの中に必ず組み入れなければならない「アイーダの凱旋行進曲」などのキー曲が無いことだった。やむなく他社から音源使用料を払って音源を借りると制作原価が上がり、アルバムの収益性が悪くなることからしばしば企画が没となった。 今回、バッティストーニ指揮カルロ・フェリーチェ歌劇場管弦楽団&合唱団の新録音「イタリア・オペラ管弦楽・合唱名曲集」のCDを手にしたときの感想は「まさか、よく、こんな曲をイタリアのオペラハウスで録音できたな!しかも自主録音で、よくやった!!」という驚きだった。 イタリアの音楽家たちは、「先に口からうまれてきたのでは?」と言われるほどよく喋る。良く言えば、個性豊かだが、悪く言えばまとまりが無く、バラバラとなる。昔イタリアの巨匠フェリーニで「オーケストラ・リハーサル」という映画があった。オーケストラメンバーが指揮者の言うことを聞かず、好き勝手な振る舞いをするが、ある事件をきっかけにまとまり、素晴らしいオーケストラ・サウンドを奏でる、というものだった。 1991年パドヴァで似た経験をした。ペーター・マーク指揮パドヴァ・エ・ヴェネト室内管弦楽団のモーツァルト:《救われたベトゥーリア》の録音に立ち会ったときのことだ。正確には録音を委託したイタリアの録音エンジニアより「B&Kマイクを貸してくれないか?」という要請があり、急遽デュッセルドルフからパドヴァまでマイクを運び、使い方を教えたという次第である。録音はパドヴァの大広間で行われたが、音楽が止むと、すかさずあちこちでお喋りが始まるので、指揮者は何回も指揮棒を叩いて注意を促し、メッセージを伝えていた。 録音馴れしている団体でもこうだ。まして、ライヴ録音でなく、セッション録音に馴れていない(ライヴでは音楽の乗りが大切だが、セッションでは音楽の縦の線をきちっと合わせることが求められる)歌劇場のオーケストラや合唱団が相手では、指揮者も、制作担当の馬場ディレクターも大変な苦労があっただろうと想像できる。しかし、仕上がった演奏はどれも伸びやかで、地中海の明るさが聴こえてくるようだ。 このアルバムを更に魅力的にしているのはオーケストラと合唱が一体となって繰り広げる、迫力がありながら歪感が感じられないサウンドの録音だ。 2014年8月のこのコラムで1985年ドレスデン、ゼンパーオペラ《魔弾の射手》のライヴ録音で用いられたマイク間の時間差を補正するデジタル遅延補正技術のことを取り上げたが、その後、デジタル録音技術とパソコンの発展により、さらに高度に進化していった。 2008年のレコードアカデミー賞に輝いた田部京子とカルミナ四重奏団によるシューベルト:ピアノ五重奏曲《鱒》の録音エンジニアは今回のアルバムの録音も担当した塩澤である。発売当時、担当ディレクターの国崎が呟いた一言が印象的だった。「編集を終えた演奏を聴きながら塩澤がパソコンを操作していると、突然澄んだ響きの世界が現れたのです。遅延補正技術は凄いですね。」 勿論だが、塩澤によるマイクロフォン・セッティングや録音技術が優れているからこそ最後の遅延補正がより生きてくるのである。 今回の「イタリア・オペラ管弦楽・合唱名曲集」の録音会場となったイタリア、ジェノヴァのカルロ・フェリーチェ歌劇場は塩澤にとって初めての録音会場であるが、初めての会場はなにかと心配事が多い。 たとえば、会場の響きは良いか、悪いか、響き過ぎないか、響かないか、癖のある響きや嫌な反響、残響は無いか、外部からの騒音は無いか、内部でノイズを発生するもの(軋む楽団員用の椅子や譜面台、山台)は無いか、モニタールームはステージまで遠いか、モニタールームの広さは、変な響きは無いか、 電圧は安定しているか、電気信号系にノイズが乗ることは無いか。今回のようにコンサートも同時に行われる場合、コンサート中はメイン・マイクは天井から吊らなければならない。吊りマイクの設備はあるか、あっても目指すマイク位置に可動できるか、吊りマイクの設備が無ければ、天井からマイクを吊り下げられるか、そのマイクケーブルの長さはどれほどか、日本ならば気心の知れたスタッフ数人で手分けして準備に取り掛かれるが、はるかイタリア、ジェノヴァでは日本語と録音機材を解るスタッフを調達することは不可能だ。そこで、今回は元ドイツの録音チームの一員で、日本語が堪能なベッツに参加を要請した。 ベッツは、当時担当した一連のアファナシェフのピアノやラ・ストラヴァガンツァ、ウィーン室内合奏団などの録音を聴けばお分かりいただけるが、塩澤と同様、澄んだ響きの録音を行っている。 迫力があって、しかも音が濁らない録音とは?具体的にはアルバム2曲目の歌劇《ナブッコ》より「行け、我が想いよ・・」とか、9曲目歌劇《マクベス》より「虐げられた祖国よ!」、10曲目の歌劇《アイーダ》より凱旋の合唱を聴いて頂ければお解り頂けるだろう。 オーケストラに合唱が加わると、歌われる言葉を明瞭に捉えるため合唱団の前に立てられたマイクにオーケストラの音が廻り込み、また、オーケストラのマイクに合唱が廻り込むので、それらのマイク信号を単純に混ぜてしまうと、相互のマイクに漏れた音が干渉しあって混濁した響きとなってしまう。混濁を避けるために合唱のマイクレベルを絞ると言葉の明瞭度が失われ、迫力ある合唱が聴こえてこない。ここが録音技術者の腕の見せどころであり、塩澤は手前に弦楽器の厚い音を、木管、金管、打楽器の奥に明瞭で力強い合唱を響かせて、迫力あるサウンドステージを繰り広げている。 全編が素晴らしいのだが、個人的には、歌劇《ウィリアム・テル》序曲、最終部分のトライアングルの澄んだ響きのバランスがとても音楽的で、大好きなサウンドである。 これは昨年、第21回プロ音楽録音賞最優秀賞を「レスピーギ:ローマ三部作」で受賞した塩澤の技術・実力が遺憾無く発揮されたアルバムと言えるだろう。 このアルバムを一聴後、馬場ディレクターにアルバム制作への労いと感謝の感想を伝えた後、「ジェノヴァ近郊のポルトフィーノに行った?」とメールで尋ねてみた。返事は「残念ながら」であった。 ポルトフィーノは東京ディズニーシーの入口を潜ったところに佇む入江ポルト・パラデイーゾのモデルになった、今回の録音地から南東に40kmの所にある小さな美しい港町である。 20年以上前、ヨーロッパの知人に「1週間休みが取れたら、スケッチブックを携えてこの港町に行くといいよ」と薦められたがまだ実現していない、私の夢の場所である。 (久) |
|||
|
|||
[この一枚] インデックスへ |
|||