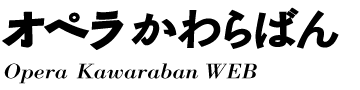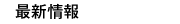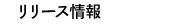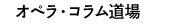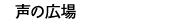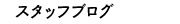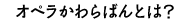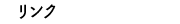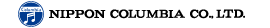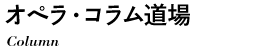連載内容
「レコード芸術」などで活躍する気鋭の評論家、広瀬大介さんが、オペラに登場する日の当たりにくい脇役になりきり、そのオペラの魅力と鑑賞のツボを押さえた作品解説、対象映像の演出について語る、世にも不思議ななりきり一人称ガイド。
これぞ自己言及のパラドックス!ねじれの向こうに真実がみえる!
プロフィール

広瀬大介
1973年生。一橋大学大学院言語社会研究科・博士後期課程修了。博士(学術)。著書に『リヒャルト・シュトラウス:自画像としてのオペラ』(アルテスパブリッシング、2009年)、『レコード芸術』誌寄稿のほか、NHKラジオ出演、CDライナーノーツ、オペラDVD対訳、演奏会曲目解説などへの寄稿多数。
Twitter ID: @dhirose
最近、無味乾燥な歴史書の代表格『徳川実記』に現代語訳が登場しはじめ、うれしさを噛みしめつつも、昔苦労して読んだのは何だったのか、と一抹の寂しさも感じているところ。好きな食べ物は相変わらず甘いチョコと甘い梅酒。

第9回 《エフゲニー・オネーギン》オリガがひとり紐解く、グレーミン公爵の日記
《エフゲニー・オネーギン》とは
ロシア近代文学の祖、アレクサンドル・プーシキン(1799-1837)。急進的な文学理論と、巧みに口語を取り入れた作風は、後のロシア文化の形成に多大な影響を与えた。この《エフゲニー・オネーギン》のみならず、《ルスランとリュドミラ》(グリンカ)、《ボリス・ゴドゥノフ》(ムソルグスキー)、《金鶏》(リムスキー=コルサコフ)、《スペードの女王》(チャイコフスキー)など、多くの作品がオペラ化されている。妻に言い寄るフランス人と決闘に及び、命を落としてしまうところなど、プーシキンの最期はこの作品の一方の主人公、レンスキーそのままであった。名作オペラ《ボリス・ゴドゥノフ》への対抗意識も剥き出しに生み出された《エフゲニー・オネーギン》(1879年初演)。交響曲とバレエが突出して名高いピョートル・イリイチ・チャイコフスキー(1840-1893)だが、この時期はまだあまりオペラの作曲に慣れていなかったというのがもっぱらの世評。とはいえ、ドビュッシー《ペレアスとメリザンド》と並ぶ叙情的オペラの代表作として、日本でも近年とみに上演回数が増えている。
レンスキーの悲劇的な死から十数年。オリガは新たな恋人と結婚し、それなりに幸せな生活を送っている。姉タチヤナは、老公爵グレーミンと結婚し、満たされた日々を送っていた。グレーミンに余生はあまり残されておらず、結婚数年後に死去。タチヤナは早くも寡婦となってしまった。姉と他愛ないお喋りをするべく、冬の凍てつく空気の中、オリガはタチヤナの元を訪れたが、姉は外出中とのことで、つかのま客間で待たされることになる。
オリガ(以下O): お姉様ってば、相変わらず素敵なおうちにお住まいね。公爵夫人ともなれば、いいうちなのは当たり前か。貴族の爵位については、《ローエングリン》の稿も参照のこと。公爵は一番偉い貴族である。うちの旦那とは大違いだわ…。イイ人なんだけど、つまんない男と結婚しちゃったのかもね。今更後悔してもしょうがないけど。
 明るく快活なタチヤナの妹オリガ。昔の彼氏レンスキーの非業の死も、いまでは気丈に乗り越えたようだが…?
明るく快活なタチヤナの妹オリガ。昔の彼氏レンスキーの非業の死も、いまでは気丈に乗り越えたようだが…?
 読書大好きなヒロイン、タチヤナ
読書大好きなヒロイン、タチヤナ
召使いがロシアン・ティーを運んでくる。溶かしきれないのでは、と心配になるほどのジャムをカップに入れ、何かに思い詰めたようにスプーンでかき回し続けるオリガ。その目は空間の一点を見詰めている。
O: …。壁には本、本、本ばっかり。お姉様は、昔から本ばっかり読んでたわ。未亡人になってから、ますます読書量に拍車がかかってるようね。あんな活字の世界ばかりに浸って、何が楽しいのかしら。私なんか、本なんか読んでも、頭が痛くなるだけ。まあ、お姉様はあまり身体が強くなかったし、私が振り回してばかりいたから、あんな性格になったのかもしれないけど。あーあ、外もしんしんと冷えてきてるみたいだし、早く帰ってこないかしら。
甘すぎるロシアン・ティーをこともなげに飲み干し、ため息をつく。ふと本棚の一点に目を遣るオリガ。
O: …。あの本だけ、何だか妙に小さいわね。他の本は全部大きさが揃ってるのに。色もくすんでるし、サイズも小さいし、何なのかしら?
椅子から物憂げに立ち上がり、本棚に近づき、小ぶりの本を手にとる。
O: 題名も書いてないわ。あら、活字じゃないのね。細かい字でびっしりと何か書いてある。これは日記みたい。もしかして、亡くなったグレーミン公爵様のものかしら。以前頂いたお手紙と筆跡がよく似てるわ。
辺りを見回し、急にそわそわし始める。
O: のぞき見するのはあまりお行儀がよくないけど、何が書いてあるか、気になるわ…。お姉様が帰ってくるまでにはまだ間があるみたいだし、ちょっとくらいなら読ませてもらってもいいわよね。帰ってきたら、ここに戻しておけばいいんですもの。そうよ、それならわかりはしないわ。
初めの数ページに目を通すオリガ。
 タチヤナをものにした初老の公爵グレーミン。タチヤナとの年齢差はかなりのものだが、オペラ中で「恋に年齢など関係ない」と熱唱する
タチヤナをものにした初老の公爵グレーミン。タチヤナとの年齢差はかなりのものだが、オペラ中で「恋に年齢など関係ない」と熱唱する
O: 戦場での話かしら…。軍務の話は、私にはさっぱり。確か公爵様は、戦場で大けがを負われたのよね。その功によって、叙爵されたってお姉様が言ってた。復員後にお見合いで知り合われ、ご結婚されたとか。なんだか、どこもかしこも、ずいぶんと書き方が素っ気無いわね。まるで報告書みたい。この軍務のお話は、結婚する前の話なのかしら。「タチヤナより便りあり。返事をしたためる」なんて書いてある。昔から、お姉様は手紙をよく書いてたわね。手紙と言えば細馬さん。是非彼のエッセイもお読みください。って、それもそうなんですが、もとい、手紙と言えば、何と言っても「タチヤナの手紙の場」(強引)。手紙の場に頻出する、四つの音から成るホルンの動機(ヘ→変ロ→変イ→変ニ)が、恋に高鳴る乙女の心の期待と戸惑いと憂鬱と…、とにかく、チャイコフスキーはこの四つの音に、その手の思春期特有の酸っぱい思いをめいっぱい閉じ込めたのである。このタチヤナを描く調とされたのが変ニ長調。チャイコフスキー先生も、ご自身が奥様と結婚される時の経験を、えっ、チャイコフスキーって同性愛者じゃなかったの、という人、いるでしょう?実は彼、一度、アントニーナ・ミリューコヴァという自分のファン(ストーカーとも言う)と結婚しているのです。たった数週間でしたが。タチヤナの描写に反映させたみたいだし。ご結婚の時の様子もずいぶん簡単ね。あら、ご結婚後に招待された、夜会のときのお話もあるわ…。ここはずいぶん詳しく書いてある。まあ、冒頭に「心千々に乱れる一日」なんて書いてあるわ。どういうことかしら…。
グレーミンの日記
「○月×日。心千々に乱れる一日。某伯爵宅での舞踏会に出席。妻を伴う。千客万来。旧友エフゲニー・オネーギンに再会。数年外国にいたとのことだが、不自然なまでにやつれ、顔色がよくない。それでも、自分の前で快活さを装おうとするのが痛々しい。同席していた知り合いに聞いた話では、オネーギンが外国にいたのは、ちょっとした諍いで親友の詩人ウラジーミル・レンスキーと口論、決闘に追い込まれ、殺す気などなかったその男を手にかけてしまったからだと言う。良心の呵責に苛まれ、世間の目を気にして、ロシアを離れたのだろう。22歳の若さで、痛ましいことではある。」
 オリガの彼氏、レンスキー
オリガの彼氏、レンスキー
それを読むオリガの顔が見る間に曇る。触れられたくない過去をものの見事に刳られたためか、冷や汗をかき、呼吸が浅くなる。
O: 何なの? ウラジーミルのこと、何で公爵様はここまで知ってたのよ! 私の前ではそんなそぶりなんか一度も見せなかったくせに! きっとお喋りなお母様が、全部しゃべったからに違いないわ。もう忘れたかったのに、また思い出しちゃったわ…。あの人、すぐにヤキモチをやいて、ねっとりした目で私を見回すの。でも、詩人なんて身の回りにいなかったから、あの人の妙な存在感にほだされちゃったのよね。今思えば、若かったわ。
それでもグレーミンの日記を読むことはやめられない。迷いを振り払うように2杯目の紅茶にジャムをタップリ入れ、それをすすりながら続きに目を通すオリガ。文字を読み慣れぬせいか、その読みっぷりはどこかたどたどしく、速度も遅い。
グレーミンの日記
「無理をして快活に振る舞おうとするオネーギンの様子が、妻を紹介するに及んで、いよいよおかしい。妻とは幼なじみだったようだが、その妻を目にしたときのオネーギンの動揺はただ事ではない。明らかに正気を失っていたオネーギンに周りの視線が集まりはじめていた。私はとっさに年寄りじみた訓戒をオネーギンに与える振りをしつつ、妻への切々たる愛情を訴えることで、おなじみ、第3幕第1場の公爵のアリア「恋には歳など関係ない」。有節形式による素朴な歌曲といった趣で、ここで一旦劇の進行が止まる、純然たるアリア。だが、その調性はフラットが6つもつく変ト長調。分別くささ、年寄り臭さ(失礼)を描こうとしたのだろう。オネーギンを牽制した。」
O: お姉様は、確かオネーギン様がお好きだったのよね…。あの方に初めてお目にかかったとき、お姉様は16歳。私はほんの子供だったわ…。
グレーミンの日記
「妻とオネーギンの間には何かがあった、と、私は直感した。だが、それを今更蒸し返すのは憚られた。妻の過去を詮索することなど、どれほどの甲斐もない。だが、この弱い心に巣食った不安は、消えるどころかますます大きくなる。気がつくと、私は隣室から妻の様子をうかがっていた。戦場の英雄たるグレーミンが、いまや妻の後を追いかけ、息を殺してその一言一句を聞きのがすまいと、物陰で必死になっている。」
O: 何だかシェークスピアの悲劇みたいね。何のお話だったかは忘れちゃったけど…。オリガさんの代わりに思い出して差し上げましょう。それは、イヤーゴの奸計にはまり、ありもしないデズデモナの不貞を疑うオテロのことだと思われます。プーシキンは、シェークスピアもよく読み込んでいたそうですよ。もっとも、このグレーミンさんの振る舞いについては、プーシキンさんも描いていませんでしたけどね。
グレーミンの日記
「別室のサロンで妻は腰掛け、手紙のようなものに目を通し、それを握りしめ、涙さえ浮かべている。オネーギンからの手紙でも読んでいるのか。やがて、オネーギンが情熱的にサロンへと飛び込み、妻に何事かを訴える。隣の部屋から様子をうかがうだけで、何をしゃべっていたのかまではわからない。だが、二人は取り乱し、涙を流し、抱擁し、そして最後に妻はオネーギンを突き放す。何かに引き裂かれるかのような悲壮な面持ちで、妻はその場を後にした。慟哭し、その場に崩れ落ちるオネーギン。私は、二人の愛の終焉を、この目で見てしまったのだ。このオペラにおいて、恋の成就はホ長調、恋の破局はホ短調で描かれている。この調性が選ばれたのは、ワーグナーが《タンホイザー》や《ローエングリン》でホ長調を愛の調性として用いたことに影響を受けたのだろう。というわけで、全曲の終結は、当然ホ短調である。ワーグナーには一貫して距離のある態度をとり続けていたチャイコフスキーだが、その作劇法はいろいろと研究していたのだ。見なければ心安らかに暮らせたものを。」
O: …心千々に乱れる一日、というのは、こう言うことだったのね。お姉様も辛かったでしょうけど、公爵様はもっとお辛かったのね…。
グレーミンの日記
「妻が貞節を守ったことには満足したが、その代償に彼女が失ったものは、どれだけの大きさか。その日の妻は、努めて快活にしているように見えた。私への気配りも、いつも以上に欠かさない。改めて、自分との生活以外のことを考えないようにしているようなそぶりだった。いまだ20歳になるかならぬか、という妻の献身ぶりを見るにつけ、妻への愛情を新たにはするものの、これからどれだけの春秋を妻と共に暮らせるのか、自分に残された時間の短さに思いを致さずにはいられない。」
グレーミンの深い思いに打たれ、3杯目のロシアン・ティーが冷めてしまうのにも気づかず、しばらく無言でページを繰り続けるオリガ。やがて、途中で日記が中断しているのに気がつく。筆跡も乱れた最後のページの日付は、グレーミンが心臓発作で倒れる前日だった。
グレーミンの日記
「○月×日。朝から調子が悪い。動悸が激しく、息も苦しい。心臓が悲鳴を上げているのだろう。軍人として戦場で死ぬことができぬのは心残りだが、晩年に与えられた心安らかなる日々に対し、心からの感謝を神に捧げる。夕食はほとんど口にできず。甲斐甲斐しく働く妻に、これまでの感謝の気持ちをそれとなく伝えるが、『まるで遺言みたいな仰りよう』と、いっかな取り合わない。そう、妻よ、その感謝の言葉は、我が遺言なのだ。おそらく自分の死後、妻は私の書斎机からこの日記を見つけ、そして紐解くことだろう。私が彼女の心の全てを知っていたにもかかわらず、それを口外することなく、従容と死についたことに、妻は涙を流してくれるだろうか。それとも、このような日記を見ようとも、所詮は老人の繰り言と一笑に付すだろうか。祖国の英雄として祭り上げられた晩年ではあったが、それは敵の血をもって購った、血塗られた栄光に過ぎない。老いてから得た妻は、これまでの自分の苦労に対する報いかとも考えたが、彼女が意に染まぬ結婚を強いられたのだとすれば、私は自分のささやかな満足のために、一人の女性の運命を弄(もてあそ)んだことになる。私が妻にその代償として残してやれるのは、公爵夫人としての地位と財産くらいのもの。妻よ、おまえの若き青春の日々、そして純真な愛を奪ってしまったこの老人を、どうか許してほしい。そして、レンスキーとも結ばれなかったオリガともども、男の身勝手に振り回されたラーリナ家の姉妹に、末永く神の恩寵のあらんことを。」
滂沱の涙と共に日記を読み終えたオリガ。しばし呆然としたまま、その場を動けない。突如、何かにはじかれたように立ち上がり、部屋にある鏡の前に立って、自分の顔を眺める。
O: ああ、もう、こんなグジャグジャな顔になってしまったわ。勘のいいお姉様のこと、このままお目にかかったら、きっと私があの日記を盗み読みしたことがバレるに違いないわ。
オリガは慎重に日記を本棚に戻す。だが、それは元の場所とは全く別のところだった。ストールを身にまとい、そそくさと客間を離れる。
召使: おや、オリガ様、お帰りでございますか? 奥様はもうすぐお戻りと存じますが、もう少しお待ちになられては?
O: もういいの。ちょっと用事を思い出しちゃって。ロシアン・ティーのジャムは、もっと甘い方がおいしいわよ。ああそうだ、お姉様に伝えといてちょうだい。素敵な男性に巡り会えて、幸せだったわね、って。
召使: は? 「素敵な男性」と仰いますと、亡くなられた公爵様のことで?
O: お姉様がそうだと思うなら、きっとそうよ。じゃ、またね。
召使: はあ…。
第9回・了
このオペラが観たくなったら…

チャイコフスキー 歌劇《エフゲニー・オネーギン》
ボリショイ劇場 2000
■キャスト&スタッフ
イリーナ・ウダローワ
マリヤ・ガヴリーロワ
エレーナ・ノヴァーク
ガリーナ・ボリーソワ
ウラジーミル・レトキン
ニコライ・バースコフ
演出:ボリス・ポクロフスキー
指揮:マルク・エルムレル
ボリショイ劇場管弦楽団
■収録
2000年10月18日、ボリショイ劇場(モスクワ)
■SPEC
- [収録時間] 156分
- [字幕] 日本語・ロシア語
- [映像] 4:3 カラー
- [音声] リニアPCMステレオ/Dolby Digital5.1/DTS5.1
- [ディスク仕様] 片面2層+片面1層(2枚組)
- DVD●TDBA-81260~1 3,570円(税込)