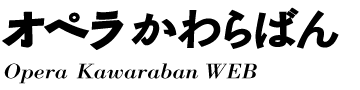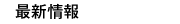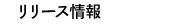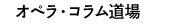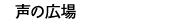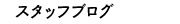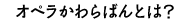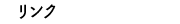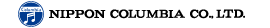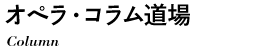連載内容
「レコード芸術」などで活躍する気鋭の評論家、広瀬大介さんが、オペラに登場する日の当たりにくい脇役になりきり、そのオペラの魅力と鑑賞のツボを押さえた作品解説、対象映像の演出について語る、世にも不思議ななりきり一人称ガイド。
これぞ自己言及のパラドックス!ねじれの向こうに真実がみえる!
プロフィール

広瀬大介
1973年生。一橋大学大学院言語社会研究科・博士後期課程修了。博士(学術)。著書に『リヒャルト・シュトラウス:自画像としてのオペラ』(アルテスパブリッシング、2009年)、『レコード芸術』誌寄稿のほか、NHKラジオ出演、CDライナーノーツ、オペラDVD対訳、演奏会曲目解説などへの寄稿多数。
Twitter ID: @dhirose
最近、無味乾燥な歴史書の代表格『徳川実記』に現代語訳が登場しはじめ、うれしさを噛みしめつつも、昔苦労して読んだのは何だったのか、と一抹の寂しさも感じているところ。好きな食べ物は相変わらず甘いチョコと甘い梅酒。

第10回 《運命の力》至るところ、罪深い、罪深い…
《運命の力》とは
1860年、ジュゼッペ・ヴェルディは、イタリア統一の立役者にして初代首相となったカミッロ・カヴールの願いを聞き入れ、上院議員の職を引き受ける。翌年カヴールが死んでしまうとほとんど国会には行かなくなってしまうが、単なる作曲家と言うだけでなく、イタリア統一の象徴的存在として重きを置く存在になっていった。一方で、長年ともに暮らしてきたジュゼッピーナ・ストレッポーニとも、59年にはついに結婚。作曲家として大成功を収め、祖国統一の象徴的存在となり、泥沼のような恋愛からも解放されて安らかな家庭を持ち、さて俺はこれからどうする…、人生の目的を見失っているのではないか、と己を顧みはじめた頃、ロシア宮廷から委嘱を受けて書かれ、62年に初演されたのが、この《運命の力》。どうやらそのときに上演された「オリジナル版」と、69年にミラノでの上演用に変更が加えられ、現在専ら上演されている「改訂版」では、かなりの違いがあるようで…。
マドンナ・デリ・アンジェリ(天使の聖母)教会の前庭。フランチェスコ会の修道士が集うこの修道院で、あの凄惨な事件が起きてから、1年と少しが過ぎている。修道士メリトーネは今日も貧者にスープを頒け与える。慎みを知らぬ貧者相手に苛立つばかりの仕事は、メリトーネにとって気が進まない。スープを配り終わり、やや不機嫌なメリトーネ。まだ夕方の晩禱には間があるのか、手許にある本をパラパラとめくりながら、そのまま前庭に咲き乱れる花をボーッと眺めている。
 貧者たちに施しをするも、その厚かましさにお玉を振り回して怒るメリトーネ「あーもー、これだから嫌なんだよ!!」
貧者たちに施しをするも、その厚かましさにお玉を振り回して怒るメリトーネ「あーもー、これだから嫌なんだよ!!」
 駆け落ちをすることになっていた夜のレオノーラとドン・アルヴァーロ。レオノーラ:「このオペラで綺麗な服を着られるの、ここだけなのよね…」
駆け落ちをすることになっていた夜のレオノーラとドン・アルヴァーロ。レオノーラ:「このオペラで綺麗な服を着られるの、ここだけなのよね…」
メリトーネ(以下M): …それにしても、なんと罰当たりな本を買ってしまったものか。世俗とは完全に縁を切ったつもりだったのに、あの事件の顛末が忘れられないばっかりに、つい買ってしまうとは。おお神よ、弱いこの心を何卒お許し下さい。『ドン・アルヴァーロ、または運命の力』。著者:リヴァス 公爵アンヘル・デ・サーヴェドラ、か。わが目の前で起きたあの凄惨極まる出来事が、早くもこうして戯曲になってしまうとは、まったく世も末だ…。あらすじがついているのか。なになに、主人公ドン・アルヴァーロは、スペイン人のインカ総督とインカ帝国 皇帝との間に生まれた嫡子ながら、インカ帝国の没落に伴い本国へ戻る。侯爵家カラトラーヴァの姫レオノーラと道ならぬ恋に墜ち、駆け落ちを決意するも、それを見咎めた父親を、ピストルの暴発によって誤って殺してしまう。以後、二人は生き別れ、兄は父の仇として二人を付け狙う、か…。
修道院長・グァルディアーノ神父が二人の修道士を供に従えて戻ってくる。遠くからメリトーネの姿をみとめた修道院長は、供の二人を先に帰し、物陰からメリトーネの様子を窺う。メリトーネは手許の本にしばらく目を落としている。
M: 結局、レオノーラとドン・アルヴァーロの二人は互いがこの修道院にいるとは知らず、彼らを追ってきた兄ドン・カルロは、ドン・アルヴァーロに返り討ちにされるも、駆け寄ってきた妹を、最後の力を振り絞って刺してしまったからな…。思い出すだにおぞましい現場を見てしまった後、一ヶ月はまともな精神状態に戻れなかったものだ。あの事件から一年と三ヶ月くらいは経っているか。一年三ヶ月と言えば、このコラムの筆者が前回の《エフゲニー・オネーギン》を書いてからすっかり音沙汰なくなった期間と、全く一緒か。久々に書く「なりきり」だから、筆者もすっかり書き方のコツを忘れて、冗長なあらすじから書き始めているようだし。まったく情けない話だ。このような信心薄い筆者には、そのうち天罰が下るはず。それにしても、このリヴァス公の話、私の目の前で起きた事件とは随分違うように見受けられるが、いったいどういうことなのだ。そもそも、この本に出てくるドン・アルフォンソとは何者だ。ドン・アルフォンソといえば《コジ・ファン・トゥッテ》若いフェルランドとグリエルモをけしかけ、恋人の貞操をネタに賭けようともちかける、かなり罪深いオヤジ…、であることは、このコラムを読む方はご存じですね、ハイ。しか知らないな。あのときここにやってきて、ドン・アルヴァーロに返り討ちに遭い、いまわの際にレオノーラを刺し殺したあの男は、確かドン・カルロと名乗っていったはずだが。
修道院長(以下G): その男は、ドン・カルロの弟だったのだ。
M: うわっっっ! 院長、いつお帰りで? ドン・カルロには弟がいた? 何がなにやらサッパリわかりませぬ。
 いつも冷静だが、メリトーネにはちょっと手を焼いている修道院長
「アルヴァーロもレオノーラもここに逃げ込むとは。
二人を逢わせぬようにするのは、気骨が折れる」
いつも冷静だが、メリトーネにはちょっと手を焼いている修道院長
「アルヴァーロもレオノーラもここに逃げ込むとは。
二人を逢わせぬようにするのは、気骨が折れる」
G: はっはっは。これほど錯綜した話もないからな。ちゃんと貧者に施しを終わらせたのなら、説明してやろう。お前がその手許に持っている原作では、父親カラトラーヴァ侯爵には二人の息子がいることになっている。兄がドン・カルロ、弟がドン・アルフォンソ。だが、ヴェルディ先生は、この二人をドン・カルロというひとりの人格にまとめてしまったのだ。
M: なぜそんなことを? 二人ともオペラに出せば良いではありませぬか。
G: おそらく話がややこしくなりすぎる、ということと、似たようなバリトンを二人出すことによって劇的効果が弱まるとか、劇場の経済的負担とか、いろいろなことを考えられたのであろうな。
M: 院長、なにやら聖職者には似合わぬ世俗的なおもんぱかりを見せられますなあ。
G: 何しろ原作でのドン・カルロは、第3幕、戦場でその素性を知ったドン・アルヴァーロと決闘して、その場で殺されてしまうのだから。
M: なんと。それは存じませんでした。ドン・アルヴァーロがラファエーレと名を偽ってこの修道院にやってきて、俗世を棄てたいという理由がいまいちわからなかったのです。もし戦場ですでに恋人の兄を殺してしまっている、とするならば、何となく話のつじつまは合いますなあ。オペラ版だと、その辺の事情がすっ飛ばされてしまうので、いまいちわかりづらいのか。それまでのヴェルディ先生のオペラと違って、惚れたはれたがあまりないのは、そのテのことにもはや縁のない私のような聖職者にとっても、華のない話で。
G: だからこそ、ヴェルディ先生は、お前のような役を作ったのだ。
M: へ、私を?
G: お前の役、配役表には何と書いてある?
M: ああ、そういえば…、確か「バリトン・ブリランテ Bariton Brillante」と書いてあったような。そんな声域の区分け、はじめて聞きました。ブリランテとは「華やかに」とか「輝かしく」とかいう意味ですかね? いや、照れるなあ、確かに脇役にしては結構な活躍ぶりですが、いやいやそれほどでも。
G: 何を言っているのだ。もとの意味はそうだが、永竹由幸『ヴェルディのオペラ:全曲の魅力を探る』音楽之友社 362頁。先生によると、ここでは「喜劇的」という意味で用いられているようだ。本人は真面目にやっているのに、他人から見ると少々滑稽という役回り、と言うわけだな。
M: なんだ、褒められているのやら、けなされているのやら…。
G: 逆に言うならば、お前にそういうコミカルな役回りを担ってもらわないと救いようのないほどの復讐譚だった、ということにもなるだろうな。
 占い女プレツィオシッラは、カルロの手相を見て…「学生さんとか言ってるけど、すぐバレルよ。
ちょっと老けすぎだもの」
占い女プレツィオシッラは、カルロの手相を見て…「学生さんとか言ってるけど、すぐバレルよ。
ちょっと老けすぎだもの」
M: コミカルと言えば、私のことを馬鹿にしたナントカとかいう占い女!ならばあの女も「ブリランテ」ということになるので?
G: プレツィオシッラのことか。彼女は普通のメゾソプラノとしか書いていないようだな。その割には三点Cを用いるアジリタ唱法agilita イタリア語で「敏捷」を指す名詞。転じて、敏捷な動きを必要とされる箇所を歌うコロラトゥーラ・ソプラノには必須のテクニックとされる。でも、この後、ヴェルディ先生はほとんどこの技法を必要とするオペラを作らなくなってしまうんですよねえ。もあったり、随分と難しい役のようだが。
M: 占い女といえば、ヴェルディ先生が直前に作曲された《仮面舞踏会》にもウルリカという名前の占い女がいましたなあ。あちらはいやにドスが効いていて、確か主人公の死を予言するんでは。
G: 占い女の予言は必ず当たるこの話、もうどこかでしましたね。《カルメン》のトランプ、《アラベラ》の占い女、オペラの占いは全部当たります。百発百中。、というのがオペラの鉄則だからな。こちらの占い女は大して予言らしい予言もせず、戦争を鼓舞する歌を歌うだけ。コロラトゥーラを駆使するその旋律は、《仮面舞踏会》で喩えるなら、ウルリカというよりはむしろオスカルのそれだろう。声域的には無理があるのでは、と思わざるを得ないの。
 突如として、厚い友情に燃えるアルヴァーロとカルロ。お互いのことよく知らないけど、友達大事!
突如として、厚い友情に燃えるアルヴァーロとカルロ。お互いのことよく知らないけど、友達大事!
M: でも、ところによっては、この後に作曲された《ドン・カルロ》を思わせるところもあったりして、なかなか愉しいですなあ。第3幕冒頭では、互いに名前を偽ったドン・アルヴァーロとドン・カルロが、友情の誓いを交わすところなどは、《ドン・カルロ》で、ドン・カルロとロドリーゴが歌う同じ友情の二重唱を思わせる…、って、ドン・カルロだらけで、何を言っているのか自分でもわからん!
G: 大丈夫、一応つじつまは合っているようだぞ。まあ、この作品が《仮面舞踏会》寄りの古いスタイルに属する作品なのか、《ドン・カルロ》寄りの未来を見据えた作品なのかは、それぞれに議論があるようだな。それまでのイタリア・オペラで盛んに使われていたカヴァティーナ・カバレッタ様式《椿姫》の第1幕最後、ヴィオレッタのアリアを思い出してみましょう。「不思議だわÈ strano!」と歌い始める前半のゆったりした部分がカヴァティーナ、その後で、「いつも自由の身でいるのSempre libera degg’io」(いわゆる「花から花へ」)と歌い始める、アップテンポな後半部分をカバレッタと呼びます。19世紀前半のイタリア・オペラは、この様式で作曲されるのが通例でした。から離れ、よりドラマと音楽が密接な結びつきを深めているんだがな。
M: 私なぞ、このオペラの音楽と言えば、あの序曲がやたら有名、ということしか思いつきませんがなあ。あの冒頭の三つの和音冒頭の三つの和音、いわゆる「ミ」Eの音で始まります。調号も♯一つ、ホ短調なのですが、その後しばらくは、なぜかイ短調で音楽が推移するというところは、ヴェルディの新工夫。やがてちゃんとホ短調に戻るんだけど、なんか変だなー、落ち着かないな-、という気分をわざと味合わせるよう、ヴェルディ先生が仕組まれたのでしょう。こそが《運命の力》を表しているのでしょう。実にカッコイイ!。
G: 何を言っておるのだ、あれはわれら聖職者の敬虔なる祈りを表すものだ、とヴェルディ先生自身が仰っておるのだぞ!
M: え、え、ホントに??
G: 楽譜をよく見てみろ。この金管が吹き鳴らす和音、フォルテはたったの一個だ。やたら強く吹き鳴らしては、それこそ戦争への雄叫びのようになってしまう。その含意は全くと言っていいほど正反対なのだぞ。
M: なんと、ヴェルディ先生はわれらカトリックに対して、敬虔な気持ちをお持ちであったとは、意外でございますな。
G: まあ、そうとは限らん。何しろ、ロシアで初演されたオリジナル版では、ドン・アルヴァーロはわれら聖職者に「大馬鹿野郎! Imbecille!」と叫び、「俺は地獄の使者だ、人類よ、滅びよ」と叫んで、自殺するのだから。
M: な、なんと罰当たりな! 涜神(とくしん)の言葉を吐き、さらに自殺を犯すとは!
G: この結末では、ロシアでは上演できても、カトリックの総本山イタリアでは難しかったであろう。改訂の直接のきっかけはこの言葉にあったと言われている。
M: ということは、オリジナル版では侯爵も、ドン・カルロも、レオノーラも、そしてドン・アルヴァーロまで、皆死んでしまうのですか。なんと救いのない筋書きであることよ…。
G: 主要な登場人物が皆死んでしまうオペラ《トスカ》とか、《ニーベルングの指環》とか、とか?は、たくさんあるようでいて、実はそれほど多くないからな。こうした、惚れたはれたがない題材を選んだ当時のヴェルディ先生の虚無感が、あちこちから透けて見えるようではないか。
M: そしてこの後は、愛する妻ストレッポーニがいるにもかかわらず、若いドイツ人歌手テレーザ・シュトルツとの不倫へと突き進み、その経験を反映させて、フィリッポ=ヴェルディ、エリザベッタ=ストレッポーニ、エボリ=シュトルツに擬(なぞら)えた《ドン・カルロ》が生まれるということなのですな。何にせよ、自らの生き様を作品に投影させないと、ヴェルディ先生は納得いく作品が作れなかったのでしょうなあ。われらにとっては、実に罪深い。罪深い。
G: さあ、祈ろう。むごい死を遂げたこのオペラの主役達に、そして罪深いながらも、人の心に永遠に残る旋律を生み出した、ヴェルディ先生その人に…。
第10回・了
このオペラが観たくなったら…

ヴェルディ:歌劇《運命の力》
フィレンツェ歌劇場2007年
■キャスト&スタッフ
ドンナ・レオノーラ:ヴィオレータ・ウルマーナドン・カルロ・ディ・ヴァルガス:カルロ・グエルフィ
ドン・アルヴァーロ:マルチェッロ・ジョルダーニ
プレツィオシッラ:ユリア・ゲルセワ
修道院長:ロベルト・スカンディウッツィ
メリトーネ神父:ブルーノ・デ・シモーネ
クルラ:アントネッラ・トレヴィサン
市長:フィリッポ・ポリネッリ
トラブーコ親方:カルロ・ボージ
外科医:アレッサンドロ・ルオンゴ 他
演出:ニコラ・ジョエル
再演監督:ティモ・シュリュッセル
装置:エツィオ・フリジェリオ
衣裳:フランカ・スクァルチャピーノ
照明:ユルゲン・ホフマン/ルチアーノ・ノヴェッリ
■収録
2007年、フィレンツェ歌劇場(テアトロ・コムナーレ)
■SPEC
- [収録時間] 180分
- [字幕] 日本語・イタリア語
- [映像] 16:9 カラー
- [音声] リニアPCMステレオ/Dolby Digital5.1/DTS5.1
- [ディスク仕様] 片面2層(2枚組)
- DVD●COBO-5984~5 8,190円(税込)