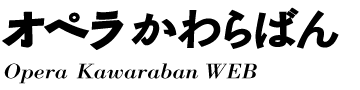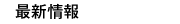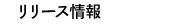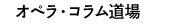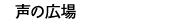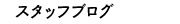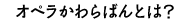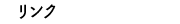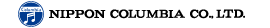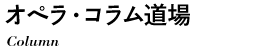連載内容
『絵はがきの時代』(青土社)の著者、細馬宏通さんのオペラ絵はがき連載。
細馬さんの所有するオペラ絵はがきコレクションをもとに、絵はがきの時代=図像交換の時代であり、さらにオペラ絵はがきがオペラをアイコンとして交換するメディアであったことを明らかにします。
初演当時の絵はがきから透かし見える時代精神!
プロフィール
 写真:渋谷博
写真:渋谷博
細馬宏通
1960年西宮市生まれ。滋賀県立大学人間文化学部教授。専門は会話とジェスチャーの分析、 19世紀以降の視聴覚メディア研究。著書に『絵はがきの時代』『浅草十二階』(いずれも青土社)など。バンド「かえる目」で作詞・作曲とボーカルを担当。
好きな音楽:中学生時代はブーレーズ指揮のドビュッシーとラベル、高校時代は荒井由実と矢野顕子、いまは物音から鼻歌まで。
好きな食べ物:ご飯と干物。

第6回 手紙は変装する
《セヴィリアの理髪師》の筋書きをすらすらと言えるオペラ・ファンというのはどれだけいるのだろう?
これほど有名なオペラであるにもかかわらず、脚本はひどく複雑で入り組んでいる。そう感じる人は多いらしく、世に流布しているあらすじにも、ひかえめに「紆余曲折」とあったり、あるいは露骨に「ドタバタ喜劇」などと書かれていたりする。
複雑さの原因ならば、すぐに思い当たる。そのひとつは、なんといっても主人公である伯爵の変幻自在ぶりだろう。伯爵は、身分を隠すためにリンドーロと名乗り、しかも騎兵の兵卒、音楽教師ドン・アロンソと、よせばいいのに変装に次ぐ変装を重ねて、物語を必要以上に複雑にしている。
 ロジーナの第二の手紙を疑う後見人バルトロ。下に書かれたフランス語は、「わたしのようなドクターに向かって」
ロジーナの第二の手紙を疑う後見人バルトロ。下に書かれたフランス語は、「わたしのようなドクターに向かって」
この物語を複雑にしているもう一つの原因は、手紙である。この物語では、猜疑心の強い後見人バルトロの目を盗むべく、恋心がいちいち手紙に託され、あちらこちらへと複雑に移動する。しかも手紙はどれも、バルトロのすぐそばで舞い、その気配をふりまく。目を盗むためというよりは、ほとんどその存在をひけらかしていると言ったほうがよい。手紙こそは、物語を混乱させる、油断ならぬ小道具である。
しかし、ただ複雑だ、混乱しているというだけでは、この物語が何世紀にもわたって人々を魅了してきた理由がわからない。《セヴィリアの理髪師》がかほどまでに長きにわたって世界中で演奏され続けているからには、この物語に、何かしら、人々の心にひっかかる、深い構造が含まれているに違いない。では、それはなんだろうか。
今回は、《セヴィリアの理髪師》の物語に登場する手紙に注目しながら、物語に埋め込まれている人間関係について考えてみよう。
読み上げの形式
 バルコニーから手紙を落とそうとするロジーナ
バルコニーから手紙を落とそうとするロジーナ
《セヴィリアの理髪師》には、三通の手紙が登場する。
第一の手紙は、ロジーナがバルコニーの下に落とす手紙である。ロジーナは監視の目を光らせている後見人バルトロの目前で、手紙を階下に落とす。手紙は風のない階下へひらひらと落ち、伯爵が拾い上げる。バルトロは疑いの目を向けるが、ロジーナは手紙のことを「無用な用心のアリア」の譜面だと言い張って切り抜ける。
このあと、手紙の全文が読み上げられる。が、この読み上げにはちゃんとしかるべき形式がある。以前挙げた、オペラにおける手紙の原則をもう一度思い出しておこう。
1. 手紙は本来、声を避けるメディアである。
2. 差出人も受取人も、手紙を声にすることを避ける。
3. オペラでは、手紙を読み上げるとき、メロディを伴わないことによって、オペラ的な声を避けることを表す。
まず、ここで読み上げるのは、受取人である伯爵ではない。伯爵は慇懃に「お前、読め」と言って、そばにいるフィガロに読み上げさせる。手紙を読むことは、いわば受取人と秘密を共有することである。「町のなんでも屋」フィガロはロジーナに無断で彼女から伯爵に宛てられた手紙を読むことで、伯爵の共犯者となり、以後、伯爵の恋を手助けすることになる。
読み上げには、メロディは伴っていない。ハープシコードが和音を奏でるのを合図に、レチタティーヴォが始まり、フィガロはすらすらと手紙の内容を読み上げる。「あなた様のご熱心なる思いやりは私の好奇心をかき立てております・・・この(バルトロとの)鎖を断ち切るためあらゆることをいたす所存です」そして、最後に記された署名をフィガロが「不幸な (La sventurata)...」と読み上げようとした途端、伯爵は手紙を引き取って夢見るように「ロジーナ Rosina !」と、差出人の名前を口にする。その名前をあでやかに飾るようにハープシコードが再び和音を奏でて、手紙文の終わりを告げる。ここでは、1,2,3の原則が見事なまでに実現されている。その点では、しごくオペラらしい手紙場面だと言えるだろう。
鏡としてのバルトロ
 手紙をしたためるロジーナ
手紙をしたためるロジーナ
伯爵は、ロジーナの心を試すべく、自分を貧しい身分の「リンドーロ」であると偽って、階下で恋心を歌う。この歌に答えてロジーナが書くのが、第二の手紙である。ロジーナは自分の決意を歌いながら手紙に封をし(カヴァティーナ《一つの声が少し前に》)、出入りの床屋であるフィガロに手渡す。さすがのフィガロも封をした手紙を読むことはできない。フィガロを介してロジーナの手紙はリンドーロこと伯爵へと渡される。
リンドーロこと伯爵は、自らロジーナのもとに乗り込むべく、騎兵の兵卒のふりをして後見人バルトロに宿泊の申込をする。バルトロとの口論の隙に、リンドーロこと伯爵は床にロジーナへの手紙を落とす。ロジーナはハンカチをかぶせて、この手紙を拾い上げる。バルトロは疑いの目を向けるが、ロジーナは手紙のことを「洗濯物のリスト」だと言い張って切り抜ける。これが第三の手紙である。
第三の手紙におけるリンドーロの身振りは、まるきり第一の手紙におけるロジーナの身振りを反復していることに注意しよう。手紙はわざわざバルトロの目前で「落とされる」。そして相手に「拾い上げさせる」。バルトロに対しては、手紙は他の紙であると言い訳される。
なぜこんなにも瓜二つの反復が行われるのか。それは、彼らがバルトロを必要としているからである。
ロジーナとリンドーロとがなぜわざわざ手紙を書くかといえば、それはバルトロに聞かれることを避けるためだ。しかし、バルトロがいなければ、わざわざ手紙を書く理由がない。むしろ、彼らの欲望は、バルトロの存在を必要としているといっていいだろう。ロジーナは、ただリンドーロと結ばれたいというよりは、「この(バルトロとの)鎖を断ち切るためあらゆることをいたす所存」(ロジーナの第一の手紙)なのであり、伯爵もまた、ただロジーナの気性に惚れただけではなく、「不幸な」ロジーナを老いぼれ後見人の手から救いたいからこそ、恋心をつのらせている。つまり、手紙を書きたい、手紙を渡したいという二人の欲望は、バルトロの存在ゆえに燃え上がる。その結果、彼らは飽きることなく、自分たちの手紙を、わざわざバルトロの目前で際どく渡そうとする。バルトロの目前で初めて、手紙は手紙らしくなる。ロジーナとリンドーロにとって、バルトロはいわば鏡である。バルトロという鏡の前で同じ身振りを繰り返すことによって、二人は、お互いを自分の鏡像として認めあえるのである。
変装に憑かれた男
バルトロの存在を欲しているのは、手紙だけではない。
伯爵の変装もまた、バルトロなしには成り立たない。もちろん、変装はバルトロにばれぬように行われる。しかし、バルトロに見せなければ、そもそもバルトロにばれるかどうかがわからない。変装とは、そもそも、自分の正体を知られぬことを目的としている。が、誰にも見せることのない変装は、変装にならない。変装者は必ず、見せる相手を欲する。変装した姿を相手が見て、なおかつそれが自分ではないことを認めてくれなくては、変装する価値がない。だからこそ、伯爵は、変装をし、わざわざバルトロのいる場所に行き、そしてバルトロが愚かにもその変装に騙されるのを確認しては悦に入る。バルトロという「騙される者」の存在によって、変装ははじめて変装となるのである。
その一方で、変装する者はどこかで、変装を見破って欲しいと思っている。変装によって表されている者がじつは自分なのだとわかってもらえなければ、それは変装でもなんでもなく、ただの異なる二者に過ぎない。だから、変装者は、ただ「騙される者」を欲するだけでなく、変装しているのがじつは自分だとわかってくれる第三の他人、つまり「見破る者」を必要とする。
これは何も『セヴィリアの理髪師』に限った話ではない。
たとえば、江戸川乱歩の『怪人二十面相』を考えてみよう。怪人二十面相は変装の天才である。しかし、もし変装が、純粋に人目につかぬことを目指しているのなら、被害者に知られぬまま、こっそり犯罪を犯せばよいはずである。ところが、二十面相には「一つのみょうなくせ」がある。それは、貴重な品物をねらうときは必ず、何日何時にはそれをちょうだいに参上するという予告状を送ることである。二十面相は、予告の時刻に意外な人物に変装しては、被害者の目前に現れる。被害者は判で押したようにこの変装に騙される。予告通りに品物を被害者の前で奪い、なおも誰も二十面相の存在に気づかないとき、二十面相は被害者たちの目の前で、わざわざ正体をばらしてしまう。やがて、明智小五郎というライバルが登場し、彼の正体を見抜くようになると、二十面相は明智探偵によって変装を見破られては逃げることを反復するようになる。二十面相は、いわば変装に「騙される者」と変装を「見破る者」とを求めて犯罪を繰り返しているのであり、明智小五郎は、二十面相の欲望を体現する「見破る者」なのだ。
伯爵にとっては、ロジーナがこの「見破る者」にあたる。バルトロが騙されると同時に、ロジーナがことごとく変装を見破ってくれることによって、伯爵の変装はめでたく成就し、伯爵はロジーナにますます恋心をつのらせる。
変装と手紙
変装をめぐる三者の図式は、手紙の図式と見事に対応している。伯爵の手紙は、わざわざバルトロのすぐそばで落とされる。それは手紙が、バルトロに見られながら見逃されることを欲しているからである。そして、手紙を見ながらバルトロが騙され、ロジーナが手紙を見破ることで、伯爵はようやく目的を達成する。
手紙と変装との対応はこれだけではない。第一の手紙は、階下に舞ったあと、バルトロに対しては「無用な用心のアリア」の譜面だったことにされる。第三の手紙は、床に落とされた途端、バルトロの目を欺くべく「洗濯物のリスト」とすり替わる。《セヴィリアの理髪師》では、手紙がまさに伯爵のごとく「変装」して、バルトロの目前を行き来するのである。
恋人たちのやりとりは、さらにエスカレートする。
音楽教師ドン・アロンソに変装したリンドーロ(実は伯爵)とロジーナは、大胆不敵にも後見人バルトロの目の前で、歌に託して自分たちの恋心を歌い出す(またしても恋人たちは、バルトロの目前でなければ燃え上がることができないのである)。ドン・アロンソは、「ロジーナ、お願いだ、私の言うことを聞いてくれ」と呼びかけながら、譜面を読むふりをしながらこんな風に歌う。「真夜中ちょうどに我々は貴女を連れにここに来る。今や我々は鍵を手に入れているからなんの懸念もない」。内容は一種の秘密の恋文と言っていい。が、それは差出人と受取人だけの秘密のことばであり、声にしたとたん、秘密でなくなってしまう。
しかし、だからこそ、ドン・アロンソとロジーナは、あえて歌に託しているのだ。歌ならば、まさかそれが、すぐそばにいる者へのメッセージとは思われないだろう。「手紙は声にされることを避ける」という規則が、ここでは逆手に用いられている。声にされているからこそ、手紙とは思われない。あからさまだからこそばれることはない。二人の歌は、いわば歌に変装した手紙なのである。
なぜ変装と手紙とは、同じ振る舞いをしてしまうのだろうか。それは、どちらも同じ三者関係に依存しているからだ。
変装は「変装する者」「騙される者」「見破る者」の三者関係を産み出す。手紙もまた「差し出す者」「見逃す者」「読む者」の三者関係を産み出す。わたしたちは「特別」な誰かと二者関係を築こうとするとき、無意識のうちにその「特別」な誰か以外の、第三の人間を招き入れる。というより、第三の人間なしには、相手は「特別」にはならない。手紙も変装も、「騙される者」の目前をわざわざ通過することによって、正体をさらす相手を「特別」な存在にする。あたかも、怪人二十面相が、大胆にも被害者のただ中に変装で現れ、正体を見破る明智小五郎を「特別」な存在にするように。
伯爵は、変装と手紙に憑かれた者である。このような者は、三者関係を求めては、物語を複雑怪奇になる。なぜなら、彼は、自らを変装に包んでは、変装を見せびらかし、繰り返しその正体を見破られようとするからだ。変装者とは、変装という封筒に身を包んだ手紙であり、見逃す者と読む者を求めてやまない存在なのである。
 第2幕、バルトロの前でロジーナが音楽教師ドン・アロンソ(実はリンドーロ=伯爵)へ歌に託して恋心を伝える場面。下の仏語の歌詞はフランスで人気のあったオペラコミーク版《セヴィリアの理髪師》から(「うるわしの木陰よ/青葉がまた開こうとしている/軽やかなニンフも/若い羊飼いも/お前を褒め称えにやってくる」)。
第2幕、バルトロの前でロジーナが音楽教師ドン・アロンソ(実はリンドーロ=伯爵)へ歌に託して恋心を伝える場面。下の仏語の歌詞はフランスで人気のあったオペラコミーク版《セヴィリアの理髪師》から(「うるわしの木陰よ/青葉がまた開こうとしている/軽やかなニンフも/若い羊飼いも/お前を褒め称えにやってくる」)。
第6回・了
このオペラが観たくなったら…

ロッシーニ 歌劇《セヴィリアの理髪師》チューリヒ歌劇場 2001
欧州のオペラ・シーンで話題を集めるチューリヒ歌劇場から、名匠ネッロ・サンティの指揮のもと新世紀のディーヴァ、カサロヴァが天真爛漫なロジーナを歌い、充実した男声アンサンブルと共にロッシーニの傑作オペラ《セヴィリアの理髪師》の真髄をお届けします。地中海的雰囲気の横溢するアサガロフの演出が新鮮です。
■キャスト&スタッフ
アルマヴィーヴァ伯爵:レイナルド・マシアス
バルトロ:カルロス・ショーソン
フィガロ:マヌエル・ランサ
ロジーナ:ヴェッセリーナ・カサロヴァ
バジリオ:ニコライ・ギャウロフ
フィオレッロ:ヴァレリィ・ムルガ
ベルタ:エリザベス・ラエ・マグナソン
演出:グリシャ・アサガロフ
指揮:ネッロ・サンティ
チューリヒ歌劇場管弦楽団
■収録
2001年4月1日 チューリヒ歌劇場
■SPEC
- [収録時間] 155分
- [字幕] 日本語・イタリア語
- [映像] 16:9 カラー
- [音声] リニアPCMステレオ/Dolby Digital5.1/DTS5.1
- [ディスク仕様] 片面2層+片面1層(2枚組)
- DVD●TDBA-80280~1 4,935円(税込)