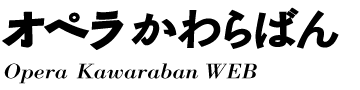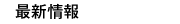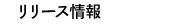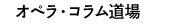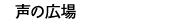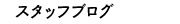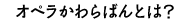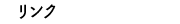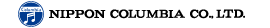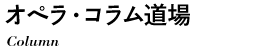連載内容
『絵はがきの時代』(青土社)の著者、細馬宏通さんのオペラ絵はがき連載。
細馬さんの所有するオペラ絵はがきコレクションをもとに、絵はがきの時代=図像交換の時代であり、さらにオペラ絵はがきがオペラをアイコンとして交換するメディアであったことを明らかにします。
初演当時の絵はがきから透かし見える時代精神!
プロフィール
 写真:渋谷博
写真:渋谷博
細馬宏通
1960年西宮市生まれ。滋賀県立大学人間文化学部教授。専門は会話とジェスチャーの分析、 19世紀以降の視聴覚メディア研究。著書に『絵はがきの時代』『浅草十二階』(いずれも青土社)など。バンド「かえる目」で作詞・作曲とボーカルを担当。
好きな音楽:中学生時代はブーレーズ指揮のドビュッシーとラベル、高校時代は荒井由実と矢野顕子、いまは物音から鼻歌まで。
好きな食べ物:ご飯と干物。

第7回 声で書く手紙 《タチヤナの手紙》
ここまで、さまざまな手紙の場面を取り上げてきたけれど、今回は大物である。というのも、長大なアリアがまるまる、手紙の場面にあてられているからだ。ご存じ『エフゲニー・オネーギン』の《タチヤナの手紙》である。
田舎暮らしをしている読書好きの可憐なタチヤナのもとに、友人に連れられてオネーギンがやってくる。オネーギンの姿に恋してしまったタチヤナが、月夜に一人、部屋の中でオネーギンに宛てて思いのたけを綴りながら歌うのが、このアリアだ。
ここまで、オペラで差出人が手紙を読み上げるときは、オペラ的なメロディアスな声を避ける、という話を書いてきた。実際、これまで見てきたオペラでは、手紙文はレチタティーヴォで朗読調で読まれるか、単純なワンノートによって旋律のなさが強調されていた。
ところが、《タチヤナの手紙》は、この原則に真っ向から立ち向かっているように見える。プーシキン原作の手紙文に、チャイコフスキーは豊かなメロディを付けているのだ。暗黙のうちに守られてきたオペラの原則を、チャイコフスキーは全く無視しているのだろうか。
いや、話はそう簡単ではない。
 アントニーナ・ネジダノーヴァ(タチヤナ役)の絵はが
き(旧ソ連製)。革命前の1906年、ボリショイ劇場(モスクワ)での『エフゲニー・オネーギン』。
アントニーナ・ネジダノーヴァ(タチヤナ役)の絵はが
き(旧ソ連製)。革命前の1906年、ボリショイ劇場(モスクワ)での『エフゲニー・オネーギン』。
まず、《タチヤナの手紙》は、ただ手紙文にメロディをつけて読み上げるアリアではない。プーシキンの原作では、タチヤナの手紙の文面は、まるごと一つのまとまりを為している(第三章31節)。が、後で述べるように、チャイコフスキーと脚本家のシロフスキーは、この場面を翻案するにあたって、この手紙をいくつかの部分に分断し、原作とは異なる構成をほどこしている。
このことは、実際にオペラを見ると、いっそうはっきりする。《タチヤナの手紙》は、確かに手紙が書かれる場面には違いないのだが、見ていて感じるのは、もっと不思議な感覚である。手紙の内容をただ聞いているというよりは、あたかもタチヤナ自身の夢想の中に誘われていくかのようなのである。
いったい《タチヤナの手紙》に、チャイコフスキーとシロフスキーはいかなる魔法をほどこしているのだろうか。そのヒントは、オペラのリブレット(台本)にある。リブレットには、音符ばかりでなく、歌手がどのような所作をすべきかが細かく指定されている。こうした所作は、プーシキンの原作にはないものだ。今回は、メロディに加えてこの所作の問題を考慮に入れながら、《タチヤナの手紙》について考えていこう。
手紙からの離陸
手紙を書く場面をアリアにする、というときに、まず考えられるのは、ペンを走らせながら、いままさにペンが書いていることを歌う、という方法だ。しかし、オペラ版『エフゲニー・オネーギン』では、このやり方はほとんど使われていない。まずタチヤナが机に向かって椅子に座り、手紙を書き始めると、オーケストラはオペラの最初に提示された主題を奏で始める(譜面1)。しかし歌はまだ始まらない。このとき、タチヤナは手紙を黙って書いている。他のオペラと同じく、ここでは、差出人はオペラ的な声を避け、手紙を書き綴っているのである。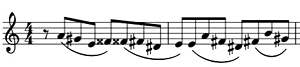 (譜面1) (譜面1) |
が、この最初の試みはうまくいかない。「だめ、こうじゃないわ! またはじめからだ!」タチヤナは、手紙をくしゃくしゃに丸めてしまう。「どうしたのかしら、火の上にいるみたい・・・始め方がわからないわ!」原作にはない台詞である。
おもしろいことに、「始め方がわからないわ!」と歌ったとたんに、タチヤナはあたかも始め方を思いついたように、再び書き始める。今度は、少し音楽のテンポが上がって、弦の伴奏とともにオーボエが印象的なメロディを奏で出す。弦はあたかもペンの運びを助けるかのように、シンコペーションを効かせて前進していく。フルートがメロディに祝福を送るように降り注ぐ(譜面2)。ああうまく書き出せたのだな、と観客は音楽を聴いただけで判る。
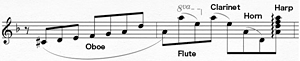 (譜面2) (譜面2) |
しかしここでもやはり、タチヤナは書いている間は黙っている。リブレットによれば、このあとタチヤナは「ペンを止めて、書かれたことばを読み上げる」。つまり、書きながら歌うのではなく、いったん途中まで書き終えてから読み上げるよう、所作が指定されているのである。
弦とオーボエの伴奏が続く中、読み上げはこんな風に始まる。「わたしはあなたに書いています。それでもう十分ではありませんか?この上何を申し上げることがありましょう?」。不思議な書き出しだ。「わたしはあなたに書いています」とは、書かずもがなのことではないか。これを読む相手の目の前には書かれた手紙がある。書いていますと言われなくとも、そんなことはわかりきっている。早く用件に入ってくれ、と言いたくなる。
いや、そんなせっかちを言うのは野暮というものだ。恋文とはいつだって「不用意な手紙(プーシキン)」ではないか。恋文の内容のほとんどは、不用意であること、書かなければよかったこと、告白を迂回することによって成り立っている。それに、内容がどうであれ、たいていの恋文は、封を開ける前に、その正体を明らかにする。靴箱や机の引き出しで見つけられたとたんに、友達やばあやを介して渡されたとたんに、それは恋文であると判る。そこに書かれた手紙がある、ということ自体によって、恋文はすでにその用件を相手に伝えているといってもよい。むしろ「わたしはあなたに書いています。それでもう十分ではありませんか?」とは、恋文の本質をずばり言い当てたことばだとさえ言える。
この手紙の始まりに、チャイコフスキーは微妙な旋律を付している。まず「わたしはあなたに書いています」は、起伏のないAの音程だけを用いて、あたかも旋律のなさを強調するように。次に、「それでもう十分ではありませんか?」では、Aの末尾に少し起伏を添えて(譜面3)。さらに「この上何を申し上げることがありましょう?」では、Aの頭と末尾に起伏をつけて(譜面4)。
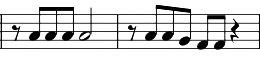 |
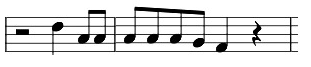 |
| (譜面3) | (譜面4) |
最初は手紙らしく読み上げ始めながら、次第に声の起伏を混じらせて、手紙というよりは独白へと離陸させていく。いわば、 「わたしはあなたに書いています」というひとことで手紙らしさ、 旋律の不在性は完結されて、そこからは手紙というよりは、声による訴えへと移行させていく仕組みなのである。
手紙は声へとすり替わりつつある。しかし、ただすり替えられて終わるのではない。このあと、手紙と声とは、よりはっきりと対立させられていく。
声による中断
いよいよタチヤナの手紙が書き始められた。タチヤナは途中まで書いた手紙を読み返している。
旋律をたっぷりと使いながらタチヤナが読み返すのは、恋の告白というよりは、告白への逡巡である。「あなたがお怒りになったとしても無理はないこともわかっています」「でも、あなたはお慈悲をもってわたしを許して下さるでしょう」「はじめわたしは黙っていようと思っていました」「あなたはたぶんわたしの恥を永久に知らずにいらしたことでしょう、けして(ニコグダ)!」まったくいらいらさせられるような遠回りではあるが、これもまた恋の告白につきもののことととらねばなるまい。このくだりはほとんどプーシキンの原作通りである。
が、このあと、チャイコフスキーとシロフスキーは、原作にはないことばを挿入する。タチヤナは、自分の放った「けして(ニコグダ)!」という否定に対して、急に悟ったように、「おおそうだ(オー、ダー)」と手紙を置くのである。歌は、レチタティーヴを指定されている。もはや声は、手紙文を追ってはいない。「わたしは自分の狂ったこの情熱を、隠し通すと誓ったはずだった」「でも、わたしには自分の心を抑える力がない。何が起ころうとも起こるにまかせるしかない。」「告白するのよ!勇気を持って!彼はすべてを知るでしょう。」
恋心の相手を「彼」と呼んでいるところからも、これが手紙文ではなく独白の形式を取っていることは明らかである。しかし、相手を「あなた」と呼んだり『彼」と呼ぶことで手紙と独白とを区別する余裕を、タチヤナはこのあと次第に失っていく。というより、音楽と所作によって次第に手紙は独白にその地位を譲っていくのである。その過程をさらに追っていこう。
彼女は再び書き始める。オーボエのメロディが鳴り、今度はタチヤナは書きながら歌う。書きながら歌うことは、これまで見たオペラの原則からはずれている。人が手紙を心から書くとき、それは声にはできない。声にできないからこそ手紙に書くのである。逆に言えば、書きながら声にできるということは、そのことばはまだ、手紙にする必然性のないもの、声にしてもさしつかないものであることを示すといってもよい。実際、この部分は、まだ、手紙の本題ではない。本題どころか、彼女の本心とは逆の仮定が述べられていく。「なぜあなたはこの村を訪れたのでしょう?さもなければ、忘れられたこの草深い片田舎で、私は一生涯あなたという方を存じあげず、辛い苦しみも知らずに過ごしたでしょうに。時のたつままに初心な魂の動揺を静めて、誰か他の人を見つけて、貞淑な妻とも慈悲深い母ともなったでしょうに・・・」タチヤナは、エフゲニーがこの村を訪れなかったなら訪れたであろう自分の未来をあれこれと思い描く。あたかも迂回をすることで、自分の情熱を抑えようとするかのように。
しかし、タチヤナは自分の考えに怯えたように「突然立ち上がる」。「ほかの人!」。原作にもこの一文はあるが、それは手紙の中のひとことに過ぎず、むろん立ち上がる所作はない。それに対してオペラ版では大胆にも、ここで手紙を書くことを中断させてしまう。
手紙の破綻・手紙の成就
いまや、ものとしての手紙はテーブルに放っておかれたままである。タチヤナは立ったまま歌いながら、夢の中に出てきた相手に向ける甘い思いへと滑り込んでいく。「あなたは夢にも出てきました。心の中ではあなたの声が響いていました」。オーケストラはひとことひとことに甘く合いの手を打つ。小鳥の様にさえずるフルートが、まるでタチヤナの恋心に答えるように、恋しいオネーギンの姿をあぶりだす。あたかも惑星ソラリスのように、タチヤナが求めるものを形にしていく。
その合いの手を否定するようにタチヤナはさらにたたみかける。「いいえ、あれは夢ではなかったわ!」「はいっておいでになったとたん、わたしにはあなただとわかりました。体がしびれてほてってきます。心の中でわたしは言います。『あの人だ!あの人だ!』」「心の中で」と言いながら、その台詞をタチヤナは絶叫して歌う。もはやタチヤナは、自分の恋心を抑えることができないのと同じように、心の中の声が現実の声になってしまうことを抑えることができない。心の中にあるはずのことばを、歌によってあからさまに声に出して叫ぶ。
黙って手紙にこめるはずだったことばは、手紙にとどめおくことができず、声にされる。声にされることで、タチヤナの抑えてもあふれ出す恋が表される。チャイコフスキーは、手紙を書く場面を描きながら、手紙を書くことを破綻させ、そのことで恋心の激しさを表すという、なんともロマンティックな大技を繰り出しているのである。
ここまでくると、もはやタチヤナは書きながら歌うことはない。途中、歌のないアンダンテで手紙に戻るものの、すぐにペンを止めて考え込んで歌い、さらには立ち上がってうろうろしながら歌う。《タチヤナの手紙》では、書こうとした手紙は声によって中断される。手紙から離れるほどに、歌は力を得る。クライマックスに近づき、オーケストラの合いの手はますます力強くなる。「たったひとことでこころの希望を生き返らせてくださるか、それとも私を叱って、苦しい夢を終わりにしてくださるかです!」相手に決断を迫る絶叫を放った直後、タチヤナは憑きものが落ちたように急いでテーブルに戻って無言で手紙を書き上げる。
チャイコフスキーは、プーシキンの作り上げた手紙の文面を、ただの手紙としてではなく、書くことと声との相克として描き直した。これはただ「手紙を書く」だけの場面でも、あるいは「手紙を読む」だけの場面でもない。手紙を書こうとして抑えられていた声を、歌によって解き放ち、歌によって声にされたことばに力を得て、再び手紙を書く場面なのである。
実際にアリアの最中にタチヤナがペンを持っている時間は、ごく短い。手紙は、手によってではなく、彼女の声によって書かれたのではないか。文字は、タチヤナが手を下すことなく、声によって刻まれたのではないか。《タチヤナの手紙》を聴き終わった観客は、そんな不思議な錯覚にさえ、とらわれる。声で書く手紙。なんともオペラ的なできごとではないか。
 レオニード・ソビノフ(レンスキー役)の絵はがき(旧ソ連製)。1900年、ボリショイ劇場での『エフゲニー・オネーギン』
レオニード・ソビノフ(レンスキー役)の絵はがき(旧ソ連製)。1900年、ボリショイ劇場での『エフゲニー・オネーギン』
年月が経ち、公爵夫人となったタチヤナと再会したオネーギンは、ようやく彼女への愛に目覚める。彼は遅すぎた恋の手紙を書く。最終場、タチヤナは一人、読み終えたオネーギンの手紙を手にしている。手紙は、声に出して読まれることはない。原作では手紙文として記されているオネーギンのことばは、オペラでは手紙ではなく、タチヤナの部屋に忍んできたオネーギンの歌として再編されているからである。オネーギンは、彼を拒むタチヤナに声をあげて言い寄る。しかし、切々と訴えるそのことばには、悲しいかな、手紙を破綻させるほどの声の力は、込められていない。
第7回・了
このオペラが観たくなったら…

チャイコフスキー:歌劇《エフゲニー・オネーギン》ボリショイ劇場2000年
《エフゲニー・オネーギン》最高の演奏として語り継がれる1944年ボリショイ公演の蘇演の記録。巨匠ポクロフスキーらが豪華絢爛なボリショイ劇場の流儀を余すところなく次世代に伝えた記念碑的映像です。
■キャスト&スタッフ
演出:ボリス・ポクロフスキー
指揮:マルク・エルムレル
演奏:ボリショイ劇場管弦楽団&合唱団
合唱指揮:スタニスラフ・ルィコフ
振付:ユーリ・パプコ
背景:セルゲイ・バルヒン
装置:アリョーナ・ピカーロワ
衣裳:エレーナ・メルクーロワ
ラーリナ:イリーナ・ウダローワ
タチヤナ:マリヤ・ガヴリーロワ
オリガ:エレーナ・ノヴァーク
フィリーピェヴナ:ガリーナ・ボリーソワ
エフゲニー・オネーギン:ウラジーミル・レトキン
レンスキー:ニコライ・バースコフ
グレーミン公爵:アイク・マルティロシャン
トリケ:アレクサンドル・アルヒーポフ
大尉:ウラジーミル・クラーソフ
ザレツキー:アレクサンドル・コロートキ
農民の合唱のリーダー:ウラジーミル・ソコロフスキー
■収録
2000年10月18日、ボリショイ劇場
■SPEC
- [収録時間] 156分
- [字幕] 日本語・ロシア語
- [映像] 16:9 カラー
- [音声] リニアPCMステレオ/Dolby Digital5.1/DTS5.1
- [ディスク仕様] 片面2層+片面1層(2枚組)
- DVD●COBO-5959~60 3,570円(税込)