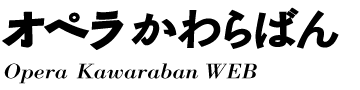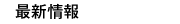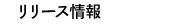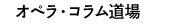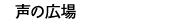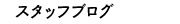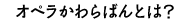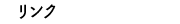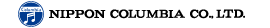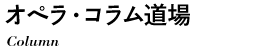連載内容
オペラをこよなく愛する吉田光司さんがお送りするオペラ・ニュース月報。国内外の歌劇場の様々な話題、ニュースを活きのいいうちにご紹介。5分で世界のオペラ界が垣間見える、月1回更新の速報型ウェブ連載!
※煩雑になるので伝聞調を採っていませんが、基本的に実際に公演を観た人から得た情報を基に書いています。
プロフィール

吉田光司
早稲田大学法学部、および国立音楽大学声楽科卒。音楽関係の会社に勤務後、現在はフリーで活動中。オペラDVDの日本語字幕翻訳・制作、ノーツ執筆両方を手掛ける職人であり、また稀にNHK-FMのクラシック番組で案内役も務める。大のオペラ好きで、オペラと名のつくものは何でも聴くが、特にお気に入りはヘンデルとロッシーニ。イタリア、ペーザロで開催される「ロッシーニ・オペラ・フェスティバル」には十年来通い詰める常連である。オペラ公演は「自腹で聞くのが当然」の主義。和食の魚、ことに寿司と干物が好物。猫をこよなく愛する。

第6回 [特別編] ロッシーニ・オペラ・フェスティヴァル速報
編集部より:今回の「オペラニュース月報」は特別編。イタリアのペーザロで毎夏行なわれるロッシーニ・オペラ・フェスティヴァルを、吉田さん自身が観劇してきました。今回は、その臨場感あふれるレポートをお届けします。
 ロッシーニ・オペラ・フェスティヴァル速報
ロッシーニ・オペラ・フェスティヴァル速報
2009年も、ペーザロで行われるロッシーニ・オペラ・フェスティヴァル(以下ROFと略)を観劇してきた。今年は新制作の《ゼルミーラ》(1826年パリ稿)、新制作の《絹のはしご》、そして2003年制作の再演である《オリー伯爵》の3本が中心である。
総じての感想は、ROFとしてはやや低調に終わっていたと言わざるを得ない。音楽が良いものは演出に難あり、逆に舞台が面白いと音楽が低調と、噛み合っていないのだ。舞台と音楽が融合した時、ロッシーニのオペラは素晴らしい相乗作用が生まれるのだが、今年はついにそうした瞬間がなかった。
●《ゼルミーラ》 (1826年パリ稿)
おそらくロッシーニのオペラの中でも最も至難なテノール役であるイーロを歌ったファン・ディエゴ・フローレスが、期待をもさらに超えて圧倒的な素晴らしさを披露してくれた。高いD音を連発するアリアや、最後にまだこれだけ歌うかというフィナーレでの歌に酔いしれた。対する悪役アンテーノレ役のテノール、グレゴリー・クンデが3年連続で強烈な印象を与える充実振りで、この二枚看板はROFならでは。他の役も概ね上々。とはいえ、肝心のタイトルロールのケイト・オールドリッチは、よく頑張ってはいたものの、全体の中で弱点になっているのは否めない。昨年の《エルミオーネ》で絶賛されたロベルト・アバドとボローニャ市立歌劇場のオーケストラのコンビは、今年もロッシーニのツボをピタリと押さえた見事な演奏を聴かせてくれた。
しかし、ジョルジョ・バルベリオ・コルセッティの演出がどうにも問題。《ゼルミーラ》を近代の社会動乱と革命の物語に据えるのは悪くないが、舞台づくりにセンスが感じられない上に、アイデアがことごとく滑っていて、プロの演出家とは思えないほどまとまりのない舞台で終わってしまった。初日には、壮絶なブーが飛んだという。
●《絹のはしご》
ダミアーノ・ミキエレットの演出は、賛否が分れたものの、かなり面白いものだった。舞台は、実寸の設計平面図とおぼしき床面に、実際の家具を置いた、不思議な「館」で演じられている(壁やドアはないが、あたかもあるように演じられている)。これを背景に据えられた45度に傾けた鏡で映し出し、効果を出していた。ミキエレットは、《絹のはしご》が本来持っていた斜に構えた皮肉とドタバタぶりを巧みに現代化した舞台を作り上げていたが、ことに日本のマンガ文化からの影響がかなり感じられた。ちなみに召使のジェルマーノは、イタリアの有名コメディアンのパクリをしていて、イタリア人(だけ)には大うけだった。
だが演奏は、ここ10年ほどのROFの上演でも最低レべルといってよいほどの残念な出来だった。歌手はほとんどが若くて非力。スペインのテノール、ホセ・マヌエル・サパタは明らかに喉を傷めていて聴くのがつらいほど。さらに、クラウディオ・シモーネの指揮がこの現代的な舞台とあっておらず、しかもアンサンブルが終始揃わない。レチタティーヴォ・セッコのピアニスタが必死に補助指揮していたほどだった。ミキエレットの演出に合った冴えた演奏だったら、もっと盛り上がったことだろう。
●《オリー伯爵》
2003年制作の再演。この時は、ファン・ディエゴ・フローレスとステファニア・ボンファデッリらの出演で、音楽的にも大変豪華だったが、加えてルイス・パスクワルの演出が大いに話題になった。サロンで《オリー伯爵》ごっこをするという二重設定が分かり辛いと非難が多く出た一方で、その重層構造の奥から浮かび上がる卓越した人間描写は一部で高い評価も得ていた(これについては拙HPにて触れている)。 だが、今回の舞台は、あらゆる点で前回とはまるで別物であった。分かり辛いという批判に応えたためだろうが、ことに第1幕が説明的になり過ぎ、結果として「《オリー伯爵》ごっこ」をしている戯れの馬鹿馬鹿しさばかりが強調される結果になっていた。一方で肝心の要素があちこちで抜けていた。たとえば、この演出では伯爵夫人を演じる女性とイゾリエを演じる女性がレズビアンの関係にあるというのが重要なのだが、それが今回は容易に理解できない。また、2003年には意味のあった「平和の旗」をそのまま踏襲したフィナーレも、まるで6年前の新聞を読んでいるような気分にさせられた。
東京で学んだ若いテノール、石倚潔(シー・イージェー)がタイトルロールに大抜擢された。健闘していたが、まだだいぶ若さが露見していた。伯爵夫人のスペインのソプラノ、マリア・ホセ・モレノは、容姿も美しく、歌もまずまずだったが、演出の要求する役柄とはかなりズレていた。ロレンツォ・レガッツォの家庭教師が一番映えていたろう。 パオロ・カリニャーニの指揮は、引き締まったダイナミックなもの。鮮烈ではあったが、少々ミリタリー調過ぎた気がする。ボローニャのオーケストラからかなり反発を買っていたそうだ。
●若者公演《ランスへの旅》
ROFでは毎年、若い歌手の勉強を目的としたアッカデミアが催されている。そしてその参加者によって、2001年から《ランスへの旅》が2公演上演されるのが恒例となっている。この若者公演の《ランスへの旅》からは、既に多くの優秀な歌手が発掘されており、毎年その出来栄えが注目されている 今年は日程の関係で第2公演のみ観劇(今年は歌手の入れ替わりはほんの僅か)。第1公演を観た人たちから「今年はレベルが低い」と聞いていたが、過去の若者公演と比べて、とりわけ低水準とは思わなかった。たしかにソプラノがこれほど全壊だった年はなかったろう。しかしテノールとメッゾは要注目。リーベンスコフのエネア・スカラ Enea Scala(イタリア人?)は、張りのある声でDまで出せて、しかも装飾歌唱もできるという、ちょっと驚異的なテノールだ。また、ベルフィオーレのハンス・エーヴェル・モゴロン Hans Ever Mogollon も軽めの柔らかい声で悪くない。ペーザロで唯一のインターネットポイントで偶然出くわして話したところ、コロンビア人だそうだ。また、メリベーアを歌ったヴィクトリア・ザイチェヴァ Victoria Zaytsevaも充実したメッゾの声を持っている。
だが何より特筆すべきは指揮者だ。タイ人のトリスデー・ナ・パタルン Trisdee na Patalung は、なんとまだ23歳。タイのバンコク・オペラで活動し、オランダでも学んだという。若く経験のない歌手たちを引っ張って公演を盛り上げたのは彼の功績だ。カーテンコールで、ボルツァーノ・トレント・ハイドン管弦楽団のメンバーから温かい拍手が送られていた。
☆スカラの歌唱はYouTubeにいくつかアップされている。
●演奏会、リサイタル
実は今年のROFで一番強烈だったのは、8月16日の昼11時から行われたハイドンのコンサートだった。交響曲2曲の間に、カンタータ《ナクソスのアリアンナ》(オーケストラ版)が演奏されたのだが、そのエヴァ・ポドレシュが素晴らしかったこと!!! この4月に57歳になったポドレシュ、見た目こそおばさんからおばあちゃんになったような印象だったが、しかし歌は相変わらず見事で、深いコントラルトの声と、柔軟で運動性に長けた歌い回しには磨きがかかっていた。何より彼女ならではの表現力の幅広さには唸らされた。絶望したアリアンナが悲痛に叫ぶ「酷い人 barbaro!」の一言は、聞く者の胸に鋭く突き刺さってきた。曲が終わると、ロッシーニ劇場が爆発するような歓声に包まれ、何分も大喝采が続いた(アンコールに《アルジェのイタリア女》の「酷い運命」と、スペインのカンツォネッタ)。
演奏会は、マヌエラ・カンタレロ、ホセ・マヌエル・サパタ、グレゴリー・クンデ、オリガ・ペレチャツコの4つ。なかでは、50歳を越えて新たな境地に達したクンデのリサイタルが充実していた。プログラムの最後に、前半だけとはいえ《ウィリアム・テル》のアルノールのアリアが歌われた。鋭い声で響き渡る高いC音は、今のクンデならではの魅力だ。アンコールのガーシュウィンも良かった。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
ちなみに、ペーザロ入りする前にザルツブルク音楽祭でロッシーニ《モーゼとファラオ》も観てきた。音楽面では良いところは多々あり、ことにROFで見出されたマリーナ・レベカ(アナイ役)が大喝采を浴びたのは嬉しかった。ところがユルゲン・フリムの演出がさっぱりつまらないもので、感興を大きく削いでいた。音楽祭総監督のフリムは、本来予定されていたイタリア人演出家が降りたために自ら演出に当たったそうだが、準備不足と作品理解の薄さが舞台に反映されてしまっていたように思う。
第6回・了