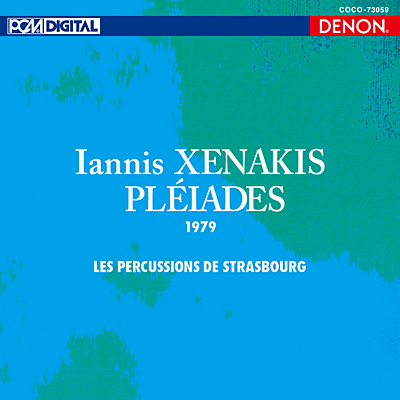音盤中毒患者のディスク案内
音盤中毒患者のディスク案内 No.50
クラシックメールマガジン 2017年9月付
~スティーヴィー・ワンダーの笑顔 ~ クセナキス/プレイヤード ストラスブール・パーカッション~
ストラスブール・パーカッションによるクセナキスの「プレイヤード」(COCO-73059)について文章を書こうとネットで調べものをしていて、偶然見つけた動画に釘付けになってしまいました。
それは、「音楽のノーベル賞」とも呼ばれるスウェーデンのポーラー賞の1999年の授賞式コンサートで、その年の受賞者ヤニス・クセナキスの「プレイヤード」の中の「Peux(太鼓)」を、クロウマタ・パーカッション・グループが演奏した映像。6人の打楽器奏者たちが、超快速テンポで激しくリズムを叩きつけながら、一糸乱れぬ超絶的なアンサンブルを聴かせています。
その演奏以上に印象的なのが、何度か映し出されるもう一人の受賞者スティーヴィー・ワンダーの姿です。客席で演奏を聴いている彼は、「こんな音楽があるのか!」とでも言いたげな驚きの表情を隠さず、ニコニコと満面の笑みを浮かべて音楽を楽しんでいます。曲の中盤、まるで鬼太鼓座のようなアンサンブルが繰り広げられる場面では、白い歯を見せてゲラゲラと隣席の人たちと笑い合ってもいる。 おいしそうにものを食べる人の姿を見ると、こちらまで幸せな気分になるのと同じように、スティーヴィー・ワンダーが感じた音楽の喜びが伝わってきて、もうそれだけで嬉しくなってしまいます。
その演奏以上に印象的なのが、何度か映し出されるもう一人の受賞者スティーヴィー・ワンダーの姿です。客席で演奏を聴いている彼は、「こんな音楽があるのか!」とでも言いたげな驚きの表情を隠さず、ニコニコと満面の笑みを浮かべて音楽を楽しんでいます。曲の中盤、まるで鬼太鼓座のようなアンサンブルが繰り広げられる場面では、白い歯を見せてゲラゲラと隣席の人たちと笑い合ってもいる。 おいしそうにものを食べる人の姿を見ると、こちらまで幸せな気分になるのと同じように、スティーヴィー・ワンダーが感じた音楽の喜びが伝わってきて、もうそれだけで嬉しくなってしまいます。
コンサートの場で、こんなふうに素直に音楽の喜びを表現できるというのは、素敵なことだと思います。勿論、公共の場なので度を超してはいけませんが、でも、聴衆がこれほど幸せそうに音楽を楽しんでいたら演奏する側も嬉しいだろうし、何より会場の雰囲気がグッと良くなるんじゃないでしょうか。
しかも、演奏されている曲は、没後16年を経た今も、バリバリの前衛と位置づけられる孤高の作曲家が書いた現代音楽。エンターテイメントを目的として書かれた訳ではなく、作曲者の言葉を借りれば「事象の集合体」としての音楽を目指して、様々な作曲技巧を駆使して書かれた曲。演奏にも相当な演奏技術も要する高度な芸術性を備えた音楽が、こんなにもあたたかく迎えられているなんて実に素晴らしい。
でも、動画を御覧になれば、あるいは、ストラスブール・パーカッションの音盤をお聴きになれば、スティーヴィー・ワンダーのあの喜びに満ちた表情は、「プレイヤード」が私たち聴き手に与えてくれるもの、つまり「楽しさ」を如実に表わしていることを実感して頂けるのではないでしょうか。
しかも、演奏されている曲は、没後16年を経た今も、バリバリの前衛と位置づけられる孤高の作曲家が書いた現代音楽。エンターテイメントを目的として書かれた訳ではなく、作曲者の言葉を借りれば「事象の集合体」としての音楽を目指して、様々な作曲技巧を駆使して書かれた曲。演奏にも相当な演奏技術も要する高度な芸術性を備えた音楽が、こんなにもあたたかく迎えられているなんて実に素晴らしい。
でも、動画を御覧になれば、あるいは、ストラスブール・パーカッションの音盤をお聴きになれば、スティーヴィー・ワンダーのあの喜びに満ちた表情は、「プレイヤード」が私たち聴き手に与えてくれるもの、つまり「楽しさ」を如実に表わしていることを実感して頂けるのではないでしょうか。
クセナキスの「プレイヤード」は、1978年、ストラスブール市の委嘱で、ライン・バレエ団の公演のために書かれた音楽で、前述のように6人の打楽器奏者アンサンブルによって演奏されます。全体の演奏時間は約43分で、ブラームスの交響曲1曲分くらいの長さ。
「混合」「金属」「鍵盤」「太鼓」というタイトルの4つの部分から構成され、使われる楽器は曲によって変わります。つまり、「金属」では、クセナキス自身が考案したジクセン(SIXXEN)という金属の板を並べたもの、「鍵盤」では、マリンバ、ビブラフォン、シロフォン、シロリンバなどの鍵盤類、「太鼓」ではティンパニや大太鼓などの太鼓、「混合」ではそれらすべての楽器が用いられます。
初演を担当したのは、このディスクで演奏をしているストラスブール・パーカッション。彼らは、1986年にハルモニア・ムンディに作曲者監修下で録音していますが、その2年後、東京の夏音楽祭出演のために来日した折、浦安でセッションを組んで再録音しました。
初演を担当したのは、このディスクで演奏をしているストラスブール・パーカッション。彼らは、1986年にハルモニア・ムンディに作曲者監修下で録音していますが、その2年後、東京の夏音楽祭出演のために来日した折、浦安でセッションを組んで再録音しました。
「プレイヤード」の楽しさとは、何しろ打楽器だけで演奏される曲ですから、言うまでもなく、まずリズムにあります。
何人かの奏者が同時に奏でたモチーフがだんだんずれていき、鳥の群れが空を飛ぶように、集合と離散を不規則に繰り返していく。しかも、すべての楽器の音程は微妙にずらされているので、聴こえてくるリズムは非常に複雑でとらえどころのないものになる。
性格の異なるエピソードが、入れ代わり立ち代わり現れ、目まぐるしく音楽の様相を変えていく。ロックのような激しいビートをもったリズムの応酬があるかと思えば、ガムランのような陶酔的な音の重なりが水平的に広がっていく。またある時には、勇壮な和太鼓合奏のようなアンサンブルが繰り広げられる。そんなシーケンスが積み重なり、やがて大きなうねりを生み出す。部分が全体であり、全体が部分であり、というような個と全体の裏返しを見せながら、音楽は曲がりくねった道を進む。やがて、独立した生命をもった音楽の包絡線をかたちづくって円環を閉じていく。
そんな「プレイヤード」のスリリングな生成過程に追随していると、耳と心は絶えず刺激を受け続け、どんどん活性化されます。何度も繰り返して聴いているうちに、だんだん耳が慣れてきて、複雑な音の綾が見えるようになってくると、ああ、ここにはこんな風景があったのか、こことここはこんな風に結びついているのかといろいろ気づく。
しかし、ジクセン、マリンバ、ティンパニなどの楽器への一打、それらの音の連なりにいったい何の意味があるのか、具体的に何かを表現しているかなどと考えを巡らせる暇はありません。新たな発見に満ちた音たちが、次から次へと押し寄せてくるからです。そこに明確な音楽のドラマがあるようにも思えないし、弁証法的なロジックが展開されているとも感じられない。ならばと肚を括って、音楽が作り出す波動にエイヤと身を任せていれば、ただひたすら「音」だけの世界の中へと分け入ることになります。
すると、昔、音楽に対する知識も経験もほとんどないまま、好きな音楽をただ夢中で聴いていたときに感じていた、手垢のつかないピュアな喜びがよみがえってきます。あるいは、神の仕業としか思えないような巨大な自然の造形に触れ、打ちのめされてポカーンと見ているときの感覚と通じるものがあるかもしれない。いずれにせよ、スティーヴィー・ワンダーが全身で表現していたキラキラしたものも、それらと同質のもので、聴き手の存在の根源から湧き上がってくるものに違いありません。
しかし、ジクセン、マリンバ、ティンパニなどの楽器への一打、それらの音の連なりにいったい何の意味があるのか、具体的に何かを表現しているかなどと考えを巡らせる暇はありません。新たな発見に満ちた音たちが、次から次へと押し寄せてくるからです。そこに明確な音楽のドラマがあるようにも思えないし、弁証法的なロジックが展開されているとも感じられない。ならばと肚を括って、音楽が作り出す波動にエイヤと身を任せていれば、ただひたすら「音」だけの世界の中へと分け入ることになります。
すると、昔、音楽に対する知識も経験もほとんどないまま、好きな音楽をただ夢中で聴いていたときに感じていた、手垢のつかないピュアな喜びがよみがえってきます。あるいは、神の仕業としか思えないような巨大な自然の造形に触れ、打ちのめされてポカーンと見ているときの感覚と通じるものがあるかもしれない。いずれにせよ、スティーヴィー・ワンダーが全身で表現していたキラキラしたものも、それらと同質のもので、聴き手の存在の根源から湧き上がってくるものに違いありません。
ただ、「プレイヤード」から感じとれる猛烈な力は、自然に生まれたものだとは思えません。とことん人工的、人為的につくられたものであって、何かとてつもなく大きな力への反撥、反作用なのではないかという気がします。
そのことは、クセナキスが、解読の難しいユニークなフォーマットの楽譜を使い、数学の理論を導入しコンピュータを使って計算して作曲したとか、コルビジュエの助手を務めた建築家でもあるとかいうようなエピソードとは、ほとんど関係がない。
それよりも、私たち聴き手を、ほとんど空っぽの状態にしてただ音だけに集中させ、それ以外のことは一切考える隙を与えないという作曲家の強い意志を、音楽の端々から感じずにいられないのです。
そのことは、クセナキスが、解読の難しいユニークなフォーマットの楽譜を使い、数学の理論を導入しコンピュータを使って計算して作曲したとか、コルビジュエの助手を務めた建築家でもあるとかいうようなエピソードとは、ほとんど関係がない。
それよりも、私たち聴き手を、ほとんど空っぽの状態にしてただ音だけに集中させ、それ以外のことは一切考える隙を与えないという作曲家の強い意志を、音楽の端々から感じずにいられないのです。
これは、徹底的に「言葉」と「意味」を拒絶した音楽なのではないでしょうか。
私たちは、普段、「言葉」と「意味」にまみれて生きています。人類は、森羅万象に言葉を与え、言葉でその謎を解明し、意味を探求していくことによって宇宙を理解し、科学や文明を発展させ、信じがたいような繁栄を築き上げてきた。でも、その一方で、ことに現代においては、「言葉」があるばかりに互いに争いが起こり、地球を破壊し、「意味」に傷つき、傷つけられながら生きている。その過程で、私たちは、祖先が脈々と受け継いできた豊かなものを多く失ってしまった。
クセナキス自身、第二次世界大戦や祖国ギリシャの内紛を経て、言葉にも意味にも裏切られ、失望を繰り返してきたに違いありません。だから、せめて、言葉も意味もない仮想世界を音楽のなかで作り出してユートピアを出現させ、その中で輝かしい人間性を取り戻したい。そんな強い願いが、彼の「プレイヤード」には込められているように思えます。
いや、たぶん、彼の他の曲にも、それはある。放物線を描くように積み重なるグリッサンドの果てに奏でられるトーンクラスターの轟音、12段にも及ぶピアノ譜からこぼれ出る複雑な音響、延々と叩き鳴らされる鐘の音、壊れたラジオのように鳴り続ける電気的なノイズ音、ギリシャ悲劇の殺人の場面で鳴り響く断末魔の叫び、そうした凶暴な音響の背後に隠れて見えにくくなっているだけ。彼は、聴き手を怯えさせ、威圧し、支配するために音楽を書いたのではないはずです。
クセナキス自身、第二次世界大戦や祖国ギリシャの内紛を経て、言葉にも意味にも裏切られ、失望を繰り返してきたに違いありません。だから、せめて、言葉も意味もない仮想世界を音楽のなかで作り出してユートピアを出現させ、その中で輝かしい人間性を取り戻したい。そんな強い願いが、彼の「プレイヤード」には込められているように思えます。
いや、たぶん、彼の他の曲にも、それはある。放物線を描くように積み重なるグリッサンドの果てに奏でられるトーンクラスターの轟音、12段にも及ぶピアノ譜からこぼれ出る複雑な音響、延々と叩き鳴らされる鐘の音、壊れたラジオのように鳴り続ける電気的なノイズ音、ギリシャ悲劇の殺人の場面で鳴り響く断末魔の叫び、そうした凶暴な音響の背後に隠れて見えにくくなっているだけ。彼は、聴き手を怯えさせ、威圧し、支配するために音楽を書いたのではないはずです。
クセナキス自身は、1984年におこなった武満徹との対談でこんなことを述べています。
芸術の分野における創造というのは、人間の改良していく、創造していく能力の中で一番豊かなものだと思うのです。その力を人間が持つことになれば、戦争の危険というものはより少なくなり、人間と自然との間に培われている関係の質というものはより豊かなものになるのではないかと考えます。政治や経済の話は多くされるけれども、自分たちの生に価値を与える、人生を生きる価値のあるものにする、それの話をすることを忘れているのではないかと思うのです。何かというと、それは、つくること ー 想像することだと思います。
「武満徹 対談選 仕事の夢 夢の仕事」(小沼純一編、ちくま学芸文庫)
創造という行為が、人間の生の価値を高め、平和へとつなげ、自然との関係も改善する。クセナキスの音楽にある「楽しさ」とは、彼が目指すそんなユートピアを創造する喜びだったに違いない。この「プレイヤード」という音楽には、特有の苛烈な不協和音やノイズが少ない分、作曲者の内部から溢れ出た「喜び」が裸のまま剥き出しになって現れている気がします。
音楽のこういう楽しさは、大人よりもむしろ子供の方が、素直に感じられるものなのかもしれません。年を重ねるうちに、私たちは言葉と意味にどっぷり浸かって生きてしまいますが、子供たちは必ずしもそうではない。もっと直感の中で生きている。ならば、大人のように知識や経験に惑わされることなく、まっすぐにクセナキスの音楽の楽しさを体感できるのではないか。だから、子供のためのコンサートとか、学校の音楽の教材として、この「プレイヤード」を聴かせてあげるといいんじゃないかと思ったりもしています。
「プレイヤード」の初演者ストラスブール・パーカッションによる演奏は、実に楽しい。前述の動画でのクロウマタの演奏は、確かにノリは良くて面白いのですが、反面、スピードに頼りすぎてしまっていて、各奏者がてんでバラバラに乱れ打ちするところがカオスになってしまっている嫌いがある。
一方、ストラスブールの面々は、心持ちテンポをゆっくりとり、各奏者の音のずれ具合を精緻に具現化しています。その「正確にずれていく」プロセスは快感で、やみつきになってしまいます。また、クロウマタの演奏より情報量がとても多く感じられ、音もたくさん聴こえるような気がするのは、それだけ精密に演奏されていることの証だと思いますし、作曲者自身の意図を十全に汲んだ結果に違いありません。 また、クロウマタのような激しいノリはないけれど、独特のスピード感があってかっこいい。しかも、作曲後10年を経ない時期の新しい音楽ということもあってか、音のエッジがいい具合に尖がっているのがまた嬉しい。特製楽器ジクセンの、金属的に過ぎず、たっぷりと共鳴した響きも、ミステリアスでいい。
録音当時、私も彼らの演奏する「プレイヤード」の実演を聴こうと思えば聴けたはずなのに、なぜ聴かなかったのか、いったい何をしていたのだろうかと残念に思いますが、でも、こうして優秀な録音で素晴らしい演奏が聴けることに感謝せずにはいられません。
一方、ストラスブールの面々は、心持ちテンポをゆっくりとり、各奏者の音のずれ具合を精緻に具現化しています。その「正確にずれていく」プロセスは快感で、やみつきになってしまいます。また、クロウマタの演奏より情報量がとても多く感じられ、音もたくさん聴こえるような気がするのは、それだけ精密に演奏されていることの証だと思いますし、作曲者自身の意図を十全に汲んだ結果に違いありません。 また、クロウマタのような激しいノリはないけれど、独特のスピード感があってかっこいい。しかも、作曲後10年を経ない時期の新しい音楽ということもあってか、音のエッジがいい具合に尖がっているのがまた嬉しい。特製楽器ジクセンの、金属的に過ぎず、たっぷりと共鳴した響きも、ミステリアスでいい。
録音当時、私も彼らの演奏する「プレイヤード」の実演を聴こうと思えば聴けたはずなのに、なぜ聴かなかったのか、いったい何をしていたのだろうかと残念に思いますが、でも、こうして優秀な録音で素晴らしい演奏が聴けることに感謝せずにはいられません。
「プレイヤード」は、最近、加藤訓子が一人で多重録音した英Linnレーベルの音盤がリリースされて、大きな話題となりました。それは、クセナキスの音楽の美しさを明らかにした快演でしたが、実演で取り上げられる機会はまだ少なく、ディスクもあまり多くはない。
でも、昨今は、目覚ましい技量をもった若い音楽家たちが次々に出てきて、現代音楽も軽々と楽しげに弾く人が増えてきました。ならば、若いパーカッショニストたちとDENONの優秀な録音スタッフの手で、この「プレイヤード」という音楽像をアップデートするような、刺激的な音盤が聴きたいと思います。この曲は、本来、6人の演奏家たちを、聴衆が360度囲んで演奏することを想定されていたそうなので、その特殊な音響効果をSACDのマルチチャンネルで再現できるのではないでしょうか。聴き手が空間を移動したら、音場もそれに追随して変わるなどの体験もできれば面白そうです。
でも、昨今は、目覚ましい技量をもった若い音楽家たちが次々に出てきて、現代音楽も軽々と楽しげに弾く人が増えてきました。ならば、若いパーカッショニストたちとDENONの優秀な録音スタッフの手で、この「プレイヤード」という音楽像をアップデートするような、刺激的な音盤が聴きたいと思います。この曲は、本来、6人の演奏家たちを、聴衆が360度囲んで演奏することを想定されていたそうなので、その特殊な音響効果をSACDのマルチチャンネルで再現できるのではないでしょうか。聴き手が空間を移動したら、音場もそれに追随して変わるなどの体験もできれば面白そうです。
それにしても、「プレイヤード」を聴くスティーヴィー・ワンダーのように、あんなふうにニコニコと音楽を楽しみたいものだと、しみじみ思います。楽しい音楽を聴いたから楽しくなるというのも良いですが、楽しい気分で音楽を聴いたから音楽も楽しく聴こえる、という聴き方も、あっていいんじゃないかと思います。そんな聴体験を実践するためにも、これからはなるべく口角をあげながら音楽を聴こうかと思います。私がやるとただの変なおじさんになってしまいますが。
※クロウマタが演奏するクセナキスの「Peux(太鼓)」の動画は、「Xenakis Peux Kroumata」と入力して検索すればすぐに見つけられます。クセナキスの曲をクロウマタがカバーしたというようなタイトルがなかなか味わい深いです。
-
粟野光一(あわの・こういち) プロフィール
1967年神戸生まれ。妻、娘二人と横浜在住。メーカー勤務の組み込み系ソフトウェア技術者。8歳からクラシック音楽を聴き始めて今日に至るも、万年初心者を自認。ピアノとチェロを少し弾くが、最近は聴く専門。CDショップ、演奏会、本屋、映画館が憩いの場で、聴いた音楽などの感想をブログに書く。ここ数年はシューベルトの音楽にハマっていて、「ひとりシューベルティアーデ」を楽しんでいる。音楽のストライクゾーンをユルユルと広げていくこと、音楽を聴いた自分の状態を言葉にするのが楽しい。